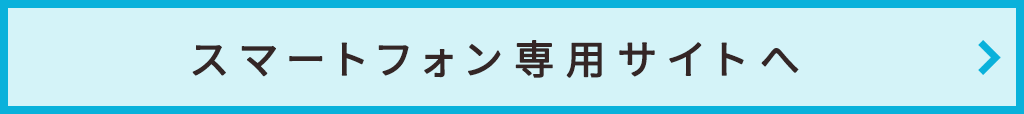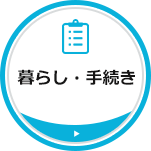介護保険における例外給付等について
制度の趣旨について
介護保険制度では、原則として国が定めた基準に基づきサービスの提供や給付が行われます。利用者の個別事情により通常の基準では給付が認められない場合でも、一定の条件を満たせば「例外的に給付」が認められる制度です。
※ 要支援者の場合は、地域包括支援センターへお問い合わせください。
申請・届出がいるケース
提出に必要なものは、下記の項目をご参照ください。
申請がいるケース
・同居家族がいる場合の生活援助
:同居家族等に介護認定および障害手帳を持っていない方がいる場合
(それ以外の場合、居宅サービス計画等をご提出していただく必要がございます。)
・軽度者に対する福祉用具の貸与
:厚労省が定める状態像を認定調査票から確認できない場合
(それ以外の場合、居宅サービス計画等をご提出していただく必要がございます。)
届出がいる場合
以下の例外給付を算定するすべての場合において
・通院・院内介助
・規定回数を超える訪問介護(生活援助中心型)
・認定有効期間の半数以上を超える短期入所

承認期間に関して
例外給付の承認期間は、“状況に変化があるときまで”とし、基本的には“認定有効期間”といたします。ただし、状態が短期間で変わると見込まれる場合は、承認期間を調整する場合がございます。
これまでは承認期間を1年以内としておりました。承認期間は長くなりますが、これまでと同様モニタリングの際には、他のサービスと同様に必ず例外給付の必要性を判断し、必要でないと判断された場合は速やかにサービスを終了させてください。
なお、承認期間終了後も引き続いて例外給付となるサービスの給付が必要な場合は申請が必要となりますのでご注意ください。
※ 承認期間が現状1年程度となっている場合(認定有効期間が例外給付の承認期間よりも短い場合)は、承認有効期間の終了日を認定有効期間終了日に読み替えてください。
申請等に先行してサービスを実施する場合
必ず、サービス実施前に事前にご相談ください。なお先行でサービスの実施後、届出内容を確認・検討する段階で、サービスの実施内容を変更していただく可能性がございますので、あらかじめご留意ください。
提出方法
留意事項
- 例外給付のサービスを行う場合は、サービス担当者会議において例外給付に関するサービス内容について必ず議題として検討し、居宅サービス計画の第4表等の様式に記載してください。
- 一度届出等を行った例外給付に関して、居宅サービス計画変更後も継続して例外給付となるサービスを実施される場合、必ずサービス担当者会議で議題として検討のうえ、その理由を申請書、届出書および居宅サービス計画等に明記してください。
各種例外給付に関して
同居家族の生活援助の算定に関して
1.制度の趣旨
介護保険における「生活援助」とは、掃除・洗濯・調理・買い物などの日常生活上の家事支援を対象としています。
厚生労働省の基準では、以下のように定められています。
「利用者と同居する家族等がいる場合であっても、障がいや疾病等により家事を行うことが困難な場合には、生活援助の算定が可能である。」
つまり、同居家族がいることにより一律に生活援助が認められないわけではなく、家族自身の介護・支援状況や障がいの有無等が考慮されます。
厚労省:同居家族等がいる場合における訪問介護サービス等の生活援助の取扱いについて
2-1.申請がいるケース
- 要介護認定もしくは障がいの認定のない同居家族等がいる場合に、生活援助のサービスを行う場合
- 生活援助のサービス内容を変更もしくは増加する場合(軽微な変更は除く)
- 区分変更により、認定有効期間が変更となった場合
提出物
-
承認申請書
-
居宅サービス計画書 第1表 ~ 第4表
-
アセスメントシート
※ 状況により、居宅サービス計画第6表・第7表、モニタリング結果、及び支援経過記録及等を求めることがあります。
2-2.申請が不要なケース
同居家族全員が、要介護・要支援の認定を受けているもしくは障がい者手帳を持っている場合
提出物
-
居宅サービス計画書 第1表 ~ 第4表
-
アセスメントシート
※ 状況により、居宅サービス計画第6表・第7表、モニタリング結果、及び支援経過記録及等を求めることがあります。
3.各種様式
同居家族がいる場合の生活援助算定 申請書 (Excelファイル: 25.8KB)
4.注意事項
- 単に、障がいや要介護であるからという理由では生活援助を算定することはできません。利用者本人及びご家族へ希望を確認し、その疾病等によって具体的にどのような家事がなぜ困難なのかを分析し、サービス担当者会議を通じた適切なケアマネジメントにより必要性を判断してください。(サービス担当者会議の記録には、検討した内容を具体的に記録してください。)
- 生活援助の算定を身体介護との組み合わせの場合でも申請が必要となります。
- 家族の就労等により、長時間にわたり日中不在となり、利用者のための必要な家事・日常生活上の介助に限りがある場合においても、家族が不在の時間帯に行われなければ日常生活に大きな支障が生じることを明確にする必要があります。家族が滞在している時間帯(夜間及び休日)において対応することで差し支えない場合は、援助の対象になりません。
- 二世帯住宅や同一敷地内別棟に家族が居住している場合でも、生活の実態から実質的に同居とみなされる場合は、同居家族がいる場合の生活援助の算定となります。
軽度者に対する福祉用具の貸与
1.制度の趣旨
要介護1・2(軽度者)に対しては、介護保険制度上、原則として以下の福祉用具は貸与の対象外とされています。
車いす・車いす付属品、特殊寝台・特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器
手すり(工事を伴わないもの)、スロープ、歩行器、歩行補助つえ
ただし、厚生労働大臣が定める告示に該当する対象者については、要介護認定における基本調査結果等に基づく判断があった場合や、または、市町村が医師の所見・ケアマネジメントの判断等を書面等で確認の上、要否を判断した場合には、例外的に給付が可能となっております。
例外的に福祉用具の貸与が可能となる状態像(厚生労働省告示第94号第31号のイに定める状態像):
〇状態が変動しやすく、日によってまたは時間帯によって頻繁に必要となる者
例:パーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象(急激な症状の改善と悪化を繰り返す)により、日によってあるいは時間帯によって、車いすや特殊寝台が必要となる場合。
〇状態が急速に悪化し、短期間のうちに必要となることが確実に見込まれる者
例:がん末期等、疾病の進行により急速に状態が悪化し、近いうちに車いすや特殊寝台、床ずれ防止用具などが必要となることが確実である場合。
〇身体への重大な危険性または症状の重篤化を回避するために医学的に必要と判断される者
例:ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避等、医学的判断から特定の福祉用具がなければ生命に危険が及ぶ、または症状が重篤化するおそれがある場合。
2-1.申請がいるケース
- 直近の認定調査・主治医意見書において、厚労省が認める「状態像」(下表)に該当しない場合
- 該当する、基本調査項目がない場合(車いす及び車いす付属品 移動用リフト(つりぐの部分を除く))
- 福祉用具の品目が変わる、品目が増える場合
- 区分変更により認定有効期間が変更になった場合
- 例外給付の有効期間は終了するが、引き続き例外給付が必要な場合

要支援・要介護1の者に対する福祉用具貸与の判断
提出物
-
承認申請書
-
居宅サービス計画 第1 ~ 4表
-
アセスメントシート
-
医学的な所見を確認できるもの(主治医の診断書、居宅サービス計画作成担当者が聴取した記録等)
※ 状況により、居宅サービス計画第6・7表、モニタリング結果、支援経過記録及び訪問介護計画等を求めることがあります。
2-2.申請が不要なケース
直近の認定調査・主治医意見書の結果において、厚労省が定める「状態像」に該当する場合
提出物
-
居宅サービス計画 第1 ~ 4表
-
アセスメントシート
-
医学的な所見を確認できるもの(主治医の診断書、居宅サービス計画作成担当者が聴取した記録等)
※ 状況により、居宅サービス計画第6・7表、モニタリング結果、支援経過記録及び訪問介護計画等を求めることがあります。
3.各種様式
軽度者への福祉用具貸与 申請書 (Excelファイル: 159.8KB)
様式1号 軽度者に対する福祉用具貸与の対象外種目に係る 主治医からの診療情報提供書(医師記載様式) (Wordファイル: 26.3KB)
様式2号 軽度者に対する福祉用具貸与の対象外種目に係る 主治医からの診療情報提供書(所見聴取記録様式) (Wordファイル: 25.7KB)
4.注意事項
- 医学的な所見については単に病名が記載されているのみではなく、明確に例外給付の必要性がわかる内容が記載されてることが必要となります。
- 単に「あったら便利」という理由や介護者の負担軽減のみを目的とする場合では算定の対象とはなりません。
- 確認した医学的所見を踏まえ、サービス担当者会議の開催時には福祉用具専門員その他サービス提供事業者と検討してください。(サービス担当者会議の記録には、検討した内容を具体的に記録してください。)
通院・院内介助
1.制度の趣旨
訪問介護における「通院・院内介助」は、利用者が医療機関を受診する際に提供されるサービスですが、院内介助については、例外的な給付として位置づけられており、保険者の判断により場合により算定対象としています。これは、医療機関内での介助は本来、医療機関のスタッフが行うという原則があるためです。
厚労省:「通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合」及び「身体介護が中心である場合」の適用関係等について
届出に関して
通院・院内介助を居宅サービス計画に位置付ける場合は、原則としてサービス実施前までに下記の資料をご提出ください。
提出物
- 届出書
- 居宅サービス計画 第1~4表
※ 状況により、居宅サービス計画第6・7表、訪問介護計画書及び支援経過記録等を求めることがあります。
3.各種様式
通院・院内介助 届出書 (Excelファイル: 20.3KB)
4.注意事項
- 病院スタッフによる対応が可能な場合や情報提供のみを目的とする場合は、算定の対象となりません。
- サービス担当者会議を開催し、適切なケアマネジメントにより当該被保険者の心身の状況や院内の状況等を勘案し特に必要であるかどうかを判断してください。(サービス担当者会議の記録には、検討した内容を具体的に記録してください。)
基準回数以上の訪問介護(生活援助中心型)
1.制度の趣旨
介護保険における訪問介護サービスのうち、生活援助中心型サービスについては、利用者の状態像や介護度に応じて、厚生労働大臣が定める「規定回数」が設定されています。
- 要介護1:27回
- 要介護2:34回
- 要介護3:43回
- 要介護4:38回
- 要介護5:31回
厚労省:「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の公布について
2.届出に関して
田原本町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例第15条第20号に基づき、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を居宅サービス計画に位置付ける場合は、原則サービス実施前までに下記の資料をご提出ください。また、適正性を確認するため、初回届出時には、計画作成担当のケアマネジャーを交えた検討会議を実施いたします。
提出物
- 届出書
- 居宅サービス計画 第1~4表 第6・7表
- 支援経過記録
※ 状況によりモニタリング結果及び訪問介護記録等を求めることがあります。
3.各種様式
規定回数を超える訪問介護(生活援助中心型) 申請書 (Excelファイル: 21.7KB)
4.注意事項
- この規定回数を超えてサービスを算定する際には、利用者にとってそのサービスが本当に必要不可欠であること、そして他のいかなる資源や方法でも対応できないことをが必要があります。
- 1回の訪問介護において身体介護及び生活援助が混在する場合(生活援助加算を算定している場合)の回数を含みません。
- サービス担当者会議を開催し、適切なケアマネジメントにより当該被保険者の心身の状況や介護の状況等を勘案し特に必要であるかどうかを判断してください。(サービス担当者会議の記録には、検討した内容を具体的に記録してください。)
認定有効期間の半数を超える短期入所サービス
1.制度の趣旨
介護保険制度では、短期入所生活介護(ショートステイ)は、在宅生活を継続する上での一時的な支援として位置づけられています。
そのため、在宅での生活が基本にあることを前提とするサービスであり、施設入所の代替として長期的・恒常的に利用することは本来の趣旨と異なります。
2.届出に関して
田原本町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例第15条第15号に基づき、介護認定の有効期間のうち、短期入所サービスの利用日数が半数(全体の50%)超えることが見込まれる時点で下記の資料をご提出ください。
提出物
- 届出書
- 居宅サービス計画 第1~4表
※ 状況により、居宅サービス計画第6・7表、モニタリング結果、支援経過記録及び訪問介護記録等を求めることがあります。
3.各種様式
認定有効期間の半数を超える短期入所 届出書 (Excelファイル: 22.1KB)
4.注意事項
- 短期入所はあくまでも「在宅生活の支援」となっているため、他の在宅サービス等デイサービス、訪問介護、地域資源など)の活用状況や、施設入所の可能性も含めて検討してください。(在宅へ復帰する希望があるかどうかを分析してください。)
- サービス担当者会議を開催し、適切なケアマネジメントにより当該被保険者の心身の状況や介護の状況等を勘案し特に必要であるかどうかを判断してください。(サービス担当者会議の記録には、検討した内容を具体的に記録してください。)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
担当課:長寿介護課介護保険係
電話:0744-34-2101