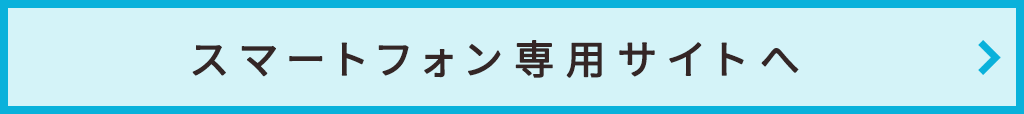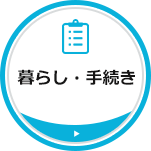平成20年田原本町議会第1回定例会会議録(第2日)
2008年7月1日更新
平成20年3月4日
午前10時00分 開議
於田原本町議会議場
出席議員
14名
1番
古立憲昭君
2番
西川六男君
3番
竹邑利文君
4番
辻一夫君
5番
吉田容工君
6番
植田昌孝君
7番
松本美也子君
8番
小走善秀君
9番
吉川博一君
10番
松本宗弘君
11番
上田幸弘君
12番
安達周玄君
13番
竹村和勇君
14番
欠員
15番
欠員
16番
鶴藤幾長君
欠席議員
0名
出席した議会事務局職員
議会事務局長
取田弘之君
議事係長
谷口定幸君
地方自治法第121条の規定により出席した者
町長
寺田典弘君
副町長
森口淳君
総務部長
福西博一君
総務部参事
石本孝男君
住民福祉部長
中島昭司君
生活環境部長
小西敏夫君
産業建設部長
森島庸光君
水道部長
渡邉和博君
総務課長
吉川建君
監査委員
楢宏君
教育委員長
大西宏興君
教育長
濱川利郎君
教育次長
森本至完君
会計管理者
東口豪君
選挙管理委員会事務局長
安部和夫君
農業委員会事務局長
鍬田芳嗣君
議事日程
日程1 一般質問
2番 西川六男議員
- 田原本町の教育を充実するために
・3月末教職員の人事について - 放課後子どもプランについて
・その取り組みについて - 子育て支援のために
・放課後児童健全育成事業(学童保育)の充実について - 安全・安心の街づくりのために
・AED(自動体外式除細動器)の普及について
1番 古立憲昭議員
- 地方分権について
- 行政経営と行政評価について
- 学習指導要領の改訂について
7番 松本美也子議員
- 高齢者対策として
1.「介護保険の住宅改修費の受領委任払い制度」の創設について
2.「後期高齢者医療制度」の円滑化のための取り組みについて - 災害に強いまちづくりとして
・学校施設及び公共施設における防災機能の充実について - 妊産婦にやさしい環境づくりとして
・マタニティマークの活用、推進について
11番 上田幸弘議員
町の環境政策について
- 清掃工場操業に関する協定書について
- 清掃工場の基本的な計画について
- 計画策定プロセスにおける住民参加について
- 排ガス規制について
- ごみ減量を目的としたフリーマーケットの開催について
8番 小走善秀議員
町民の安全・安心
- 食の安全、安心
・学校給食について - 環境の安全、安心
・野焼き、不法投棄の対応について
5番 吉田容工議員
- 税金の徴収姿勢について
1.町長の課税、徴税に関する方針は
2.滞納者の生活実態を把握しているのか。 - 情報公開について
・土地開発公社を対象としないのか。 - 農業施策について
1.町長の農業施策の方向性、課題、目的は
2.新産地づくり対策交付金を山来高制に変えないか。
3.農業振興の町長のビジョンは
本日の会議に付した事件
議事日程に同じ
議事録
午前10時00分 開議
議長(松本宗弘君)
ただいまの出席議員数は14名で、定足数に達しております。よって議会は成立いたしました。
これより本日の会議を開きます。
日程に入ります。
一般質問
議長(松本宗弘君)
一般質問を議題といたします。
なお、質問については、会議規則第63条において準用する第55条の規定により3回を超えることはできません。
それでは質問通告順により順次質問を許します。2番、西川議員。
(2番 西川六男君 登壇)
2番(西川六男君)
議長の許可をいただきましたので、町民の皆様を代表して質問をいたします。
本年度も年度末が近づきましたが、本年度末で町内の幼稚園の園長先生お1人、小学校の校長先生2名が定年を迎えられると聞いております。また、教職員の方々の退職や転勤のご希望なども、すでに教育委員会として掌握され、3月末教職員人事に向けて取り組みが進んでいるものと推察いたします。教育委員会の教育行政の姿勢は人事にあらわれますけれども、田原本町教育委員会の姿勢、とりわけ昨年4月に就任いただきました濱川教育長の手腕が問われるときであります。教職員の人事につきましては、保護者や地域の方々の関心が大変高いわけですが、平成20年3月末の教職員人事について、田原本町教育委員会としてどのような方針で取り組もうとしておられるのか、町民の皆様にお示しをいただきたいと思います。
さて、先日、ある小学生の子どもをお持ちのお母さんから「子どもが放課後や週末などに学校などで活動する放課後子どもプランのことが新聞に載っていましたが、田原本町はどうなっているのでしょうか」と質問されました。すべての学校区で放課後の子どもの安全で健やかな活動場所を確保し、総合的な放課後対策として「放課後子ども教室推進事業」と「放課後健全育成事業」いわゆる学童保育を一体的あるいは連携した「放課後子どもプラン」の実施について、田原本町としてどのようにお考えか、その方針をお聞きしたいと思います。また、その主管をどこの部署、課にされるのか、あわせてお答えをいただきたいと思います。
その「放課後子どもプラン」の方針は、当然、放課後児童健全育成事業、いわゆる学童保育に関連しますので、中身の細部については今後委員会で質問したいと考えておりますけれども、基本的な事項について関連して質問をさせていただきます。
学童保育については、保護者から「対象学年を6年生まで拡充してほしい」「保育時間を午後7時まで、せめて6時半まで延長してほしい」など、充実を求める切実な意見が多くありますが、今後、放課後子どもプランの策定に当たって、これらの意見をどのように実現し、町民の皆様の願いに応えていくのか、子育て支援の観点からお考えをお示しいただきたいと思います。
次に、安全、安心のまちづくりにかかわりまして、AED(自動体外式除細動器)について、教育委員会所管の施設の状況についてお尋ねをしたいと思います。
先日、ある女性の方から次のようなお話がありました。「私の伴侶が、会社で心臓発作を起こし、備えつけのAEDで電気ショックを与え、一命を取りとめることができました。新聞に、奈良県の公立学校のAEDの設置率が全国最悪と載っておりましたけれども、田原本町の小、中学校は設置されているのでしょうか」との、自分の経験に基づくご質問をいただきました。その新聞記事によりますと、県内では平成19年度末時点で、県内幼稚園、小学校、中学校、高校を含めた公立学校での設置率は11.1%で、全国一低い状態になっております。奈良県教育委員会の矢和多教育長は「全国の設置状況から大きく遅れ大変あせっている。6月までには全県立学校に設置する方針で、各市町村教委の整備を促す」と述べています。
田原本町でも、安全、安心のまちづくりのためにAEDを早急に公共施設に設置すべきです。本町の教育委員会所管の公共施設における設置状況、とりわけ幼稚園、小学校、中学校の設置の状況と今後の予定及び、本年度小学校へ設置をしていただけるようでありますけれども、設置時期についてはどのように考えておられるのか。また、使用方法等の普及の取り組みと今後の対応についてどのように考えているのか、お答えをいただきたいと思います。以上で質問を終わります。
再質問は自席で行います。
議長(松本宗弘君)
教育長。
(教育長 濱川利郎 登壇)
教育長(濱川利郎君)
おはようございます。
2番、西川議員のご質問にお答えいたします。
まず第1番目の、田原本町の教育を充実するために、3月末教職員の人事についてのご質問にお答えいたします。
教職員の人事異動に関しましては、奈良県教育委員会が定めました「平成20年4月教職員人事異動方針」に基づいて行っております。基本方針には、教育に対する県民の期待と要望に応え、学校教育の一層の進展を期するため人事行政の秩序を保ち、公正にして適切な人事異動を行うとしております。本町におきましても、この方針を重く受け止めて人事行政を進めているところでございます。
この方針の中にも触れていますが、さらに平成19年第1回定例会に「平成19年3月末人事について」ご質問いただき、そのときにお答えさせていただいたことと重なるように思いますが、その点も踏まえてお答えしたいと思います。特に最近は、ご存じのように、10年長期勤務という形で広域人事が進められ、田原本町から外の教育現場へ、反対に他市町村から田原本町へお越しいただく先生が多くなっているのが現状でございます。また、田原本町外の教育現場での経験をお積みいただいた上で田原本町へ戻っていただき、本町の教育に携わっていただくという流れも今までと大きく変わっていないことでございます。
さらに質の高い人材、地域に根差す人材を求めることは田原本町だけではなく、奈良県下の流れでもあります。今後、県教育委員会とともに教職員人事にかかわっていくわけでございますが、本町の学校教育充実のために、両者が情報を密にして進めてまいりたいと考えております。
以上でございます。
2番目、4番目のご質問につきましては、教育次長から答弁させます
議長(松本宗弘君)
教育次長。
(教育次長 森本至完君 登壇)
教育次長(森本至完君)
それでは続きまして、2番目と4番目につきまして私のほうから答弁させていただきますので、どうかよろしくお願い申し上げます。
まず、2番目のご質問、「放課後子どもプラン」の実施についてどのように考えているかとのご質問でございますが、放課後子どもプランは、地域社会の中で放課後や週末等に子どもたちが安全で安心して健やかにはぐくまれるよう文部科学省の「放課後子ども教室推進事業」として創設されました。
この事業は、子どもたちの適切な遊びや生活の場を確保したり、小学校や公民館等を利用して地域の方々の参画のもと、学習やスポーツ、文化活動等に地域性を生かし、各校区単位で実施するものでございまして、本町におきましても、今後各関係機関とも相談しながら、実施に向け検討してまいりたいと考えております。また、その主管はどこの部署かとのご質問でございますけれども、教育委員会の生涯教育課で担当する予定でございます。
次に、4番目の安全、安心のまちづくりのためにAED(自動体外式除細動器)の普及についてのご質問より、公的施設における設置状況及び使用方法等の普及の取り組みと今後の対応につきましては、平成18年第1回定例会におきまして、古立議員よりAEDの設置の普及促進と講習についてのご質問がございましたので、その後の進捗状況等につきましては、西川議員のご質問とあわせてお答えさせていただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
まず、幼稚園、小学校、中学校の設置状況と今後の予定についてのお尋ねでございますが、平成19年度末時点で、田原本中学校、北中学校にはそれぞれ設置いたしております。また、小学校5校につきましては、平成20年度予算確定後に早急に設置する予定をいたしております。
なお、公的施設における設置状況につきましては、平成18年度に本庁舎、ふれあいセンター、青垣生涯学習センター、磯城休日応急診療所及び老人福祉センター、また平成19年度には中央体育館に設置したところでございます。また、使用方法等の普及の取り組みと今後の対応につきましては、設置当初にそれぞれの所管課職員を対象として講習を実施したところであり、今後も必要に応じて実施してまいりたいと考えております。なお、磯城消防署内で、月1回でございますが、広く一般の方々を対象とした応急手当講習会の中で、AEDを用いた応急手当を実施されているところでございます。
以上、私からの答弁とさせていただきます。ありがとうございました。
議長(松本宗弘君)
住民福祉部長。
(住民福祉部長 中島昭司君 登壇)
住民福祉部長(中島昭司君)
それでは2番、西川議員のご質問の3番目の子育て支援につきましてご答弁を申し上げます。
「放課後児童健全育成事業(学童保育)の充実について」のご質問についてお答えをいたします。
放課後プランの方針に関連し、いわゆる学童保育の対象学年を6年生までに拡充してほしい、保育時間を午後7時まで、せめて6時30分まで延長してほしい、との意見に対する本町の考えでございますが、まず対象年齢の拡充につきましては、児童福祉法にも、おおむね10歳未満の就学児童となっておりますことから、保育時間の延長も含めて、現行の体制で運営をしてまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りますようお願いを申し上げます。
以上でございます。
議長(松本宗弘君)
2番、西川議員。
2番(西川六男君)
ただいま3月末の教職員人事について、田原本町教育委員会のお考えをお示しいただきましたけれども、このことにかかわりまして再度質問をしたいと思います。
ご存じのように、今日、社会が大きく変化をしております。今学校では、児童、生徒が生き生きと笑うことのできる教育の環境を整えること、また、保護者や地域に信頼される学校づくりを推進する自立的な学校運営が求められております。そのために校長の責任と権限のもとで、教職員が学校組織の一員としてさまざまな課題に適切に対応して、組織的な教育力を発揮していかなければなりません。そのため、リーダーとしての校長の資質、これが大変重要になってくると思います。
本年度は2人の小学校の校長先生が定年退職なさいます。それに今後二、三年で、現在お勤めいただいている多くの管理職の方々の退職を迎えると思います。その中で、今後確固たる教育理念を持った質の高い管理職の確保が重要になります。また、多くの課題をかかえる今日の学校教育において、使命感や情熱、さらには実践的な指導力など、資質や能力を持ち、家庭や地域との連携を大切にして児童、生徒に寄り添い、人間としての豊かな成長を支援していくことのできる熱心な教職員の確保も、田原本町の教育行政の最重要課題であります。今後、団塊の世代の教職員の大量退職を迎えて、大量の教職員採用が行われることになります。このときに、学校力の低下を招くことのないように、将来を見通した人事構想が早急に求められております。人事を行う上で優秀な管理職や教職員の方々を具体的にどのような方法で確保しようと考えておられるのか、お聞きをしたいと思います。
この人事のありようにつきましては、先ほどの答弁の中にもありましたように、私は、平成19年第1回の定例会、3月議会で、次のような意見を申し上げました。田原本町で勤務していただく教職員の方々に、田原本町の地域の特色を理解し、経験を多く積んでいただきたい。そして教育委員会としても頑張っている教職員を正しく評価し、その方々のやる気の出る、その力を十分発揮できる人事を行うなど、人事面でも大切にしていただきたいこと、また、将来管理職として学校経営にその力を発揮することを望む教職員には、管理職任用のために他郡市を経験するなどの条件を整えて、また田原本町に帰っていただく、そして地域の実情を理解し、地域に根差した教職員が、地域の方々や保護者と一緒になってつくる地域の学校づくりに向けた人事を計画的に行うべきである、などと私の意見を申し上げました。
さらにそのために地教行法(地方教育行政の組織及び運営に関する)などの法律等の改正によりまして、校長の具申権の尊重や、地教委の内申権の積極的活用により、田原本町の子どもと教育を守るという確固たる教育理念を持って教育行政を行うために、県教育委員会に対して人事についてはイエス、ノーを行使いただきたいとも述べました。平成19年4月の教職員人事を見たときに、例えば、一つの学校の校長、教頭が同時に2人とも転勤され、新しく校長、教頭の2人とも他郡市から転任して来られました。さらにその学校の学校事務職員も入れ替わるという人事がありました。人事でございますので、いろいろ事情があったとは推察をいたしますけれども、教育現場から見たときに、学校経営や学校運営からの混乱と、地域や保護者の不信を招くのではないかと私は危惧いたします。
先ほどの答弁の中で、広域人事の問題を取り上げていただきましたが、その県教委の人事方針を踏まえて、田原本町の子どもと教育、これを守るために、本年度初めて人事を行われる濱川教育長に以上申し上げました私の意見についてどのようにお考えになるのか、再度お聞きをしたいと思います。
引き続きまして、放課後子どもプランに関連して質問をいたします。
ただいま回答をいただきましたけれども、実施に向けて来年度、平成20年度に具体的に検討するとのお答えだと理解をいたします。文部科学省は、放課後子ども教室推進事業につきましては、本年、平成19年度には、18年度比較の約3倍の68億2,000万円を予算計上し、全国1万箇所の設置を目指しておりました。私の調べたところによりますと、奈良県下では、生駒市、大和郡山市、香芝市、葛城市、安堵町、上牧町、広陵町、川西町、三郷町、御杖村、十津川村の11市町村、34教室、32小学校区ですでに実施をしておられます。
例えば川西町では、結崎子ども会、唐院子ども会の2教室で、なぎなたや空手、剣道などを練習するスポーツ活動と、合唱・練習の文化活動を取り入れた体験活動を実施しておいでになります。文部科学省では、さらに平成20年度には77億7,000万円を予算化し、平成19年度よりも5,000カ所ふやして1万5,000カ所として、すべての小学校区での実施を目指すとしております。そのため奈良県下でも、放課後子ども教室を実施する市町村がさらに増加するものと考えられます。
田原本町では、この平成20年度に検討して来年度に実施を目指すようでありますけれども、平成19年度実施の市町村、例えば隣りの川西町や広陵町よりも2年遅れることになります。ぜひ早急にご検討いただいて、遅れた分、本事業の趣旨に沿った地域や保護者の期待に応えられる充実した内容で、他市町村のモデルとなるような取り組みにしていただきたいと思います。この点について、指導する主管部局のお考えをお答えいただきたいと思います。
この取り組みを行うためには、学校、学童保育、社会教育、児童福祉、PTAなど関係者及び地域住民などで構成する運営委員会を設置したり、意見交換や協力体制の構築、学校や関係機関、団体などとの連絡、調整、活動プログラムの企画策定などを行うコーディネーターの選任と配置など、取り組まなければならない課題も多くあります。このように、この事業を定着、促進する上で、地域と保護者と、そして学校の理解と協力が不可欠だと思います。そのために、直接の主管をすることとなりました教育委員会の生涯教育課、とりわけ担当者の職務は重要であると考えます。また、検討される内容や方向性によっては、学校施設を利用することにもなりますけれども、利用については管理職はもちろんのこと、施設を活用し、日々授業等教育活動を行っている教職員の理解と協力を得ることも必要になります。そのため、この事業を実効のある、効果のある事業を行うためには、地域の実情や学校教育の現場のありようを理解していることが大切ではないかと考えます。この点について、中心的に推進すべき部局の責任者はどのようにお考えになっているのか、お答えをいただきたいと思います。
以上、よろしくお願いいたします。
議長(松本宗弘君)
教育長。
教育長(濱川利郎君)
ただいま西川議員から、人事にかかわって大変貴重なご意見をいただきましたこと、このことをまた参考にしながら、今後の人事に生かしていきたいなと、こう思います。
そこで一つだけつけ加えでございますが、確かに今の学校教育は、求められている点が大変多いと思います。そのためにも校長のリーダーの資質及びそれを支えていく教職員が、やっぱり一体となって学校運営、あるいは子どもたちの学習指導、生徒指導、あるいは生活指導等々を含めてかかわっていくような、そのような姿勢をたえず校長を通して学校へ伝え、そして学校は一丸となって地域を巻き込み、あるいはまたPTAとの連携を密にしなが今後進めていきたいと思います。そういう理念に立って教育行政、特に人事行政をさらに今後県と十分連絡を図りながら進めてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。
本当に貴重なご意見をいただきまして、参考にさせていただきたいと思います。ありがとうございます。
議長(松本宗弘君)
教育次長。
教育次長(森本至完君)
放課後子どもプランにつきましては、いろいろご意見をいただきましてありがとうございます。先ほどおっしゃっていただいたように平成20年度には準備年度として考えております。準備と言いましても、かなりの事務量がございます。それを踏まえて平成21年度実施に向けて関係機関とも十分協議してまいりたいと、このように考えております。
それから、所管になります生涯教育課につきましては、課長のほうで十分いろいろ勉強もしておりますので、具体的に進めてくれると、私はそのように考えております。
以上でございます。
議長(松本宗弘君)
2番、西川議員。
2番(西川六男君)
いまご答弁いただきました濱川教育長は、これまで田原本町の教育の充実、発展に大きな貢献をしていただいております。また県の教育委員会や他郡市の教育現場などの経験も積んでおいでになります。その濱川教育長の教育行政全般につきましても、その手腕に大いに期待をするところであります。特に今回の教職員人事につきましては、田原本町の子どもの教育を守るためにも、また充実、発展させるためにも一人でも多くの熱意ある優秀な管理職、あるいは先生方の確保をしていただくことを熱望して、人事につきましてはご検討をお願いをしたいと思います。
それから放課後子どもプランについて1点要望しておきたいと思います。
今後、具体的に田原本町では教育委員会が担当していただくことになるわけですけれども、その際に、子どもの安全、安心な居場所づくりを目指した放課後子どもプランは、ご存じのように放課後健全育成事業、とりわけ学童保育と一体的、あるいは連携して実施するというふうになっております。しかし、2月10日に川西町で開催されました奈良県学童保育研究集会で、全国学童保育連絡協議会の坂口副会長が次のように述べております。すべての児童を対象とした放課後子どもプランと学童保育は性格の異なる事業である。一体化が強まれば福祉としての機能が失われ、また指導員の専門性の低下にもつながる、と指摘しております。この指摘も、今後の事業の推進上、重要な検討課題であると考えられます。田原本町でも教育委員会と住民福祉部がより密接な連携を保っていただいて、放課後子ども教室推進事業と放課後健全育成事業のこれまでの事業の趣旨と独自性を尊重しながら、地域や保護者の願いに応える2つの事業を一体、あるいは連携した放課後子どもプランを策定していただきたいと思います。要望して私の意見を終わりたいと思います。
議長(松本宗弘君)
以上をもちまして2番、西川議員の質問を打ち切ります。
続きまして1番、古立議員。
(1番 古立憲昭君 登壇)
1番(古立憲昭君)
議長のお許しをいただきまして、通告どおり一般質問をさせていただきます。
まず最初に、地方分権についてお伺いいたします。
現在、地方自治体の財政は悪化の一途をたどっております。自治体の借金は年々ふくれ上がり、2007年度の地方長期債務残高は約200兆円、ちなみに国の債務残高は約600兆円であります。借金がふえ続けることはそれだけで財政が逼迫しているということでもあります。あるアンケートによりますと、全国の地方自治体の財政状況は、「極めて厳しい」と答えたのが43%、「厳しい」と答えたのが51%で、実に94%の地方自治体が苦境に追い込まれております。
その理由で最も多いのが「地方交付税の削減」で88%を占めております。次いで「高齢化に伴う関係費の増加」、また借金の返済費用である「公債費負担の増加」という結果でございます。本町の平成19年度予算も、民生費と公債費を合わせると39.5%と大きなウエートを占めております。さらに、各地方では、高齢化による福祉予算など、財政需要が高まる反面、税収は定率減税廃止により少し伸びましたが、恒常的に減少傾向ではないでしょうか。そして、地方交付税が削減され、仕方なく公債発行による借金を重ね、借金返済分が財政を身動きのとれない状況に追い込むという悪循環に各地が陥っております。つきり、サラ金地獄と同じ構図に地方自治体は近づきつつあります。
本町も、公債費は平成18年度決算と平成19年度の予算から見ると、悪化はしておりませんが横ばい状態、そして平成18年度決算から幸いにも財政の健全化は維持されておりますが、その数字は少しずつ悪化をしており、決して油断できる状況ではありません。また、自治体間の財政格差が広がっており、多くの自治体で、自治体間の財政格差を感じておられます。国の財政難のしわ寄せが、地方に配分される地方交付税の削減となり、その結果、ここにきて従来の放漫経営のツケが一挙に自治体の財政運営を苦境に陥れたのであります。
そしてバブル崩壊を機に、日本の中央集権システムを見直す動きが起こり、地方分権の推進が叫ばれはじめました。平成5年に衆参両院で「地方分権」が決議され、平成7年に5年間の時限立法として「地方分権推進法」が成立いたしました。そして平成11年に「地方分権一括法」が成立し、2000年より施行されております。
これら一連の流れは、中央にどっぷりと依存していた自治体の運営を、自立的な方向に促すものでありました。そして小泉政権における「骨太の方針」で三位一体の改革、また補助金の廃止、その後3兆円の税源移譲となり、平成18年の「地方分権改革推進法」の成立を期してその方向性が示されたのでございます。
それは分権型社会への転換、つまり21世紀の人口減少社会において加速する少子高齢化、アジアの競争激化、また環境や経済の変化などに対応していくためには、地方の多様な価値観や地域の個性に根差した住民本位の分権社会への転換、また、地方の活力を高め、強い地方をつくり出し、地域再生のため自分たちの企画力で地域経済の基盤の強化を図る必要がございます。そして、地方の税財政の基盤を確立し、簡素で効率的な筋肉質の行財政システムを構築し、財政健全化を図るべきであります。
さらに、特徴すべきことは、自己決定、自己責任、受益の負担の明確化により「地方を主役」を目指し、国から独立して、自立していく姿を描いたのが地方分権であります。国と地方の真の対等関係を構築し、地方行政の名にふさわしい住民本位の豊かな行政を実現していくことであります。この分権社会に乗り遅れたり、また実現できなければ田原本町の未来はないと言っても言い過ぎではないと思います。そのためにも、町長、職員、議員も意識をしっかり変えて、この地方分権に対応していかなくてはならないと強く訴えるものであります。そこで、この地方分権をどのように考えておられるのか、町長の所見をお聞かせください。
続きまして、この地方分権において非常に大切な運営、つまり行政の経営という点についてお伺いいたします。
地方分権時代を迎えて、改めて今行政の責任と役割が問われております。先ほど分権で述べましたごとく、国の財源不足は地方交付税の削減という形で現実のものとなり、行政サービスの財源不足をもたらしました。さらに、国の行政スリム化は、国に依存していた多くのことが地方への権限委譲という形をまさに推進していこうとするものでありました。地方分権と言えば聞こえはいいですが、自治体にとっては中央に対する甘えや依存が許されなくなり、少ない財源を駆使して独自の運営をしていかなければならない厳しい試練が待ち受けていることを意味しております。
中央とのパイプを断ち切られた自治体に求められているのは、従来の行政運営という言葉から、行政の経営という言葉であらわされる「経営」という考え方であります。そこで経営とは、限られた経営資源、つまり人、物、金、情報を最大限に活用し、住民サービスの効率的、効果的な提供をしていくことであります。その仕組みを常に追及していかなければならない。そして、ないものねだりではなく、あるものねだりへと視点を変えていかなければなりません。また、最近、自治体経営の考え方である「ニューパブリックマネージメント」という言葉がよく使われております。これは公共、行政という管理志向の組織に民間企業が行っている経営の考え方を導入し、多様化するニーズに対し、少ない財源を効果的に活用しながら、顧客である住民の満足度を高め、住みよい地域づくりを目指すものであります。
本町においても、総合計画達成のための一つとして行政改革を推し進められておられます。そこで、この行政改革を考えていただきたいのは、従来型の改革になっていないかという点であります。この従来型の行政改革と言いますのは、投入資源に力点を置き、対処療法的な改善、また改善が短期断片的であると言います。これに対して行政経営という発想は、その基本は行政の生産性の向上であります。それは一つには目的や成果を明確化していく、2つ目は計画、実施、評価、改善、いわゆるPDCAと呼ばれておりますマネージメントサイクルの実施、3つ目はこれらを着実に繰り返していくことであります。これらの考え方を導入することにより、行政を運営から経営という視点に変えなければ、行政改革は従来型に終わってしまいます。
先ほど述べましたように、本町の財政の健全化は維持されておりますが、今こそ将来、田原本町三万三千有余の方々の10年、20年先を考えて、この行政経営という考え方で行政改革が必要と思いますが、町長のご意見をお聞かせください。
さらに、この行政経営の大事なのは、一つ一つの事業に対してきちっと評価していくことであります。国において行政機関が行う政策の評価に関する法律、いわゆる「政策評価法」が制定されております。これは国のみで、地方自治体にはまだ課せられておりませんが、予算や事業の見直しを行っていくとき、必ず必要となってくるのが行政評価で、そのシステムを確立することであります。この「行政評価制度」の導入の背景といたしましては、バブル経済の崩壊、そして右肩上がりの経済成長の終えん、財政の赤字の拡大、社会の成熟化と国民の価値観の多様化、戦後型行政システムの制度疲労などが挙げられております。
これらの問題を解決するために行政評価を導入しているのであります。そして、その主な目的としては、住民に対する行政の説明責任を徹底し、住民本位の効率的で質の高い行政を実現することによって、住民の視点に立った成果志向型への行政への転換、そして職員の意識改革であります。本町の取り組みといたしましては、「第3次総合計画」の中で述べられております行政コストと成果を重視した行財政運営を行うため、行政評価システムを導入し、事務事業の再編成や見直しを行います。また、第4次田原本町行政改革大綱の中で、事務事業の見直しの中で「行政評価システム」の導入などにより見直しを図る、また、住民に対する行政の説明責任を果たすため、住民に公表できるシステムの構築を図ると述べられております。
そこでお伺いいたします。本町において大変重要になってくるこの行政評価システムをどのように構築され、どのように活用されるのか、お答え、よろしくお願いいたします。
次に、教育委員会にお伺いいたします。
文部科学省は、このほど小・中学校で教える標準的内容を定めた学習指導要領の改訂を発表いたしました。現行から引き続き「生きる力の育成」を掲げ、知識の習得、活用する力、学習意欲を身につけさせるために40年ぶりに総授業時間と学習内容をふやしました。教育基本法の改正を受け、公共の精神の育成や伝統、文化の尊重を盛り込んだのでありますが、道徳の教育は見送っております。
戦後から少しこの改訂をひもといてみますと、今回の指導要領は第8次となります。昭和22年、第1次から始まり第2次の昭和26年はアメリカの影響力が強く、学力の低下が問題になりました。昭和33年、第3次より教育の再建が始まり、基礎学力の充実、道徳の時間が新設されました。昭和43年、第4次は、時代の進展に対応した教育内容となりました。そして昭和52年、第5次は高校進学が急上昇したことを踏まえ、小中高12年間の教育内容の一貫性に配慮された。平成元年第6次は、社会の変化に自ら対応できる心豊かな人間の育成を目指す、そして「個性重視」と「新しい学力観」の提唱でありました。平成7年、第7次は、「ゆとり」を強調し、週5日制を導入し、授業内容も授業時間数も大幅に削減、そして本年第8次、本当に力がつくよう「確かな学力」を基盤とした「生きる力」の育成を強調、そして「習得」「活用」「探求」の3者をともに重視した授業時間数、教育内容の回復をうたっているのであります。
今回の改訂は、ゆとり教育が批判を浴び、国際的な学力調査でも、日本の成績低下が問題となり、その中で、学力向上の姿勢を明確に打ち出しております。そして、あらゆる学習の基盤となる「言語力」の育成に注目し、各教科で論述を強化しております。こうした時間確保のため、国語、算数、数学、社会、理科、外国語の授業をふやし、体力低下を防ぐため保健体育もふやす。そのかわり、前回の改訂で設けられました総合的な学習は減らし、中学校の選択教科も原則はなくすということでございます。そして、今回の指導要領の全面実施は、小学校が2011年春、中学校が2012年春の予定でございます。文部科学省はそれについて、理数を中心に前倒ししないと大きな混乱が起こると見て、2009年の春から段階的に移行の計画を立てております。そして、いきなり全面実施すると、年齢によっては学ばない内容が生じたり、学年が進んでから突然発展的な内容が出てきたりする、このため、内容が特にふえる算数、数学、理科は2009年の春から授業時間をふやし、その教材も文部科学省が配布予定となっております。
そこで、今回の改訂の特徴は、40年ぶりに授業時間数と教える内容をふやしたこと。また、小学校の高学年で英語を取り入れたことでございます。そして、これらは児童、生徒に混乱を起こさせないために、全面実施までの期間、つまり移行時が大変重要であります。そして、先生方も大変この対応には苦労されるのではないかと思います。そこでお聞きしたいのは、ここで全面移行時までの期間、どのように対応されるのか。また、先生の増員はどの程度考えておられるのか、ご答弁、よろしくお願いいたします。
以上で私の質問を終わらせていただきます。
議長(松本宗弘君)
町長。
(町長 寺田典弘君 登壇)
町長(寺田典弘君)
1番、古立議員のご質問にお答えをさせていただきます。
まず1番目の、住民本位の豊かな行政を実現するため、地方分権についていかに考えるのかというお尋ねでございます。地方分権の推進については、議員お述べのように、中曽根内閣における「臨時行政改革推進審議会」の議論や、地方制度調査会の答申を受け、平成7年5月の「地方分権推進法」でその基本理念が示され、また、国、地方の役割分担の明確化や権限移譲などについての「地方分権一括法」が平成12年4月から施行され、昨年4月からは地方分権改革の推進に関する基本方針を定めた「地方分権改革推進法」によりその取り組みが進められておるところでございます。
地方分権は、これまで国が持っていた権限及び財源を県や市町村に移して、地域の実情を把握している地方公共団体がその地域に合った特色ある効率的な政策を決定し、より実態に合った行政を実現することであります。地方分権の推進は、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を図ることを基本に、国及び地方公共団体が分担すべき役割を明確にし、地方公共団体の自主性及び自立性を高めることによって、地域の行政は地方公共団体が自らの判断と責任において行う行政システムを構築するものと、基本的に認識をしております。
これまで国と地方の事務見直し、地域の特性、ニーズに応じた規制緩和、地域の自主性、自立性な取り組みに対する国の横断的な財政支援措置、国の関与の見直し、税財源の見直しなどが行われ、また一定の行政規模を確保するため、平成の市町村大合併が進められたところであります。
小泉内閣の折、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006」いわゆる「骨太の方針」が示され、国庫補助金、負担金の見直し、地方交付税の改革、国から地方への税源移譲を一体的に行う三位一体改革は、地方の財源を細やかな制約のある国の補助金から交付金や地方税、地方交付税に切り替え、地方の実情に応じた行政サービスを可能にし、国、地方を通じた行財政の効率化につなげていくという趣旨と理解をしており、制約を受けない自由な財源の増加により、より満足度の高い行政サービスの提供や、地域の実情に応じた基準により事業コストの削減が可能となり、また国、県、市町村の三重行政が解消され、責任の明確化とともに歳出の効率化と財政の健全化につながるものと期待をしておるところであります。
しかしながら、国の財政悪化のもとで行われた三位一体改革による地方財政計画の圧縮は、結果としては地方交付税が削減され、税源移譲は国庫負担金の縮減を伴い、かつ地域間格差の拡大を招いたものであり、まだ真の地方分権自治には至っていない現状にあると認識をしております。地方分権は、国、地方共通の課題でありますが、本町のように財政規模の小さい自治体には、その財政構造に関する扱いがどのようになるのかが一番の問題であり、今後、地方分権改革推進法で示されました国と地方の役割等のあり方の検討や、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保等のあり方を検討される地方分権改革推進委員会での議論や、国の地方分権改革推進計画作成の動向に注視し、真の地方分権自治の推進に向け検討を重ね、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現に向け取り組んでまいりたいと考えておるところでございます。
続きまして、2番目の行政運営と行政評価についての第1点目、行政経営という考え方での行政改革が必要と思うが、町長の所見は、とのご質問でございます。
本町におきましては、平成13年に行政改革大綱を策定し、行政改革に取り組んでまいりました。しかし、地方の財政状況は、議員お述べのとおり、税収の低迷や三位一体の改革に伴う影響などにより厳しい状況が続くと見込まれております。また、国は平成17年3月に「地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針」を示し、一層の行政改革の推進を求めています。本町もこれを受け、地方分権の推進、少子高齢化の急激な進行など、厳しさの増す町財政に対処するとともに、第3次総合計画の着実な執行を図るため、平成18年2月に「第4次田原本町行政改革大綱」を策定をし、同年3月、大綱に基づき平成17年度から21年度までの5カ年間の具体的な取り組みを、住民にわかりやすく明示した「田原本町集中改革プラン」により、実践的、効率的、効果的な事務事業の執行を基本姿勢として、従来の行財政運営のあり方を抜本的に見直し、持続可能な行財政運営を図るため、一層の行財政改革を進めており、その一環といたしまして、昨年10月に役場組織機構改革を実施したところでございます。また、集中改革プランの進捗状況につきましては、毎年広報「たわらもと」やホームページで公表しているところでございます。
なお、行政経営という考え方の中で、地方分権の時代にふさわしい簡素で効率的な行政システムの確立による自治体経営を目指して、施策や事務事業の目標達成度や、費用対効果を客観的に評価し、継続的な業務改善に取り組むための行政評価システムの構築に取り組んでおるところでございます。
以上でございます。ありがとうございました。
議長(松本宗弘君)
総務部参事。
(総務部参事 石本孝男君 登壇)
総務部参事(石本孝男君)
1番、古立議員の行政経営と行政評価についてのご質問のうち、2点目の行政評価システムをどのように構築し、どのように活用するのか、というお尋ねでございます。
行政評価システムの構築につきましては、平成18年度末より準備作業を進めてまいりました。行政評価システムの導入目的は、町民ニーズの多様化や地方分権の進展の中で、健全な財政の維持と行政サービスの質や町民満足度の向上の両立が求められているところでございます。このため行政活動を客観的に評価し、限られた財源を政策課題に対して優先的に振り向ける必要がございます。このため、事業の実施に当たりましては、継続的な業務改善に取り組むとともに、透明性を確保することが求められているところでございます。
行政評価システムにつきましては、「事務事業評価」と「施策評価」により構成いたしまして、その運用を通じましてPDCAサイクルの定着化を図るとともに、行政サービス水準の向上と効率化、行政コストの削減を進め、質の高い行財政運営を実現すること、また、行政評価の結果を公表し、施策や事務事業の実施内容と目標に対する達成度を明確にするとともに、税金の投入に対しましてどのような成果をもたらしたのかを証明し、透明性の高い行政運営を実現することでございます。このため、行政評価制度導入に向けましては、職員の意識改革、準備作業のための職員研修会を始め、各課別の指導等を経て準備作業を実施してきたところでございます。
これまで、すべての事務事業の洗い出しと単位づくりのための業務棚卸作業、新規事業評価の試行、労働量に関する分析、事務事業ごとの毎月の人件費を確定する等の人工把握作業、事務事業評価の試行、事務事業ごとの予算の対応付け等を実施してきたところでございます。
これによりまして、平成20年度からはすべての事務につきまして「事務事業評価」を行いまして、事業の必要性を検証し、その結果、廃止、休止、改善などの事業の方向付けを行うとともに、継続的な業務改善を行う機能を備えました評価システムを構築するところでございます。また、「施策評価」として、施策目標の達成状況を検証する機能、施策展開の方向付けを行うシステムの構築を目指しております。
活用方法といたしましては、継続的な業務の改善に資する、説明責任の遂行、総合計画の実施計画を連動させ、実施計画査定及び進捗の確認、また各年度の予算査定の精度を高めるための基礎資料に活用することを予定しているところでございます。
以上でございます。
議長(松本宗弘君)
教育長。
(教育長 濱川利郎君 登壇)
教育長(濱川利郎君)
第3番目の学習指導要領の改訂についてのご質問にお答えいたします。
議員のご質問のように、戦後で8度目の改訂になるわけでございますが、その改訂ごとに基本的な考え方を示しています。今回の改訂は、教育基本法及び学校教育法の改正、並びに中央教育審議会の答申に基づいて行われました。文部科学省が示しております小・中学校の学習指導要領の改訂案の基本的な考え方は、1、教育基本法で明確になった教育の理念を踏まえた「生きる力」の育成、2、知識、技能の習得と思考力、判断力、表現力などの育成のバランスの重視、3、授業時間数の増加、4、道徳教育や体育などを充実し、豊かな心や健やかな体の育成の4点でございます。特に、今後変化の激しい時代には、知・徳・体の調和の取れた「生きる力」を身につけた子どもたちを育てていくことが求められております。
本町では、「未来に向かって自立的に生きる子ども」の育成を目指し、確かな学力の育成、豊かな人間性の育成、健康でたくましい心身の育成、魅力と活力ある園、学校づくりを重点課題とし、計画的な取り組みを進めてまいりたいと考えております。
小・中学校学習指導要領改訂案は、3月16日までパブリックコメントを行い、寄せられた意見を取りまとめられたあと、3月下旬に官報告示が行われる予定でございます。平成21年4月より移行措置が開始され、一部先行される予定でございます。平成23年4月より小学校、平成24年4月より中学校が新しい学習指導要領に基づいて完全実施されることになっております。
今後、文部科学省が改訂いたしました学習指導要領を精査し、検討事項等について県と十分協議してまいりたいと考えております。
以上でございます。ありがとうございました。
議長(松本宗弘君)
1番、古立議員。
1番(古立憲昭君)
ご答弁ありがとうございます。
町長のほうの地方分権について、また行政経営ということに関しての考え方をお伺いいたしました。1点お聞きしたいのが、町長ではなくて、行政評価についてなんですけれども、この中で、職員の研修会を何回か実施されておられます。これを聞くところによりますと、経営コンサルタントを中心にしてやられているということなんですけれども、これは今後どれぐらいやられるのか、そのへんをちょっとお伺いしたいということでございます。
それと、学習指導要領に関しては、今日の朝日新聞に載っておったんですけれども、小・中の授業時間数増加に対しては賛成が82%ということで、しかし総合学習が減るということに対しては反対が49%と。賛成よりも反対が多いということでございますので、このへんを踏まえて、今後学習指導要領に関しては、やはりこのへんの住民さんの考え方をよく考えられてやっていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。
以上です。
議長(松本宗弘君)
総務部参事。
総務部参事(石本孝男君)
職員研修の今後の対応でございますけれども、平成20年度におきましては、施策評価システムを構築したがために事務事業評価の全面評価を実施するためにいかにするかというアドバイス、それから評価シートの記入につきまして、具体的にやっていくための研修、それから事務事業を評価する立場にある者の評価者に対する評価の視点の研修等を平成20年度に予定しております。また、平成21年度から本格実施後におきましても、それを定着させるためのフォローアップを研修なりという形で考えていきたいと思っております。
以上でございます。
議長(松本宗弘君)
1番、古立議員。
1番(古立憲昭君)
ありがとうございます。これ、ずっとおそらく経営コンサルタントを通じてやっていかれると思うんですけれども、無料ではやってくれませんので。その点ひとつ提案なんですけれども、この講習を受けた方が講師となってそういったのを進めていただくと、別に経営コンサルタントの必要性がなくなってくるんじゃないかという考え方をしておりますので、ぜひともそのへんをまた考えていただきたいなと思います。
以上でございます。
議長(松本宗弘君)
以上をもちまして1番、古立議員の質問を打ち切ります。
続きまして7番、松本美也子議員。
(7番 松本美也子君 登壇)
7番(松本美也子君)
議長のお許しをいただきまして通告書どおり一般質問をさせていただきます。
1項目め、高齢者対策といたしまして、(1)「介護保険の住宅改修費の受領委任払い制度の創設について」お尋ねをいたします。生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して、要介護等認定者について要介護区分に関係なく、上限20万円まで住宅改修費が支給されます。自己負担は1割負担ですが、償還払いの取り扱いのため、利用者は一時的にまとまった金額を工面しなければなりません。そのために住宅改修を断念せざるを得ない場合も想定されます。県内の市町村におきましても、受領委任払い制度の創設をされているところも見受けられます。本町におきましても、利用者の負担を少しでも軽減していただき、より利用しやすくするために、ぜひとも介護保険の住宅改修費の受領委任払い制度の創設をお願いしたく存じます。本町のお考えをお聞かせください。
平成20年4月から後期高齢者医療制度がスタートいたします。広報に掲載していただき、制度等については詳細にご説明をいただいておりますが、75歳以上という年齢から見まして、十分にご理解をいただくにはさまざまなご事情のある年齢ではないかと危惧いたしております。3月末に届きます保険証を始めとして保険料の改定等々について、十分にご理解いただくための取り組みをする必要があるかと存じますが、どのようにご努力いただけるのでしょうか、お尋ねをいたします。
戦前戦後を通して厳しい環境の中で我が身を省みず、ただひたすら働いて優秀な人材を世に送り出して、日本の発展のためにご尽力いただいた一番の日本の功労者の方々です。ていねいにわかりやすくご説明いただけるよう、後期高齢者医療制度の円滑化のための取り組みをお願いいたします。
次に2項目めといたしまして、災害に強いまちづくりとして、学校施設及び公共施設における防災機能の充実についてお尋ねをいたします。本題に入るに当たり、皆様もご存じのとおり常任委員会に関連する質問におきましては、委員会で質問すべきであることは重々承知しておりますが、所管がそうであっても、防災に関しましては、町長を中心に行政関係者が連携をし、専門家、教職員はもちろんのこと、地域の多くの人々に共通認識、共通理解を持っていただくためにとの私の身勝手な思いから、本会議で一般質問させていただくことをご理解、ご承認いただきますようお願いを申し上げまして、本題に入らせていただきます。
平成7年1月17日未明に発生した兵庫県南部地震は多大な被害を及ぼすとともに、地震は全国的にいつどこで発生するかわからないことも改めて認識されることとなり、とりわけ防災拠点としての学校の役割を大きくクローズアップすることとなりました。これを契機に、平成7年6月に制定された地震防災対策特別措置法等のもとで、各地方公共団体等において学校施設の耐震化の努力が続けられてきました。しかしながら平成16年10月23日に発生した新潟県中越地震によって、学校施設は再び大きな被害を受けるとともに、避難場所として被災者を受け入れるのみならず、地域住民に必要な情報を収集、発信するとともに、食糧、生活用品等の必要物資を供給するなど、さまざまな役割を果たすことになるという、地域住民の重要な防災拠点としての役割が改めて求められました。
しかし、地域防災計画に避難所として位置づけられた建築物、その大半が学校施設でありますが、実際に防災機能の整備状況を見ますと、防災倉庫が設置されているのは約27%、自家発電設備の準備は約14%、水を確保するための設備(プールの浄水装置、貯水槽、井戸等)は27%という状況であり、また最も必要不可欠な障がいの有無にかかわらず利用可能な多目的トイレの設置等も含めて、避難場所の指定と防災機能の実態が必ずしも整合されていないのが現状ではないかと思います。
そこでお尋ねをいたします。本町においての学校施設及び公共施設の防災機能の充実についての現状と今後の取り組みについてお尋ねをいたします。
3項目めといたしまして「マタニティマークの活用、推進」についてお尋ねをいたします。21世紀の母子保健分野の国民運動計画である「健やか親子21」では、その課題の一つに「妊娠・出産に関する安全性と快適さの確保」を挙げています。この課題の達成のために、厚生労働省は平成18年3月10日、マタニティマークのデザインを決めました。デザイン決定に当たっては厚生労働省が公募し、1,600を超える応募作品の中から、恩賜財団母子愛育会埼玉県支部のデザインを最優秀作品として選定し、全国マークに決定いたしました。このマークでございます。
(マタニティマークを壇上で掲げる)
公明党は平成17年3月に発表した緊急提言「チャイルドファースト社会をめざして」の中で、妊婦バッジの普及を提言、また、松あきら参議院議員が国会質問で、だれが見てもわかるよう全国統一の規格をつくって普及を進めるよう訴えて実現をいたしました。マタニティマークは、妊産婦が身につけたりポスターなどで掲示して、妊産婦への配慮を呼びかけるものです。見た目では妊婦だとわかりにくい妊娠初期などに満員電車で押される、近くでたばこを吸われるなど、苦痛を訴える声が多いことから、一目で妊婦だとわかるよう全国共通のマークが決められました。
マークは厚生労働省のホームページからダウンロードし、自由に使用できます。また、マークの趣旨に基づくことを条件に自治体や企業、民間団体などでバッジなどの製品として配布、販売することも可能です。今年の4月1日より奈良交通のバス約600台のすべてにマタニティマークとハートプラスマークが優先座席の中に加えて表示されることになりました。昨年11月、公明党奈良県女性局で奈良交通に要望して実現の運びとなりました。最近では全国的にもかなり啓発が進み、企業や自治体で無料配布されて広く知られるところとなりました。また、県内の市町村におきましても、母子手帳交付の際にキーホルダー等にして無料で配布されているところも見受けられます。本町におきましても、妊産婦にやさしい環境づくりのために実施の方向で考えていただければと存じます。そして広く町民の皆様にこのマタニティマークを知っていただき、妊産婦の方に配慮ができるような取り組みもあわせてお願いいたします。
以上で私の質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。場合によりましては自席から再度質問させていただきますので、よろしくお願いを申し上げます。
議長(松本宗弘君)
総務部長。
(総務部長 福西博一君 登壇)
総務部長(福西博一君)
松本議員の2番目の、災害に強いまちづくりとして、学校施設及び公共施設における防災機能の充実についての現状及び今後の取り組みについて、のご質問にお答えをしてまいります。
とりわけ学校施設の避難施設としての機能整備についてのお尋ねでございますけれども、まず、本町の2次避難所は13施設ございます。その内訳は、学校施設10カ所でございまして、小学校5校、中学校2校、高等学校3校のそれぞれ体育館でございます。また、中央体育館、第2体育館、保健センターでございます。
これらの避難所の耐震性につきましては、1カ所、高等学校でございますけれども、これを除きまして、新基準で建設された施設であること、また耐震補強済みの施設で、耐震性は満たしているものと考えております。なお、この1カ所につきましては、来年度耐震検査を実施されるというふうに伺っております。
次に便所でございますけれども、いずれの避難所にも多目的トイレの設置はございません。しかし、障がい者用のトイレはすべての施設に設置をされております。
次に、避難所には避難時の生活関連物資等の必要物資を保管する防災倉庫の設置はございません。施設の空き教室、また空きスペース、また近隣の公共施設等をお借りをいたしまして保管しているのが現状でございます。また、防災資材につきましては、防災ステーション、資材置き場、水防倉庫等で保管をいたしております。
2次避難所は長期にわたり避難生活の施設として位置づけられております。また、地域住民の重要な防災拠点の役割を求められている中で、現在の避難所は防災施設としての機能、設備等につきまして、決して十分とは言えない状況にあります。そういったことから、学校施設また公共施設の防災拠点としての機能充実を図ってまいらなければならないわけでございますけれども、新年度に地域防災計画の見直しを計画をいたしております。この中で防災機能の充実につきまして、関係機関とも協議をいたしまして、必要可能な整備を検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
以上でございます。
議長(松本宗弘君)
住民福祉部長。
(住民福祉部長 中島昭司君 登壇)
住民福祉部長(中島昭司君)
それでは7番、松本美也子議員の質問の1番目の、高齢者対策1点目の「介護保険の住宅改修費の受領委任払い制度」の創設についてお答えいたします。
介護保険での住宅改修の給付サービスにつきましては、在宅の要介護者、要支援者が手すりの取り付け、段差の解消、引き戸等への扉の取り替え等、自宅での生活に支障のないように住宅改修する場合、事前申請により被保険者の心身の状況や住宅の状況から保険給付として適しているかどうかを審査し、住宅改修完了後、事前申請との確認を行い、必要と認めた場合支給する制度でございます。現在は被保険者が住宅改修費用の全額を施工業者に一時立て替え払いをしていただき、住宅改修費用の20万円を限度とし、そのうちの1割負担をしていただき、残りの9割分が保険給付となり、後日償還払いという形で返還しております。今までの申請件数につきましては、平成17年度125件、平成18年度114件、平成19年度1月末現在89件のご利用状況でございます。
そこで、議員お尋ねの受領委任払い制度への移行については、近隣市町村の取り組み状況等も参考に、利用者の簡便な手続きになるよう今後検討を進めてまいりたいと考えております。
続きまして2点目の、後期高齢者医療制度の円滑化のための取り組みについてのご質問でございますが。後期高齢者医療制度の概要パンフレットにつきましては、老人福祉センター、ふれあいセンター、保健センター、青垣生涯学習センター、図書館、社会福祉協議会窓口に配置するとともに、町の広報紙により平成19年12月号、平成20年1月号並びに3月号、及び町のホームページに掲載し、住民の皆様に周知を図っております。なお、本年4月から実施になります75歳以上の後期高齢者医療制度の該当者皆様に平成20年3月中ごろに後期高齢者医療被保険者証を送付いたします際に、制度説明の小冊子、各種申請書類、お知らせ、手続きや制度に関する相談等の問い合わせ先を明記した書類を添付いたしまして、制度移行の円滑化を図ってまいる考えでございます。
続きまして3番目の、妊産婦にやさしい環境づくりとしてマタニティマークの活用、推進についてお答えいたします。この趣旨につきましては、議員よくご承知のとおり、妊娠初期には外見から妊娠していることがわかりづらいことから、交通機関を利用するときの優先的な座席の確保、あるいは職場や飲食店での受動喫煙の防止等、周囲が妊産婦に対して配慮を示しやすくするために厚生労働省が募集し、マタテニィマークを身に付け、妊産婦にやさしい環境づくりを推進する取り組みであります。
そこで、議員お尋ねの本町のマタニティマークの活用、推進の取り組みでありますが、安心して出産できる環境づくりや母子保護の観点からも有効な手段と思われますので、県内市町村の実情等を踏まえ、今後の検討課題としてまいりたいと考えております。よろしくお願いをいたします。
議長(松本宗弘君)
7番、松本美也子議員。
7番(松本美也子君)
ご答弁ありがとうございました。
総務部長からご答弁いただきました防災計画の、学校施設及び公共施設の防災機能の充実についてのご答弁について、再度お尋ねをさせていただきます。
防災計画に示されています避難場所について再度見直しをお願いしたいと思います。先ほどご答弁いただきました13カ所でございますが、その理由といたしましてですけれども、保健センターのスペースから申しまして、大災害に遭って計画にあるすべての人員収容が可能とは思われません。しかも保健センターは本来の重要拠点としての機能も求められてまいります。それと、避難場所になっていない青垣生涯学習センターは対策本部となる庁舎のサブ拠点として、また避難場所としても防災機能が十分に整備されている施設でございます。災害になると弱い立場の高齢者、幼児、障がいをお持ちの方等々にもトイレ対応を始めとして、あらゆる面においても可能かと思われます。生涯学習センターも避難場所としてお考えをいただきたいということ。そして、避難場所として県立高校を始め県の施設もお借りするわけでございますが、町の施設においても同じことが言えると思うんですけれども、閉館時に大災害が起きた場合、避難可能となる道筋について決まっているのか、お尋ねをさせていただきたいと思います。
そしてトイレなんですけれども、先ほど障がい者トイレはほとんどのところについているというふうにおっしゃっていただきました。災害になりますと障がい者トイレだけでは……、オストメート対応のトイレ、そして幼児、そして赤ちゃんがおむつを替えられる多目的トイレが必要になってまいると思います。ぜひともこの多目的トイレの設置をお願いしたいと思います。本庁におきましても、障がい者トイレは1階にございますが、本庁も災害時には対策本部となります。そして普段にも、皆様たくさんの方にご利用いただくこの町役場でございます。ぜひとも早急にオストメート対応の多目的トイレに改修していただけるようお願いしたいと思います。
学校施設に関しては、子どもたちの教育施設であると同時に、地域住民にとって最も身近で、生涯にわたる学習、文化、スポーツなどの活動の場として利用される地域コミュニティの拠点としても重要な場所でございますので、ぜひとも多目的トイレ、皆様が利用可能な多目的トイレをぜひとも改修の方向でお願いしたいと思います。
それと関連しましてお尋ねをさせていただきたいと思います。この答弁の中にございました施設の空き教室や空きスペースまたは近隣の公共施設を借り上げ保管しているのが現状であります、というふうにご答弁いただいたんですけど、明確に場所をお教えいただけますでしょうか。
それから地域防災計画の見直しをお考えいただいて、今回洪水ハザードマップ、アクションプランについてもまとめて計画書を作成していただけるということで、予算も組んでいただいているようでございますが。10月に機構改革をされて、この防災の担当の職員の方も代わられたと思います。今現状でお尋ねしたいんですけれども、この計画書を作成するに当たり、担当課の職員の方、そしてまた関連する職員の方が災害地の現場に研修にどのぐらい行かれているのか、現状をお尋ねしたいと思いますので、その点ご答弁いただけますでしょうか。
それと、住民福祉部長にご答弁いただいた分なんですけれども、こちらは要望だけさせていただきたいと思います。マタニティマークに関しては、金額も安価ですので、ぜひとも実施への取り組みの方向で検討をしていただきたいと思います。
そして、介護保険の住宅改修費の受領委任払い制度の創設についても、実施に向けての検討ということでお願いしたいと思います。
次に、後期高齢者の円滑化のための取り組みでございますが、皆様もご存じのように、全員ではないですけれども、ほとんどの方が年金からこの保険料が天引きされることになります。年金は2カ月に1回通帳に入るなりになってますので、そこから介護保険2カ月分、そしてこの保険料2カ月分が天引きされることになり、多分、そうなって初めてびっくりされて担当課のほうにお電話があると思うんですけれども。そうしてびっくりしてから、ちょっと怒ったような形でこちらにお電話がある前に、今回お願いしました円滑化になりますように、どうか親切な対応をもう一度考えていただいてお願いしたいと思います。住民福祉部長に関しては要望で終わらせていただきますので、総務部長からお答えをお願いいたします。
議長(松本宗弘君)
総務部長。
総務部長(福西博一君)
順番にお答えいたします。
避難所の見直しについてお尋ねでございました。現在の避難所、先ほど申しましたように13カ所を指定をいたしております。しかし、長年見直しをいたしておりません。そういった関係で、この間人口増の地域もございますし、また設備等につきましての不備な面も多々ございます。そういったことから新年度計画いたしております防災計画の中で見直しを図ってまいりたいというふうに考えております。それと、生涯学習センターと保健センターもしかりでございます。この中で検討していきたいと思っております。
それと、県の施設もお借りしてということのご意見でございましたけれども、可能な限り避難所として指定をしていきたいと考えております。ちなみに、13カ所では、仮に1人約3.3平方メートルが要るとして、3,400人程度の収容しかできないような状況でございます。そういった意味で、広げていく必要があろうかと考えております。それと、避難経路についてでございますけれども、避難経路は別段定めておりません。
それと、4番目の多機能トイレに関しまして、とりわけオストメートの対応についてご質問であったと思っております。現在、田原本町には生涯学習センターに1カ所あるだけでございます。避難所にはさまざまな方が避難されて来られる中で、そういった対応も必要かなというような思いをいたします。ただ、オストメート対応トイレにつきましては、さまざまな機能が求められております。ちなみに申し上げましたら、当然便や尿を流せる大便器の汚物流し、汚れた補装具が洗える温水洗器具、またストーマーや周辺の皮膚を洗浄できる温水シャワー、またそういった装着するときの姿見等々の機能が求められております。そういった意味で、スペース的にかなりの大きな規模になっていくんじゃないかなというような思いもございます。避難所すべてに設置していくということもなかなか困難かと思いますけれども、例えば庁舎なり何なりの、現在1カ所でございますので、数をふやしていくということは重要なことかなというように思っております。
それと、保管をお願いしている場所でございますけれども、もし何でしたら、これあとでお渡ししますけれども、例えば田原本町中学校につきましては、2階の北教室、田原本小学校であれば北側倉庫というふうなそれぞれの保管場所がございます。防災ステーションに備蓄しているものもございますし、環境管理課にお願いをしている分もございます。こういうふうなそれぞれの保管場所でございます。
それと、防災担当職員がそういう災害場所の研修に行ったのかというご質問でございますけれども、そういった研修には参加をいたしておりません。ただ、淡路大震災の際に、当時そういう担当された方の体験談と申しますか、そういうのを職員が研修を受けたという経過がございます。
以上で私の答弁とさせていただきます。
議長(松本宗弘君)
7番、松本美也子議員。
7番(松本美也子君)
オストメートのトイレにおきましては、優先順位をつけてぜひとも改修をしていただきたいと思います。町長、本庁には、もう必ず、これだけの設備が整っているにもかかわらず、今そういう病気をなされている方が数多くなってきている現状におきまして、オストメート対応のトイレがないというのはちょっといかがなものかと思いますので、ぜひとも本庁からまずよろしくお願いしたいと思います。
もう二、三質問をさせていただきます。
避難経路、道筋というのは、私はもう少し違う観点でお尋ねをしたつもりでございました。言葉が明確じゃなかったので申しわけなかったんですけれども。県の施設、また町の施設も避難場所となっている施設ですが、今セコムもお願いしておりますし、この県の施設におきましては、さあ避難しなくてはいけないというときに、じゃ、だれがかぎを持っているのか、どこへ連絡をしたら……、もう県の施設、門から閉まってますね、駐車場から。これ入れるのかというこのへん……、避難場所に指定している限り、そこまで……。それと、その避難場所の中身を知っとかないと、じゃどうして、だれが誘導して、どの部屋に避難するのかと。中に入って、多分こういう大規模災害のときには必ず停電になります。自家発電のあるところもないところもあると思うんですけれども、そういう真っ暗な中で、その人たちを誘導するのに、中の状況をよく周知しておかないと、とても誘導にならないと思います。今後県とそのへんのところをきちっと詰めていただきたいと思うのと、もし今現在でかぎを持っている、どういうふうにしたら開けるようになっているというのであればお聞かせ願いたいと思います。
学校におきましても、今までの災害の状況の反省点として、学校の教職員がかぎを預っていたりという場合がありまして、教職員が着くまでにかなり時間がかかって、避難住民がかけつけて窓ガラスを割って入らなければならないという状況も起きておりますので、その点きっちりと計画の中に入れていただきたいと思います。
それと、施設の空き教室や空きスペース、または今ご説明いただいて、保管しているところをご答弁いただいたんですけれども、この保管場所はここの施設の教職員、学校の先生なり、きちっとこの場所にこの物があるということを把握されているのかどうか、もう1点お尋ねをさせていただきたいと思います。
それと、今ちょっとがっかりしたんですけれども、機構改革もしまして、前回の防災担当の方と代わられたということもありますが、これから防災計画をつくろうというときに、関係する職員の方が一度も現場を見ていない、そういうことを経験されてない状況で、本当にいろんなことを想定して、そういうマニュアル、計画書がつくれるのかどうか厳しいと思います。やっぱり現場に知恵あり、調査なくして発言なしという言葉がございますように、今後かなりの予算を組んでいただいてます。立派な計画書ができても、それが本当に使えない計画書であれば、何のための計画書かということにもなってまいりますので、ぜひともこれは町長にもお願いしたいと思うんですけれども、職員の方を現場、新潟なり、幾つか被害を受けられた場所があります。そこは神戸もそうですけれども、一番大変な思いをしたところが最先端な取り組みをされているのが事実でございますので、ぜひとも現場を見て、現場の話を聞いていただいて防災の計画をしていただきたいと思いますので、そのへんもお願いしたいと思います。
それともう1点、いろいろこれから充実していくためには、避難所の運営のマニュアルの作成が絶対的に必要かと思います。そのマニュアルに沿って訓練もしていかないと、いざというときに間に合わないことになるかと思いますので、その点もお願いします。
いろいろ多岐にわたってお尋ねいたしましたが、総務部長、そして町長、ご答弁よろしくお願いいたします。
議長(松本宗弘君)
町長。
町長(寺田典弘君)
貴重なご意見ありがとうございました。オストメートにつきましては、優先順位をつけた中でやっていきたいというふうに考えております。先ほど総務部長からも答弁ありましたように、本町におきましては青垣生涯学習センターのみということになっておりまして、町内の町民の皆さんを見ておりますと、八十数名の方がそういうご病気というか、なられてオストメートが必要とされておるようでございます。それにつきましては優先順位をつけた中で整備をしていきたいというふうに考えておるところでございます。
また、職員の研修等でございますが、なかなか実際に災害が起こったところに行くというそのタイミングの問題もございます。ただ、昨年の機構改革で残念ながら担当が代わってはしまいましたけれども、担当の代わる以前の担当者と私とで福井の防災センターと、そういったところへの研修には行かせていただいたところでございます。今後また機会を見て現担当者のほうにも研修の機会をつくっていきたいというふうに考えております。
ありがとうございました。
議長(松本宗弘君)
総務部長。
総務部長(福西博一君)
まず避難所の開所と申しますか、かぎの問題でございますけれども、現在、先ほど来申しておりますように13カ所ございます。そのうち10カ所の学校施設につきましては、一応校長先生、教頭先生、その次に校長先生の指定する者の順番にそういう連絡体制をとっていただいております。それと、あとの町の公共施設につきましては、動員がかかりましたら職員が出動いたします。その職員によりまして、また施設を管理している職員によりまして対応をしてまいりたいと考えております。
それと、物品の保管場所でございますけれども、当然学校施設等につきましては、校長先生並びにそういう学校関係者の方のご了解を得て置かせていただいているものでございますので、先生方にはご理解をいただいていると思っております。
あと、県の施設の誘導につきましては、それも含めまして、いろいろご提案なりご意見いただきました。そういったものを十分に今後の見直しに参考にさせていただきたいと。今おっしゃっている学校施設の誘導につきましては、できてない、対応できないというのが現状だと思います。そういった意味で、まず現状を見直しながら、それにどういうふうに対応していくかということも重要かと思っておりますので、ご理解をいただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。
議長(松本宗弘君)
以上をもちまして7番、松本美也子議員の質問を打ち切ります。
続きまして11番、上田幸弘議員。
(11番 上田幸弘君 登壇)
11番(上田幸弘君)
それでは議長のお許しをいただきましたので、町の環境政策について何点か一般質問をさせていただきます。
23年前の1985年に私の住む西竹田に現在操業しています田原本町清掃工場ができました。しかし、実際に清掃工場ができますと、他人事ではなくなり、365日清掃工場を見ない日はありません。煙突から出る煙を毎日見ていて、地元住民の1人として感じたことを、新清掃工場建設にもぜひとも反映させていただきたいと思い、幾つか質問させていただきます。
ご承知のように21世紀は環境の世紀とも言われ、人口の急増や食糧危機、資源の枯渇化など、環境問題は地域の問題でもありますが、地球規模の問題でもあるのは今さら言うまでもありませんし、これまで以上に深刻な世界共通の重大なテーマであります。日本の環境技術は世界のトップランナーでありながら、環境行政はトップランナーではないように思います。最近報じられている耐火偽装や古紙配合率の偽装、このような偽装が行政側で何も気付かれずに行われていたとはとても思えません。ある程度法的規制を強くしていかなくては環境は守られないと思います。
そこでまず第1番目として、平野地区6カ大字と町の間で交わされました清掃工場操業に関する協定書についてお尋ねをいたします。田原本町の新清掃工場建設は、皆さんご承知のとおり、6カ大字の協定書により操業期間を平成27年9月30日までとする。またいかなる理由が生じようとも以降の操業は行わないものとして、6カ大字は期限後の操業は一切認めないとなっておりますが、この協定書締結に至るまでには、6カ大字の役員の方々による清掃工場対策委員会が設置され、この中で議論され、また研修等も行われた結果として町との協定が交わされたわけであります。この協定書を行政としてどのように考えておられるのか、お聞かせください。
次に2番目として、清掃工場の基本的な計画をお尋ねいたします。町長は、平成18年第4回定例会の答弁の中で、「基本的には私は建設する計画を進めてまいりたいと、もちろんその方向で考えております。ただ、これにつきましては、建設に一番時間がかかりますので、それを中心の柱として、外部委託も検討させていただきたい」という答弁でありました。また「平成19年度から用地の選定や、ごみ処理基本計画等の策定に取り組み、平成20年度以降は進捗状況により環境調査や住民説明会、用地買収等に取り組んでまいりたい」とも答弁されております。
そこでお尋ねいたします。新清掃工場操業まであと7年半と迫っており、実際には建設の申請期間や用地買収などを考えると、あと数年と、時間的余裕が少ないと思います。町として建設するのか、外部委託するのか検討中ということでしたが、現在までどういう検討をされてきたのか、まずこの点について町長のお考えをお示しください。
さらに町長は、田原本町の清掃工場操業に関して、平成20年1月の広報の中で、『本年は町の将来像を「自然と歴史・文化が育む新しい生活拠点たわらもと」とした「第3次田原本町総合計画」の実現に向けた取り組みの2年目となります』行政課題の一番重要と言ってもよい清掃工場の整備については、「現在策定中でありますごみ処理基本計画のもと、その手法についてすべての選択肢を視野に最良の方法を模索検討し、周辺自治会と協定期限までに整備すべく鋭意努力してまいります」と述べられていますが、平成20年1月時点で、すべての選択肢とか、協定期限まででは、これもさらに時期が遅いのではないかと思いますが、いかがでしょうか。平成20年1月の広報の「すべての選択肢」について、現在どのような方針であるか、また策定された基本計画、これについてもお示しください。
次に、第3番目として、施設整備基本計画策定プロセスにおける住民参加についてお尋ねいたします。一般廃棄物処理事業は、町民固有の事業の一つとされ、地方行政の中でも特に町民生活と密着した対応が必要とされます。また、廃棄物は住民自身が主要な発生者であり、処理費用の負担者であることから、その計画を考える際には住民の理解と協力が不可欠なこととなっています。そのため計画策定においては、発生源における減量化、資源化のほか、収集、運搬、処理、処分の各計画要素ごとに住民との合意形成を図りながら進めていくことが必要であると思います。町は計画段階から各校区総代や学識経験者等の方々の意見も聞きながら、その地域の特性に応じた概念設計を行い、概念設計はとかく夢を描いたイメージプランとなりがちなので、幾つかの実行可能なシナリオを検討し、住民の納得いく構想、計画を策定することが重要であると思います。このことが次のステップでの具体的な処理方式、用地選定などの住民合意を容易にしていくことになると考えます。
そこでお尋ねいたします。町は平成20年度予定の施設整備基本計画で環境調査や計画策定に住民の知恵と力をお借りして、反映していかれる考えであるのかお示しください。
次に、第4番目として、排ガス規制についてお尋ねいたします。現在の清掃工場はセメント処理に固形化を行う施設整備事業と、排ガスを平成14年11月30日までと定める法律に適用するために改修工事が行われましたが、その後町の排ガスは大気汚染防止法の基準値内であるようですが、本町ではさらに町独自の自主規制を設置する予定はありますか。また、田原本町では平成12年5月に公布された「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律(グリーン購入法)」で、この規定に基づいてグリーン購入推進に関し地方公共団体の努力義務が規定されており、この規定に基づいて田原本町地球温暖化対策実行計画を作成されて、いろいろ努力されているようです。この地球温暖化対策は、職員が取り組んでいる対策であって町民に対してではないように思います。
そこで、今後町として独自の環境条例(仮称)を制定されて、新工場建設に際しさらに進んだ燃焼排ガス及びごみの減量を目的とする上乗せ基準を設けていく計画はありますか。清掃工場関係だけでなく、ごみ、騒音等を含めた条例が必要と思いますが、町の基本的な考えをお聞かせください。
最後に5番目として、ごみ減量化を目的としたフリーマーケットの開催についてお尋ねいたします。環境保全、資源の活用等への住民への啓発活動の場としてフリーマーケットやバザー、交換会などを開催することで、家庭内での不用となった生活用品の再利用の機会を広め、粗大ごみ等の減量化を促進することにつながります。また、住民がごみのリサイクルをどう考えていくか、行政が町民に対してごみの現状を知っていただく場として、さらに多くの人が集まることにより町民のコミュニティの場としても、多くの町民の方の手助けも必要でありますが、行政としてどのように考えておられるかお聞かせください。
以上で壇上での質問を終わりますが、場合により自席から質問をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
議長(松本宗弘君)
町長。
(町長 寺田典弘君 登壇)
町長(寺田典弘君)
11番、上田幸弘議員の「町の環境施策について」の1点目「清掃工場操業に関する協定書について」のご質問にお答えをさせていただきます。
清掃工場操業に関する協定書について、行政はどのように考えているのかとの質問でございますが。まず、清掃工場の操業につきましては、周辺6カ自治会のご理解とご協力によりまして再度操業延長にご同意をいただきましたことは、心より感謝を申し上げるところでございます。
さて、協定書につきましては「相互の信頼と理解により協定に合意する」と協定書に明記されていますように、平成27年9月30日までの操業期限はもちろんのこと、協定事項におきましても周辺6カ自治会と協議しながら進めてまいる所存でございます。
次に、2点目の「清掃工場の基本的な計画について」新清掃工場操業まで7年半となったが、町としてどういう検討をされてきたのか。また、すべての選択肢について現在の方針、ごみ処理基本計画についてのご質問でございます。
昨年10月に新設いたしました総合政策課におきまして、ごみ処理方法として直営処理、広域化、委託処理、またリサイクル施設の付設、管理運営方式などあらゆる選択肢を視野に最良の方法を模索、検討をいたしておるところでございます。また、建設費用やランニングコストなどにつきましても、財政状況が厳しい状況下において種々検討を行っているところでございます。なお、国庫補助金の関係につきましては、循環型社会形成推進交付金、3分の1でございますが創設されていますが、交付対象地域として人口5万人以上、また面積400平方キロメートルとの要件があります。現状におきましては本町は該当はいたしません。しかし、近隣の葛城市、広陵町の間で地域循環型社会形成計画が策定をされ、葛城市では清掃工場、リサイクル施設等、広陵町では旧清掃工場跡地にリサイクル施設、ストックヤードなどの建設が認可され、交付金の対象になった例もございます。本町も近隣ないし県内市町村との間で地域循環型社会形成計画の策定が可能か否か、またその手法などを模索、検討しているところでございます。
いずれにいたしましても、建設をしていくには都市計画決定、環境影響調査といった手続きや、建設用地の選定などに時間を要すると考えられるため、平成20年度中にはその手法及び方法を絞り込み、清掃工場周辺6カ自治会との協定書の操業期限を念頭に取り組んでまいりたいと考えておるところでございます。
なお、ごみ処理基本計画につきましては、廃棄物処理法の規定に基づき、今後10年間の一般廃棄物の発生量及び処理等の見込み、また一般廃棄物の抑制のための方策、一般廃棄物の種別及び分別、処理方法等を内容とした計画でございまして、現在策定中でございます。
次に、3点目、「計画策定プロセスにおける住民参加について」施設整備基本計画で住民参加の考えはあるか、とのご質問でございます。近隣市町村の取り組み等も参考にしながら用地の選定、処理方法、管理運営方法など、一定の方向性が決まれば、住民参加について検討してまいりたいと考えておる次第でございます。
以上でございます。ありがとうございました。
議長(松本宗弘君)
生活環境部長。
(生活環境部長 小西敏夫君 登壇)
生活環境部長(小西敏夫君)
11番、上田議員の第4点目、排ガス規制について、町の排ガスは大気汚染防止法の基準値内であるが、さらに町独自の自主規制値を設定する予定はありますか、とのご質問にお答えさせていただきたいと思います。
本町の焼却施設は環境問題を重点課題として有害物質による環境汚染等の解決に向け、排ガス中に含まれる有害物の排出濃度を低減させるため、平成11、12年度におきまして、排ガス高度処理施設等の基幹改良工事で各設備の改善を行い、ダイオキシン類特別対策措置法の基準値以下を維持できる施設となりました。
大気汚染防止法は平成9年12月1日施行の抑制基準及びダイオキシン類対策特別措置法平成12年1月15日施行の排出基準によれば、平成12年1月14日までの既存施設の排出基準値は、1焼却炉で1時間当たりの焼却能力が基準とされ、本町の焼却能力、1時間あたり1,875キログラムであることから、排出基準の焼却能力別量では1時間あたり50キログラムから1時間あたり2,000キログラム範囲であるため、本町のダイオキシン類の排出基準値は10ナノグラム以下と定められております。測定検査につきましては、ダイオキシン類で年1回、1号炉と2号炉、また排ガス4成分のばいじん濃度、硫黄酸化物、窒素酸化物、塩化水素の4成分以外に焼却灰熱灼減量の項目があり、毎月測定検査を実施しております。
平成19年12月の測定結果は、ばいじん濃度が1ノルマルリューベあたり0.25グラム以下に対し1ノルマルリューベあたり0.009グラム、硫黄酸化物K値17.5以下に対し0.010、窒素酸化物250ppm以下に対して100ppm、塩化水素1ノルマルリューベあたり700ミリグラム以下に対して1ノルマルリューベあたり2.8ミリグラム、焼却灰熱灼減量7%以下に対して1.6%、ダイオキシン類10ナノグラム以下に対し1号炉、0.020ナノグラム、2号炉は0.025ナノグラムとなっております。
なお、ダイオキシン類の排出基準値は10ナノグラム以下と定められておりますが、平成11、12年度の施設の基幹改良工事で各設備の改善に伴い、また地域の環境保全を踏まえた上で町独自で自主的に排出基準値を5ナノグラム以下とさせていただき、毎年開催している田原本町清掃工場公害モニター委員会に排出測定結果等について報告いたしているところでございます。毎年の測定値は抑制基準を大きく下回っているため、さらなる町独自の自主規制値の設定及び独自の排出基準についての上乗せ基準の見直しは、現時点では考えておりません。今後の清掃工場管理運営につきましては、環境保全等に最大の努力を傾注し、地域の方々の快適な生活環境の推進に貢献するよう努めてまいりたいと考えております。
続きまして5点目、ごみ減量を目的としたフリーマーケットの開催についてのお尋ねでございますが、ごみ問題が今や環境と資源にかかわる大きな社会問題となっていることから、町民一人一人が自分のライフスタイルを見直すことが必要となってきております。できる限り無駄な商品は買わない、一つのものを長く使うことによって生産や消費を抑えごみを減らす、不用になったものを必要な人に譲ったり、廃棄処分にする場合は分別をし、再生できるものは資源として再生利用するなど、幅広く町民にごみ減量とリサイクル意識を変えていくことが求められていることから、毎年6月の環境月間に合わせて、山辺広域の市町村の構成による山辺広域環境フエアを天理市役所前広場で開催いたしております。これは廃棄物循環型社会形成の一環としてリサイクル品や不用品の再生利用を図る目的としてフリーマーケット等の開催を行っており、毎年4月の町広報紙には、出店者の参加募集をし、例年約町内から10店舗余りが出店していただいております。
また、田原本町商工会主催で昨年10月に行われた活性化事業として、「たわらもと十六市」でもフリーマーケットの出店等の募集をされていることから、今後においても商工会と連携し、参加を促進してまいりたいと考えております。
以上、答弁とさせていただきます。ありがとうございました。
議長(松本宗弘君)
11番、上田幸弘議員。
11番(上田幸弘君)
ただいまの町長の答弁ですと、新清掃工場を建設するかどうか、まだ検討中であるかのように聞こえるんですけれども、協定書期限内までに新清掃工場ができるのかどうか、それについてお答えください。また、一つ地元の意見としてお話しますと、平成17年9月の6カ大字と結ばれた契約書に、6カ大字は補助金を減らしてでもほかの地域に清掃工場を移転していただきたいという意見もあるということをちょっと考えておいていただきたいと思います。
清掃工場がまた移転するとなれば、解体は早急にしていただかなければなりませんが、跡地利用は基本的にはどのように考えておられるのか。またそのへんを周辺6カ大字とどのようにお話をされていかれるのか、その点についてもご答弁をお願いします。
用地選定、工場建設という当面の課題は、長期的な問題を区別して対策を取り、経済的、効率的から見ても、当面当該施設から周辺住民へ負担、支障のない最小限度のものにならなければならないと思います。そこで、清掃工場建設に当たって、時間を要するんですが、時期などを含めた日程をお伺いしたいと思います。まず1つ目として、候補地選定に当たって、候補地は何箇所あり、何年に決定されますか。2番目としてPFI手法で実施は考えておられますか。3番目として、処理方式の選定をいつごろまでに検討されますか。4番目として、諸手続きはいつごろになりますか。5番目として、環境アセスメントを行われると思いますが、目標クリア型ですか、それともベスト追求型ですか、それについてもご答弁をお願いします。
3番目の住民参加ですが、例えば広陵町では、平成12年度を初年度として平成20年度を最終年度とする広陵町の一般廃棄物ごみ処理基本計画が策定されました。平成12年11月29日の広陵町の一般廃棄物のごみ処理減量等に関する諮問について検討するよう諮問を受けて審議会が設置されました。審議会では、社会状況の変化を積極的に受け止めて、9回の審議会を開催し、ごみ処理アンケート調査の結果を踏まえて議論を行われました。各委員は、生活者の視点、事業者の視点、専門的視点からそれぞれの議論を展開し、すべての項目にわたって十分審議を尽くしましたが、全委員が完全合意に達しなかった部分もあり、それについては少数意見として整理付記されたものであります。答申は、環境負荷軽減に配慮しながら、まずごみの発生量自体を抑制し、排出されるごみについてもできる限り再生利用する、いわゆる循環型社会の方向を示したものであります。後に策定される実施計画においては、本審議会の答申がごみ減量化目標値、資源化目標値並びに達成方策等のもととなっています。
そこでお尋ねいたします。発生者であり処理費用の負担者である町民や事業所に、ごみ減量化への広報もしていますし、職員も減量に努力しています。しかし、清掃工場建設に向けては今のままで別に対策は取りませんということですか。何も広陵町のまねをしろと言っているわけではないんですが、町として先進的な自治体を参考にしながら、町民の意見も聞き、ごみ減量化に向けた積極的な取り組みを進めていただきたいと思います。これについて再度ご見解を伺います。
4番目の条例について再度お尋ねいたします。
各自治体によって分別の種類や品目は多様です。資源化等を考えると分別品目は多いほど資源化がしやすいのですが、その一方で取引先の確保や収集の負担が多くなります。有害ごみについては、現在分別収集しているのは県内で18市町村であり、蛍光灯や乾電池については電気店で回収に応じてくれるところもあり、排出量関係で市町村における回収は数カ月に1回というところもあるようです。またプラスチックについては、奈良市など15の市町村で行われていますが、大部分は燃やすごみとして処分されています。プラスチックは再度プラスチックの原料になったり、コークス炉の燃料に使われたりなど有効に活用できるものもあります。いずれにせよリサイクルの施設やストックヤード、取引業者等の確保が必要となりますが、積極的に取り組んでいただきたいと思います。条例や規制によって、行政、町民、事業者がごみや焼却場等の問題に関心を持っていただくことにより、ごみ減量やリサイクル等が進むと思いますが、そこで、ごみ等の3Rを踏まえた条例を今後検討していかれるか、再度お尋ねいたします。
最後にフリーマーケットですが、ごみの再利用を進めるためにフリーマーケットやガレージセールが必要で、人に譲渡できないか、いろいろ方法を取れないか、特にガレージセールやフリーマーケットはごみの3Rに大変有効であると考えられています。昨年、弥生の里ホールで行われた橿原JC主催のタウンミーティングで、町長の友人であると思いますが、フリーマーケットに大変精通した方がおられると思います。町長のご友人であるならば、ぜひともボランティアとして知恵をお借りできたらなと思いますが、その点、よろしくお願いします。
議長(松本宗弘君)
町長。
町長(寺田典弘君)
ありがとうございます。貴重なご意見を賜りましたこと、心より御礼を申し上げさせていただきます。何点かについてご説明させていただきます。
一番最初の、期限的に可能かどうかとうことでございます。十分可能であるというふうに私どもは認識をいたしておりますし、実際問題、タイムスケジュール等もつくらせていただきまして、建設した場合はどうなるのか、委託の場合はどういうふうになるのか、またそれ以外の方法について、した場合について別にタイムスケジュールをつくらせていただいているところでございますので、十分、平成27年9月30日までは可能であるというふうな認識をさせていただいております。
その中で、跡地はじゃどうするのかというお話でございました。今の清掃工場が必要でなくなった場合には、できるだけ速やかに解体をしていきたいというふうに思っておりますが、今の現段階におきまして、何にするという決定はしておらないところでございます。ただ、幾つかの案としては実際に持っておるところでございます。
それからPFIでございます。PFIは現課のほうに指示をいたしまして鋭意研究をさせておるところでございます。
それから日程的に用地等、いつということでございます。先ほども申しましたように、今年度中にこの方策について決定をしていきたいというふうに思っておりますので、来年度以降になろうかというふうに考えております。
それから処理方法でございます。以前、清掃工場に伴う計画書といたしまして皆様方にお示しをさせていただいておったのは、ストーカー式の60トン炉でご説明をさせていただいておったかというふうに考えております。それ以外の方法、手法につきましては今後の検討課題でございます。実際に工事に着手してから2年近い工期が予定をされておるところでございますので、少なくとも平成25年度中、平成24年度の中ぐらいには発注していけるような形をとっていかねばならないというふうに逆算をしておるところでございます。
私からの答弁は以上でございます。ありがとうございました。
議長(松本宗弘君)
生活環境部長。
生活環境部長(小西敏夫君)
議員さんお述べのように3Rについて、発生抑制、再使用、再生利用、リサイクルですね、これについての条例等の検討をすることはしないのかというご質問にお答えしたいと思います。
ほかの市町村の実情も踏まえまして、今後やっぱり検討課題として考えていきたいなというふうに考えております。
それとフリーマーケットでございます。これは個人が出店される分でございまして、機会あるごとにそういう形で啓蒙していきたいなというふうに考えております。
以上でございます。
議長(松本宗弘君)
11番、上田幸弘議員。
11番(上田幸弘君)
いずれにしましても、私としては、住民の意見を町はいつごろぐらいから聞いていかれるか。設計に入って、実際に進んでいってしまってからでは、今の時代、意見を聞くのはちょっと遅いんではないかと。できるだけ早い時期に住民の方の意見を取り入れてもらって、参考にしていただくほうが、清掃工場建設に当たっては大変やりやすいんではないかと思います。
議長(松本宗弘君)
町長。
町長(寺田典弘君)
ありがとうございます。貴重なご意見を賜りました。できるだけそのような形で、住民の皆様に早い形で参加いただける形態をこしらえていきたいというふうに考えております。ありがとうございました。
議長(松本宗弘君)
以上をもちまして11番、上田幸弘議員の質問を打ち切ります。
暫時休憩いたします。
再開は午後1時といたします。
午後0時14分 休憩
午後0時59分 再開
議長(松本宗弘君)
再開いたします。
休憩前に引き続き一般質問を行います。8番、小走議員。
(8番 小走善秀君 登壇)
8番(小走善秀君)
議長のお許しを得ましたので一般質問をさせていただきます。
町民の安全安心ということについてでございます。まず食の安全安心について質問させていただきます。
日本人は、水と安全はただだと思っている、と指摘したのはベンダサンであります。平和な社会の中でそれは幸せな一つの姿でございました。しかし今はどうでしょう。牛肉の偽装、賞味期限切れ食品、産地の偽装等、数え上げたらきりがないぐらい食の安全が脅かされています。特に、中国冷凍食品や輸入農作物の残留農薬の問題です。また、冷凍ギョウザの農薬混入問題、死者まで出して本当に重大な問題となっております。食の安全は本当にどうなってしまったのでしょう。中国製は怖くて食べられないというのが本当の実感でございます。
そこで危惧されるのが学校給食の問題でございます。食は命にかかわります。給食において過去に中国野菜を使っておられたことはありますか。また、中国製冷凍食品は使っておられませんでしたか。今現在はどうでしょうか。そして食材の調達の経路はどうでしょうか。また仕組み、献立、そして調理場での事故、食中毒の防止の安全マニュアルはあるのでしょうか。どうなっていますか、回答をお願いします。
次に、環境問題についてでございます。野焼き、不法投棄についてでございます。厚生環境常任委員会のメンバーといたしまして、本来委員会で質疑するのが筋なのでございますが、町民の安全安心というテーマですので、ここであわせて質問させていただきます。よく耳にいたしますのが野焼きの苦情、不法投棄の問題でございます。これも住民の健康、安全安心にかかわる大変重要な問題でございます。現状はどうなっているのでしょうか。その取り組み、対応等について教えてください。
以上、質問を終わります。
議長(松本宗弘君)
教育次長。
(教育次長 森本至完君 登壇)
教育次長(森本至完君)
それでは8番、小走議員の、町民の安全安心についての1番目の、食の安全安心のご質問で、学校給食についてのご質問にお答えしてまいります。
現在の学校給食は、学校教育の一環として位置づけられ、児童生徒の心身の健全な発達を図る上で、学校生活に欠かせない重要な教育活動となっております。学校給食の実施に当たりましては、栄養管理されたおいしい食事の提供だけでなく、徹底した衛生管理と物資管理による安全な学校給食の実施に努めておるところでございます。しかし、最近、先ほどお話がありましたように、中国産冷凍ギョウザが原因と疑われる健康被害事例の発生を踏まえ、本町といたしましては中国野菜、中国製冷凍食品の使用について、納入業者に再調査した結果、いずれも使用していないことを確認いたしましたので、2月1日付で、保護者等に食品の安全性についてお知らせをいたしたところでございます。また、国内産加工品等につきましても、原材料の生産地名を記入することを従来から義務付けておりますことから、一部中国産がある場合は、現在のところ使用を中止しておるところでございます。
また、食材の物資調達経路につきましては、町内で購入できる青果物、肉、油揚げ、調味料等は町内業者より納入いたしております。冷凍食品等は県内業者より納入いたしております。いずれも納入業者は学校給食用物資供給業者登録申請書(年1回)により登録された業者であります。
調理場の安全マニュアルにつきましては、文部科学省が示しております学校給食衛生管理の基準により作成いたしました町の学校給食衛生管理マニュアルに基づき、衛生面に努めておるところでございます。今後も学校給食用物資供給における安全性の確保、衛生管理の一層の徹底に努めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。
以上、私からの答弁とさせていただきます。ありがとうございました。
議長(松本宗弘君)
生活環境部長。
(生活環境部長 小西敏夫君 登壇)
生活環境部長(小西敏夫君)
8番、小走議員の質問の2番目、環境の安全安心の野焼き、不法投棄の対応についてのご質問に答弁させていただきます。
野焼きや不法投棄などの拡大防止のためには、早期発見と早期対応が基本であり、行政、警察と地元住民が一体となり、小さなものでも許さないという厳然とした姿勢で臨むことが重要であります。さて、野焼きにつきましては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律において、平成13年4月に野焼きの禁止が施行され、さらに平成16年5月に罰則規定で5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、または併科というように罰則が強化されているにもかかわらず、野焼きなどの行為が後を断たないのが現状でございます。
野焼きの防止対策といたしまして、広報「たわらもと」に、野焼き行為はやめましょう、と掲載を行いつつ、昨年の8月には、産業観光課及び農業委員会より、大字農家代表者を通じまして、農業者の方々に農業焼却は例外的な焼却であっても、その行為が無制限に許容されているわけではないといった野焼き禁止についての回覧を回しておるところでございます。しかしながら、最近特にこのことの通報が多く受けられます。住民からの通報があった場合は、現場に出向き、野焼きをしている者に対し、法律で禁止されていることや、付近の住民が迷惑していることの説明を行い、野焼きをしないように行政指導を行っております。しかし、大規模で悪質な野焼きの場合は、県の産業廃棄物監視センターや警察の協力を求め指導を行っているところでございます。
次に、不法投棄につきましても、先ほど述べました罰則規定がありますが、これも野焼き行為と同様に後を断たないのが現状でございます。不法投棄の防止対策といたしまして、地元自治会の協力のもと、啓発看板などの設置による不法投棄の未然防止を図るとともに、警察の協力を求め、パトロールや住民からの通報により判明した不法投棄現場の調査、回収など、職員により早期処理を行っております。また、悪質な不法投棄であれば投棄物の中身を調査して、証拠物件などから不法投棄者の割り出しに努め、投棄者が判明した場合は警察へ通報し、警察と連携を図り、投棄者への行政指導を行っております。
このような心ない者による不法投棄などがなくならない限り、今後も引き続き公用車に「野焼き、不法投棄を行わない」といった文言のステッカーで住民に啓発を行いつつ、町広報紙により住民の協力を求めるなどの活動、及び巡回監視に力を注いでいきたいと思っております。
以上、答弁とさせていただきます。
議長(松本宗弘君)
8番、小走議員。
8番(小走善秀君)
ありがとうございます。
食の安全のほうも、今後ご回答いただいた中で、このような問題はまず起きないだろうと思います。田原本町は、もともと農業が盛んで、生産者の顔が見え、安心して食べられる地元の野菜、食品を使う地産地消の取り組みをお願いしたいと思います。牛肉は輸入牛肉よりも国産を使っていただく、そして供給問題、産地偽装が憂慮される中で、安心できる地元の商店からの調達、これも現在実施していただいているようでございますので、そのまま続けていただきたいと思います。そして、食が飽食の時代、洋風化した食生活から、現在では先進国の中でも食糧自給率が最低水準に日本はなってしまっております。国策の上からも憂慮すべき事態であり、また、生活習慣病、肥満の増加を招いているのが現状でございます。そこで、健康によいとされる和食化を押し進めていただき、またパン食から米飯食にしていただいたほうがいいのではないかと思います。平成16年の資料では、完全米飯給食を実施しているのが、3万1,000校のうち1,450校、4.5%ということでございます。約7割が週に3回以内が現状であるということでございます。子どもの健全育成、教育的意義からも、これから米飯給食に移行していただけたらなと思います。
また、昭和55年から平成12年の20年間で、食糧消費支出が44兆円から80兆円に倍増しておると、こういうことです。その中で、国内の農産物の消費支出は9兆6,000億円、これは変わってないということです。結局、流通や加工に対しての支払いがふえて、食材の農業がうるおっていないというところですね。農業がうるおい、そしてまた地元の食の安全が確保できる地産地消をぜひともお願いしたいと思います。
このことから、農業、そして商工業の振興と生産者がわかる安心できる地場産品を買えるような即売する場所ですね、今までから出ておりますけれども、道の駅その他で地場産品を即売できる場所、当面できなければそれに代わるべき何らかの検討を加えていただき、いつでも地元の産品が気軽に買えるような、それが食の安全安心につながるのではないかということで、地元農業産業振興の上からもぜひ考えていただきたいと思います。現在の取り組み状況について教えていただけますか。
議長(松本宗弘君)
教育次長。
教育次長(森本至完君)
ご意見ありがとうございます。
給食の食材につきましては、先ほど申し上げましたように、地産地消ということで一部野菜等を取り入れております。今後も地元の農家の皆様のつくられるものを導入してまいりたいと考えております。
もう1点ですけれども、現在、学校給食におきましては、米食とパン食につきましては、米食が3日、パン食が2日でございます。これは現在、学校給食運営協議会がございますので、そちらのほうのご意見を聞きながら、現在その比率で進めておりますので、ご意見はご参考としてお聞きしておきます。
以上でございます。
議長(松本宗弘君)
産業建設部長。
産業建設部長(森島庸光君)
8番、小走議員の再度のご質問の中で、農産物の直売所の件もございました。現在、田原本町で実施しております第4土曜日、月1回の朝市では、今、小走議員のおっしゃる趣旨にはまだ至ってないと思います。ちょっと今耳にしておりますのが、JAが田原本町内で、今開設に向けて研究、検討されるように伺っております。町としても協力できる部分があれば積極的に協力して努力していきたいと思います。
以上でございます。
議長(松本宗弘君)
8番、小走議員。
8番(小走善秀君)
ありがとうございます。
環境のほうも野焼きのほうも積極的にやっていただいているようで、今後ともどうぞよろしくお願いしたいと思います。
以上です。
議長(松本宗弘君)
以上をもちまして8番、小走議員の質問を打ち切ります。
続きまして5番、吉田議員。
(5番 吉田容工君 登壇)
5番(吉田容工君)
それでは議長の許可を得まして一般質問を行います。
まず1番目が、税金の徴収姿勢についてであります。国税庁が公表しています税務運営方針には、「申告納税制度のもとでは納税者自らが積極的に納税義務を遂行することが必要であるが、そのためには税務当局が納税者を援助し指導することが必要であり、我々は常に納税者と一体となって税務を運営していく心がけを持たなければならない。納税者と一体となって税務を運営していくには、納税者に対して親切な態度で接し、不便をかけないように努めるとともに納税者の苦痛、あるいは不満は積極的に解決するように努めなければならない。また、納税者の主張に十分耳を傾け、いやしくも一方的であるという批判を受けることがないよう細心の注意を払わなければならない」と定めています。これは憲法の趣旨、規定を具体化した結果です。明治憲法では、課税権は天皇にあり、日本臣民は納税の義務を負うとされていました。それが現行憲法になって、税務執行における国家権力の乱用から納税者の人権、生活が擁護される、税務行政においても主権者としての基本的人権の擁護が貫かれなければならないとされているからです。憲法第13条「すべて国民は個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする」この生存権規定からは「最低生活費、生存権的財産には課税しない」「滞納者と言えどもその生活を脅かす処分は許されない」という原則が導き出されます。憲法第14条「すべて国民は法のもとに平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により政治的、経済的または社会的関係において差別されない」これを税務行政に当てはめると、能力に応じて平等であるとなります。日本の税制の中心をなす応能負担原則は、1つは直接税を中心とする、2つ目が各種所得を総合して、所得が多くなるに応じて高い税率で課税する。3つ目が生計費は非課税とする。4つ目は勤労所得は軽課税、不労所得は重課税とするとなっています。
例えば西宮市では、国民健康保険税の賦課にあたって、課税所得の20%を上回る保険料は免除するという制度を実施に移しています。どんどん上がる保険料を見かねて、これでは生活できないと判断し、政策化したものです。生活費は非課税とする原則の具体化です。
国民健康保険課長通達「収納対策緊急プランの策定等について」では、資産状況、収入状況を把握することを求めています。そこで質問します。町長の課税、徴税に関する方針、考え方について答弁願います。
地方税法第15条の7に、滞納処分の執行停止規定があります。滞納者の生活を著しく窮迫させる恐れがある場合に、滞納処分の執行停止をすることができる、となっています。法は、本来弱者の利益を守るために存在します。租税と言えども滞納処分の執行によって滞納者の生活を著しく窮迫させてはならない、滞納処分による滞納者の生存権侵害を防ぐために滞納処分の執行停止が規定されています。文言は「できる」となっていますが、法の趣旨にかんがみて地方自治体の長の裁量ではなく義務と言えます。
昨年、住民の方から「銀行へ行ったら残高がゼロだった。聞いてみると町が差し押えをしたそうで、お金がなくなったら正月を迎えられない」という訴えをいただきました。役場で確認しますと、ちゃんと催告書は送ってあるということでしたが、差し押えという最終手段を取る場合、事前に訪問や電話で実情を把握したのかと質問しましたら、滞納者が多くて対応できない、という返事でした。催告書には「親展」または「重要」の表示もなく、全くの普通郵便で出しているということもお伺いしました。そこで「もしそれが年金だったらどうするのか、年金の差し押えは禁じられているはずだが」と尋ねると「通帳に入ったら預金です」という返事です。法を重んじるということは手続きを重んじるということです。本町の徴税手続きでは、本人の収入状況や生活実態を把握せずに進められているように受け止めました。それは地方税法違反です。
そこで質問します。滞納者の収入状況や生活実態をどのようにして捕捉しているのか答弁願います。滞納者の収入状況や生活実態を把握していないことは、生活に必要な預金を差し押えることになるだけでなく、本当は支払い能力がある人からの徴税を見逃している可能性もあります。貧困と格差が大きく広がり、商売も暮らし向きもかつてなく厳しい中、滞納者がふえて大変だとは思いますが、2人1組で訪問活動をし、滞納者の実態を把握される、地方税法に基づいた仕事をされることを求めるものです。
2番目の情報公開について質問いたします。
今年の1月に、高取町長が逮捕されました。高取町土地開発公社のお金を着服したと報じられました。さらに、高取町土地開発公社名義で資金調達をしたのに、土地開発公社の帳簿には記載されていないなど、不明朗なお金の流れも報じられました。しかも土地開発公社に1億3,000万円の欠損金があり、高取町が土地開発公社に融資をしている一時貸付金1億2,000万円を年度内に返済してもらわないと、高取町が1億2,000万円を負担することになる、高取町土地開発公社の保有している土地の簿価は8億5,000万円であるが、時価は半分以下だろうという報道もされました。一方、上牧町では、上牧町土地開発公社が23億円で取得した土地を民間へ売却するために実勢価格で評価をし直したところ5億円の評価しかなく、上牧町が一般会計で欠損金18億円を償還することが報じられています。土地開発公社は情報公開の対象でなく、住民のわからない、知らないところで町の財政を破綻させるほどの損失を計上していることになります。一部の人しか実態を知らない状態が、このような乱脈財政を許すことになったと考えます。本町でも土地開発公社は情報公開の対象外となっています。田原本町土地開発公社に限って間違いはないと信じておりますが、公明正大な事業をされておられるからこそ、情報公開対象になられて、住民に安心していただくことが大切だと、声を大にして主張いたします。情報公開の実施機関になられるかどうか、答弁を願います。
3番目の、農業政策について質問いたします。
今年になって、先ほども小走議員から指摘がありましたように、農薬汚染冷凍食品によりたくさんの方が中毒にかかられていたことが判明しました。中には重態の方もおられて、食の安全について国全体を驚かせました。4月には小麦の卸値が30%も値上げされることが公表されています。これはバイオ燃料へのシフトやオーストラリアの2年連続干ばつが大きく影響していると言われています。さらに、ほんど自給していると思っている鶏卵でも輸入えさを考慮すると90%が輸入となります。政府自民党でさえ、食糧安全保障と言わざるを得ない状況です。なぜこうなったのでしょうか。それは生産者米価を政府が放棄して以来、一貫して米の流通を市場原理に委ねてきたこと、車や電化製品を輸出する代償として農産物の輸入自由化を推し進めてきた結果です。今世界では、穀物在庫が市場最低を記録し、穀物相場の高騰、農産物輸出を禁止する国が相次いでいます。金を出せばいつでも食糧を買いあさることができる時代は終わりつつあります。国内の農地で国民に安全な食糧を生産することが本当に重要になりつつあります。そもそも農業は単なる食糧の生産だけではなく、その農地の保水力は災害防止に役立ちます。各地に残っている祭や行事は農耕に由来します。農業を振興することは文化を守ることになります。町長も農業の重要性については十分にご存じのことと存じ上げます。
そこで質問します。本町の農業政策について、政策を列挙するだけでなく、大きな方向性、課題、目標を示していただきたい。
第3次総合計画には「担い手に対する大規模化への支援」とあります。麦の作付面積が平成12年、1.9ヘクタールから平成16年には40ヘクタールに拡大したと分析されています。しかし現実は、国の麦作経営対策がなくなり、麦の生産者手取り単価は1キロ当たり140円から約40円に暴落しています。農協に依頼する刈り取り、乾燥、調整の経費は、1キロ当たり48円に上がっております。水田農業構造改革交付金を一反当たり5万3,000円もらったとしても、さらに町から1反当たり1万円もらったとしても、一生懸命つくって、できがよければよいほど実入りが少なくなります。町が認定されている担い手の方は篤農家です。一生懸命農業をされておられる方々です。ところが今の町の政策は、できが悪いほど実入りがいいという政策です。こんな政策は篤農家を本当に大切にしている政策でしょうか。大変な疑問です。水田農業構造改革交付金と町協力補助金を出来高に応じて、例えば1キログラム当たり100円で交付する制度にすると、農家の方は良質の小麦を大量に生産しようと努力されます。それが技術改良にもつながります。
そこで質問します。水田農業構造改革(新産地づくり対策)交付金等の交付方法を、担い手農家の意欲を引き出す制度に変えませんか。答弁を求めます。
元千葉農林振興センター所長、坂口和彦氏は「農業立市宣言-平成の市町村合併を生き抜く」という書物で、「国や県の業務命令や補助事業に従って、時折上級庁に苦言を呈すればすむというわけにはいきません。自分たちで管内事情を精査し、問題点を洗い出し、課題を明確にして政策、企画する自前のオリジナルな農政が求められています」と記されています。市町村合併をされなかった新潟県津南町の町長小林三喜男さんも「農をもって自立を目指す町・津南町-町民と職員がひらく豊かな農村」という本を出されておられます。田原本町都市計画マスタープラン素案には、北校区と東校区が営農のための環境と保全を必要とする地域になっています。やはり農業のできるところでは農業を振興することが生活の基盤をつくり、後継者の若者を生み出すことになるのではないでしょうか。
そこで、兵庫県豊岡市の取り組みを少し紹介します。「コウノトリも住める豊かな自然環境と文化環境は人間にとってこそすばらしいものに違いない」という中買宗治市長のもと、コウノトリ野生復帰事業、安全安心の農作物認証制度、豊岡市環境経済戦略、子どもの野生復帰大作戦など、コウノトリを中心のまちづくりに挑戦されておられます。初めはコウノトリの人工飼育や繁殖が中心テーマであったのが、いざ放鳥するためには、カエルやドジョウなどコウノトリの食糧豊かな田んぼがないとだめということがわかって、環境保全型農業、有機稲作への転換が必要になったそうです。今でこそコウノトリツーリズムが盛んになり、コウノトリの郷公園来訪者は2005年の24万人から2006年48万人にふえて、観光農業の振興に貢献しています。
最初はコウノトリが田んぼに降りたら、稲を踏みつけて米の収穫が減るといやがる農家の方が多かったそうです。ところが合ガモ農法で田んぼに合ガモを入れたところ、かわいくて子どもや孫が話をしてくれるようになったと、農家の方が変わられたそうです。今は有機肥料で苗づくりを行い、深水管理で雑草が生えるのを抑えて、無農薬無化学肥料農業を実現されています。慣行農業と比べて生産量はどうかというと、北海道の数字しか持ち合わせてないのですが、それを示しますと、慣行農法と比べて有機農法では85%程度だそうです。しかし、うまくいったら慣行農法を上回る出来高を実現しているところもあります。
本町も安心安全の農業推進のまちを宣言して有機農業を進めてはどうでしょうか。現在町内には有機農業を実践されておられる方を3人は存じ上げています。退職帰農組の方で、興味を持っておられる方はたくさんおられるのではないでしょうか。町がまず勉強をして、そして音頭を取って、興味をお持ちの方から有機農業を始められる、その田んぼが今度はビオトープとして子どもたちが楽しむ。安心安全のお米を売って喜んでもらえる、そんな町にしようではありませんか。これまでのように、営農は農協に任せておくという姿勢では農業はジリ貧です。町長が夢を語り、職員が農家を回り、農協など関係者の協力を得て農業を中心のまちづくりを進める、何か楽しくなるのではないでしょうか。
そこで質問します。農業振興を図るために町長はどのようなビジョンをお持ちですか、答弁願います。私は、安心安全の農業推進のまちを宣言し、農薬や化学肥料に頼らない農業で農家の誇りと豊かな自然を自慢できるまちにしたいと切望しています。
最後に、1つ質問を追加させていただきます。今回の議案の中で、国民健康保険税の改定ということが町長から提案されました。残念ながら議案には出ていませんので、事前に担当課に問い合わせたところ、全体の場でしたら回答できるということでした。この場を借りて、平成20年度国民健康保険税の料率をどうされる予定なのか、答弁を求めて私の一般質問を終わります。
議長(松本宗弘君)
5番、吉田議員に申し上げます。一般質問につきましては、ご承知のとおり事前通告制を採用しておりますので、通告以外の質問につきましては他の機会にしていただけますようお願いいたします。
それでは答弁を求めます。町長。
(町長 寺田典弘君 登壇)
町長(寺田典弘君)
それでは5番、吉田議員の質問にお答えをさせていただきます。
私のほうからは、大きな1の1つ目と大きな3番の1つ目、3つ目についてご答弁をさせていただきたいと思います。
まず1番目の、税金の徴収姿勢についてお尋ねでございますが、1点目の、私の課税、徴税に関する方針についてお尋ねでございますが、財政状況が厳しさを増す中、福祉需要の増大や高度多様化する住民のニーズへの対応等、住民福祉の向上を念頭に、山積する行政課題に取り組んでまいらなければなりません。そのためには、財政力の強化が求められているところであります。
そこで、課税、徴税に関する方針といたしましては、改めて申すまでもなく、税務行政の基本である公平かつ適正な課税を行うことと考えています。常に正しく法令の解釈、運用を行い、適時適確な課税が必要であります。また、徴税の果たすべき役割は、税の公平、公正を確保し、納期内納付の基盤を確立することと、滞納額の圧縮を図ることであります。そのためには、地方税法はもとより、国税徴収法に基づき納期内納付されている大多数の方々との不均等を解消すべく、厳正、的確な整理に努めることが重要であると考えております。今後とも税負担の公平性を確保し、貴重な自主財源である税収入の確保に努めてまいりたいと考えております。
続きまして、3番目の農業施策についての1点目、農業施策の方向性、課題、目標につきまして、農業や農村は食糧の安定供給はもとより、自然環境の保全、良好な景観の形成、生物多様性の保全といった多面的機能の発揮を通じて人々の暮らしに重要な役割を果たしています。しかし、農業従事者の減少、高齢化、耕作放棄地の増大、経済社会のグローバル化の進展による国際的な食糧事情の変化や、環境問題に直面するなど、大きな社会構造の変化に直面をしています。
このような中、農業の体質強化を図るべく、専業、兼業農家などを始め、多様な構成員からなる農業の振興を第3次総合計画のもとに担い手となり得る認定農業者の育成、支援を始め、農作物の安心安全、信頼の確保、農業経営を支える生産基盤の整備、食育の推進など、各関係機関、団体とも連携し農業施策を推進してまいりたいと考えております。
続きまして、3点目の、農業振興の私のビジョンは、につきましては、田原本町独自の個性を生かした魅力ある農業を展開するには、個性を発揮する素材としましては、地形、気象や地域の伝統的な野菜、食文化などが挙げられます。また、生産者、販売者、消費者の連携、協力も不可欠であります。本町に合った素材の活用を検討し、議員お述べの取り組み事例も、農業振興を考える上での参考とさせていただき、農商工とも連携し、第3次総合計画のもとに鋭意計画実現に向け取り組みまして、本町の農業、農家生活に合った生きがい、仕事のしがいを実感できる魅力ある農業の振興に努めてまいりたいというふうに考えております。
以上、農業施策についての答弁とさせていただきます。
ありがとうございました。
議長(松本宗弘君)
総務部長。
(総務部長 福西博一君 登壇)
総務部長(福西博一君)
それでは1番目の、税金の徴収姿勢についての2点目の滞納者の生活実態を把握しているのか、というお尋ねでございます。まず、滞納整理の流れございますが、納期限後、未納者には督促状を発し納税を促します。なおも未納の者には納税促告書を発し、さらに納税を促してまいります。これらと並行いたしまして、来庁依頼や電話、臨戸によります納税催告や納税相談を実施し、生活実態や所得水準等を考慮し、全額納付が困難な場合には分割納付等に応じるなどの措置をとっているところであります。
なおも未納の者には再度最終催告書または差し押え執行予告書を送付するとともに財産調査を開始いたしまして、差し押え可能財産がある場合など、支払い能力がありながら納税の意思が見受けられない場合にはやむを得ず差し押えをいたすものでございます。なお、差し押え財産がない場合は、滞納処分の停止措置を講じているところでございます。そこで滞納者の収入状況や生活実態をどのように捕捉しているのかということでございますが、まず先ほど申しましたように、来庁依頼や、電話、臨戸等によります納税催告、納税相談を実施いたしまして、実態の把握に努めています。なお、こういったことに応じない者には、過去の滞納整理資料や課税資料並びに申告書等によりまして調査を実施いたしております。これと並行し、金融機関等への照会により収集した資料により把握をいたすものでございます。
以上でございます。
議長(松本宗弘君)
副町長。
(副町長 森口 淳君 登壇)
副町長(森口 淳君)
5番、吉田議員のご質問、2番目の情報公開についてのご質問にお答えをさせていただきます。
「現在、田原本町土地開発公社は情報公開の対象外になっているが、今後情報公開の実施機関になる予定はあるのか」というお尋ねでございますが、今後、田原本町土地開発公社といたしまして、情報公開を実施してまいります。
以上でございます。
議長(松本宗弘君)
産業建設部長。
(産業建設部長 森島庸光君 登壇)
産業建設部長(森島庸光君)
それでは吉田議員のご質問の3番目、農業施策についての2点目の「新産地づくり対策交付金を出来高制に変えれないか」につきましてご答弁をさせていただきます。
現在、主食用米につきましては、消費量が年々減少し続けたこともあり、すべての水田で生産を行うと過剰米が発生し、価格の下落を招くことになることから、農業者や産地が国からのニーズを踏まえ、需要に見合った適量の生産を行っていくことが重要であります。主食用米の生産調整、水田を活用した作物の産地づくりの推進を図るため、田原本町水田農業推進協議会において使途等を定め、町の実態に即した産地づくりを支援し、米の生産調整の意欲的な取り組みを助長していただいているところでございます。
以上のことから、現時点では交付金の交付方法を変更することは考えておりません。
以上でございます。
議長(松本宗弘君)
5番、吉田議員。
5番(吉田容工君)
ご答弁ありがとうございました。それでは自席から質問させていただきます。
まず2番目の、情報公開について、情報公開を実施するという答弁をいただきまして、心強く思っております。例えば、広陵町は、決算議会のときには、町の発行する資料の中に土地開発公社の保有財産、住所、面積、取得日、取得価格というのを資料として各議員さんに配付されておられます。そういうことも入れて、積極的な公開をお願いしたいなと思うわけであります。それとともに、もう1つだけ質問ですけれども、情報公開をするということは、情報公開条例を改正するということにつながるのかと思いますけれども、いつの時期にそれを実施されるのかということを答弁願います。
次に、3番目の農業の問題についてであります。これまで田原本町は、地場産業があった工業、さらには交通の要衝に位置する商業、そして農業と3つの産業が本当に均等よく発達していたということであります。その点では、町が何をしなくても産業は活況を呈していたという時代が続いたんだと思います。ところが今は、地場産業もなくなりました。商業も停滞していると、そして農業に至っては高齢化が進んで、あと5年もしたら生産者が減るんじゃないかなということが心配されているわけです。その点では、今からその対策を練られることが一番いいんじゃないかなと思うわけであります。
今、本当に生活が苦しい中で、奈良県産の「ひのひかり」がどのぐらいの値段で売られているかと言いますと、大体1キロ300円ぐらいの値段で小売で販売されています。300円から400円、万代は400円でしたけれどもね。それが有機農産物の有機のお米は700円ぐらいでやっぱり売られているんですね。「ひのひかり」が1キロ300円としますと、御飯1ぜん大体30円ぐらいの仕入れとなるわけです。その点では、やはり先ほど小走議員がおっしゃったように、パン食よりも米飯食のほうが生活費が抑えられるということにもつながるんではないか。さらには健康の面でも優れているんじゃないかと思うわけです。
その点で、田原本町が今出している第3次総合計画の1つは、担い手の育成ということを柱に掲げておられます。2つ目が安心安全の農業と、この2つの柱でやっておられますよね。その点では、私が今回提案させていただいています環境保全型農業というのは、田原本町第3次総合計画に沿った提案じゃないかと思うわけです。そこで質問するわけですが、田原本町、今、総水田面積が863町あると思うんですね。このうち担い手の方がどれだけ耕作されているか。そして、今総農家が1,200と言われていますが、その中で専業は約100戸じゃないかと言われてますけれども、兼業農家がどのぐらいのウエートを占めているか、数字を示していただきたい。
それと、先ほど答弁いただきましたけれども、産地づくり対策資金の交付は、篤農家に対して米の生産調整を意欲的な取り組みを助長すると、米の篤農家に対してつくるなということを助長する政策だという答弁であったわけですね。その点、やっぱり非常に実際小麦をつくっておられる方は、先ほど言いましたように、1キロできて40円もらえる、しかし農協に48円払わなあかんと、できればできるほど負担が多くなるという制度になってますので、その点ではやはり、国が言っているからという面もありますが、町としてやはり考え直さなければならないんじゃないか。特に農家の方々は、これまで国の言うとおりしてきたけれど、えらい目にばっかり遭うたという気持ちでおられるわけです。その点では、田原本町が担い手をどう応援するかという施策をこれからどうされるか。
それともう1つは、退職帰農組を含めた方々を中心に、環境保全型農業をどう進めるのか。やはり町が音頭を取って、お金はかける必要はないと思いますけれども、音頭を取って普及していくということが必要だと思いますけれども、そのへんで具体的にどういう計画をされているのか、答弁願います。
3つ目ですけれども、最初の税金の問題であります。ご答弁いただいた中で、滞納者の方の生活実態や所得水準を調べているという答弁をいただきました。その中で、支払い能力がありながら納税の意思が見受けられない場合にはやむを得ず差し押えしているということでした。今の税法の中では、町長の今回の予算の提案にもありましたけれども、悪質な滞納者に対しては厳しく対応するということが書かれています。悪質な滞納者というのはどういう人かと言いますと、私は、支払い能力があるにもかかわらず払わない人が悪質な滞納者であると。支払い能力がなかって払えない人は悪質な滞納者じゃないという理解をしていますし、これは国の指針だと思うんですけれども、その点では、田原本町が考えておられる悪質な滞納者がどういう人なのかと、どういう定義なのかということを示していただきたい。さらには、今滞納されている方が何件で、そのうち経済的理由、例えば財産に被害を受けた、災害を受けたとか盗難に遭ったとか、生計を一にしている親族が病気にかかったとか、事業を廃したとか、失業したとか各理由があるわけですけれども、滞納者のうちにどういう割合で滞納者がいてるのか、その数字を示していただきたい。
以上です。
議長(松本宗弘君)
副町長。
副町長(森口 淳君)
土地開発公社の情報公開制度につきましては、県内では、奈良県土地開発公社が同公社独自の情報公開に関する規定を定め、奈良県の情報公開条例に準じた情報公開制度を設けております。奈良県下の市町村におきましても、土地開発公社についてはほとんどがこのような情報公開の体制をとっております。したがいまして、田原本町土地開発公社につきましても、田原本町情報公開条例に準じた情報公開制度の規定を制定して、早々に実施をしていきたい、このように考えます。
議長(松本宗弘君)
産業建設部長。
産業建設部長(森島庸光君)
農業政策につきましての再度のご質問でございます。1つ、統計的に専業農家の戸数でございますが、認識しておるのは約100戸でございます。それから、水田の面積について、今ちょっと資料持ち合わせございません。後ほど示させていただきたいと思います。
それから、いろいろ環境問題から農地の保全が大切だというお話がございました。すぐにこれに結びつくかどうかわかりませんが、現在、農地水環境保全向上活動支援事業ということで、その地域で休耕田をなくすとか、荒れ地をなくすとか、地域で農地の保全に取り組んでいただくところに補助金制度を設けております。これが1点でございます。
それから、今後の方針でございますが、町長も1回目の答弁で申し上げておりましたとおりでございますけれども、議員おっしゃるように、農業者を一律に支援するこれまでの政策がいいのかどうか、あるいはやる気と能力のある経営者をどう育成していくか、また、高付価価値型の高品質な生産物をどうしていくのか、あるいはまた食糧自給率が日本は低いと言われます、これの向上をどうするのか、課題はたくさんあります。また、地域の農業者団体からのご意見もまたいただきたいと思います。また、個々の農家の方のご意見も伺いながら、今後検討してまいりたいと思います。
議長(松本宗弘君)
総務部長。
総務部長(福西博一君)
悪質な滞納者ということでございますけれども、先ほど私お答えしたように、支払い能力がありながら納税の意思が見受けられない、こういったものが悪質な滞納者と考えております。それと、滞納者の理由別の件数とおっしいましたが、ちょっとそういう集計は取っておりません。ただ、平成20年の1月16日現在でございますけれども、納税催告を3,263件に発送いたしております。
以上でございます。
議長(松本宗弘君)
産業建設部長。
産業建設部長(森島庸光君)
専業農家、先ほど約100戸と申し上げましたが、122戸でございます。それから兼業農家が1,096戸、合わせまして1,218戸でございます。
それから水田面積が845ヘクタールでございます。
以上です。(「845って全部の水田と違うのでないか、担い手農家の分は幾らなのか」と吉田議員呼ぶ)もう一度再調査させていただきます。申しわけございません。
議長(松本宗弘君)
5番、吉田議員。
5番(吉田容工君)
品目横断対策の小麦の面積は大体30町ですよね。大体減反を5割してますから、大体私は60町じゃないかと思うわけですけれども、830町ある中でわずか60町ぐらいしか品目横断対策になってない。ということは、あとの農地を維持するためには、田原本町土地開発計画マスタープランに書いてあるような緑農ゾーンをつくるためには、それ以外の兼業農家の方が農業をやってもらわないと成り立たないというのが今の実情ではないかと思うわけです。その点では、この第3次総合計画に沿った質問をしてますから、もう1年たつわけですよね、これできてね。そしたら、具体的にどうなってきたかと言うたら、これからなというわけですので、そこに関してはやっぱり町長のリーダーシップをぜひ発揮していただきたいなと。全部一気に変わるのはできませんから、先ほど言ったように環境保全型農業をどうしようかということで、やはり安心安全の農作物を田原本から供給するんだということを中心にぜひ進めていきたい。これについて再度町長から答弁をもらいます。
1点目の税金の徴収ですが、実態を把握していると言いながら、その滞納の理由の統計を取ってないということは、わかってないということだと私は思うわけです。その点では、形の上では手続きやっているけれども実態を把握してないんじゃないかと思うわけです。実際にはたくさん、3,260件もあるから行けへんということもあるかもしれません。しかし、差し押えするというのはそんなに多くないわけですよね。せめてそこに差し押えする前には、必ず連絡を取る、確認をする、実態をつかむ、そういうことが必要じゃないでしょうかね。このことも答弁を求めて質問を終わります。
議長(松本宗弘君)
町長。
町長(寺田典弘君)
貴重なご意見ありがとうございます。おっしゃるとおりでございまして、先ほど議員お述べになられたように、農業政策の課題につきましては、農業者の高齢化、また兼業等による担い手の不足というのが挙げられますし、また、食品の安全性に対する消費者の意識の向上というのが2点、大きなものとしてあります。それ以外にも、今おっしゃいましたように、遊休農地の増加というのが非常に大きな問題となってきております。また、それに加えまして米の生産過剰と、こういう課題もございます。今後とも環境保全型等に通じまして、要するに付加価値のついた農作物、生産品をつくっていかねばならないというふうに考えております。
最近よく言われることでございますけれども、農業はもちろん第一次産業ではございます。ただ、これを第一次産業としてだけとらえるのではなくて、第六次産業としてとらえろと。第一次産業の農産物に対して加工という第二次産業の加工を加え、そして第三次産業である商業により売っていくというような考え方でございます。それを一つの流れの中で考えていけるような対策を取っていきたいというふうに考えております。
ありがとうございました。
議長(松本宗弘君)
総務部長。
総務部長(福西博一君)
地方税法では、督促状を発した日から10日を経過した日までに納付がなければ差し押えをしなければならないという規定がございます。しかしながら、私ども先ほどからご説明をいたしておりますように、督促状を発した後においても来庁依頼や電話、また臨戸によりまして催告を何回も何回も繰り返しております。その中で納税相談をする機会をつくっております。この間で納税をいただくものもおられます。また分割による納税をされる方もございます。また滞納処分の停止をする方もございます。決してある日突然差し押えするということは絶対にございません。ご理解をいただきたいと思います。差し押えをする場合は、先ほど申しましたように、悪質な滞納者に対しては、こちらも強硬……(「ちょっと答弁違いますよ、悪質な滞納者と催告しても来ないという話とは違いますやろ、ゆとりあっても払わない人を悪質な滞納者と言ったですね。全然つじつま合ってないですよ」と吉田議員呼ぶ)だから悪質な滞納者には、こういったことに応じない、先ほど申しましたことに応じない、支払い能力があるのに納税の意思が見受けられない方々には、いわゆる強硬な対応をしてまいっているところでございます。ご理解をいただきたいと思います。
議長(松本宗弘君)
産業建設部長。
産業建設部長(森島庸光君)
数字の漏れがございました。担い手の人数は48人でございます。それから集積面積と言うのは水田の集積面積ですか、小麦の集積面積のことですか。(「全部行ってる人。その人らの行っている面積」と吉田議員呼ぶ)192ヘクタール。
議長(松本宗弘君)
以上をもちまして5番、吉田議員の質問を打ち切ります。
これをもちまして一般質問を打ち切ります。
以上で本日の日程はすべて終了いたしました。本日の会議はこれにて散会いたします。
ありがとうございました。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
担当課:議会事務局
電話:0744-34-2119