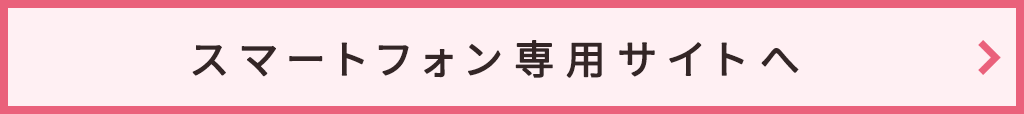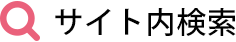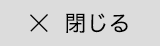ひとり親家庭等医療費助成制度
2023年4月1日更新
対象者
- 配偶者(婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)のない者であって、18歳未満の児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者)を扶養している者、およびその児童
- 父母のいない児童のうち18歳未満の児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者)
- 1、2の児童を養育している配偶者のいない者、または婚姻したことのない者
上記1、2、3のいずれかに該当し、加えて次の条件も満たす者
- 生活保護を受給していない者
- 母または父、およびこれに準ずる者(ひとり親)が田原本町に住所を有すること
例えば、下記の家庭が該当します
- 母子家庭または父子家庭
- 祖母または祖父と孫の家庭(祖父母がいる場合は、孫だけが助成対象)
- 未婚の姉または兄と、妹・弟の家庭
児童(3の場合妹・弟)が18歳の誕生日を迎えて、最初の3月31日までが助成の対象です。
申請に必要なもの
- 健康保険証 (母・父・児童などのもの)
健康保険証が、離婚する前の配偶者の扶養に入っている場合は、手続きをすることができません。国民健康保険や他のご家族の扶養に入るなど、健康保険証の切り替えをしてください。 - 個人番号カード、または通知カード (母・父・児童などのもの)
- 写真付き本人確認書類 (窓口にお越しの人のもの。個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)
- 印鑑 (認印で可)
- 金融機関の通帳
- 市町村民税課税証明書 または 所得証明書 または 給与所得の源泉徴収票の写し (扶養義務者が1月1日現在、 他市町村に在住しておられた場合のみ)
- 委任状 (代理人が窓口にお越しの場合のみ)
注意
資格取得日は離婚された日ではなく、申請に来られた日(窓口での手続きの日)が基準になります。
毎年有効期限前に更新申請書類を郵送します。
助成金の支給方法と助成額
保険治療にかかる診療が対象となります。
県内の医療機関窓口に、受給資格証を、健康保険証とともに提示いただき、自己負担額を支払っていただきます。
診療月の約3ヵ月後に、次の金額を指定された口座へ振り込みます。(自動償還方式)
※義務教育就学前のお子さんについては「現物給付方式(一部負担金のみで受診)」です。
通院・14日未満の入院の場合
レセプトごとに500円を差し引いた額
(1ヵ月、1医療機関、入院・外来別、歯科・歯科以外の診療科ごと)
14日以上の入院の場合
レセプトごとに1,000円を差し引いた額
(1カ月、1医療機関、入院・外来別、歯科・歯科以外の診療科ごと)
- 高額療養費等が支給される場合は、自己負担額から高額療養費等を先に控除して計算します。
- 差額ベッド・健康診断・予防接種・薬の容器代などの保険外医療費や入院時の食事代は対象外です。
- 振込までに3ヵ月以上かかる場合もあります。
- 調剤薬局は全額助成です。
県外で受診したとき
県外の医療機関で受診されたときは、自動償還になりません。次の必要書類を持って、保険医療課福祉・高齢医療係で手続きをしてください。
- 氏名、保険点数、自己負担額が記載された領収書
- 高額療養費支給決定通知書(該当する人のみ)
- 健康保険証
- 金融機関の通帳
- 印鑑
郵送による申請も受け付けています
助成金交付請求書を下記から印刷し、申請者欄、受給者氏名、振込口座等を記載し、申請者欄に捺印のうえ、領収書・保険証・高額療養費支給決定通知書(該当する人のみ)を必ず添付して田原本町役場保険医療課福祉・高齢医療係宛に郵送してください。
添付書類は、いずれもコピーで可能です。
県外で受診したときの助成金交付のご案内と請求書 (PDFファイル: 18.0KB)
次のような場合は、必ず届出をしてください
- 住所が変わったとき
- 加入している健康保険証に変更があったとき
- 医療受給者証を紛失したとき
- 受給資格がなくなったとき
- 交通事故など第三者の行為による怪我等の治療で、証を使用したとき
- この記事に関するお問い合わせ先
-
担当課:住民保健課保険医療年金係
電話:0744-34-2095/0744-34-2096