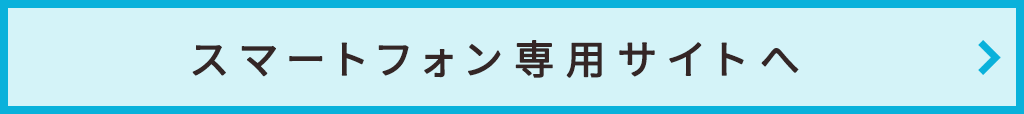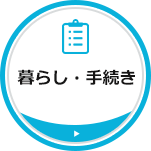多神社の太安萬侶像

区分
有形文化財 (彫刻) 【町指定】
名称
木造太安萬侶神像(もくぞうおおのやすまろしんぞう) 1躯
時代
室町時代 15~16世紀
所在地
奈良県磯城郡田原本町大字多569
交通
近鉄橿原線笠縫駅下車 西へ徒歩20分
内容
本像は、かつて多神社の第二殿に祀られていた太安萬侶の神像と伝わるものです。
左手は笏(しゃく)の下端を握り、右手はその頂に掌を添え、両足裏を合わせて畳座に座る姿をしています。左に折れた烏帽子(えぼし)を頭に被り、平安時代以降の朝廷男子の正服であった束帯(そくたい)風の衣服を着ています。
太安萬侶は『古事記』(和銅5年(712)成立) の編纂者で、歴史上著名な奈良時代の官人です。後世、彼が多氏の祖先神として神格化される段階で、本像が造られたと考えられます。吊り上がった眉や閉じた口、短い顎髭(あごひげ)など精彩ある顔つきです。体は厚みがあり、両袖の先端が強く跳ね上がらない表現や、構造技法の特色から、製作は室町時代(15~16世紀)と推測されます。
全国的な視野からみても、神像彫刻の歴史は実態が不明なところが多く、奈良県下においても所在調査があまり進んでいません。そのような中で、本像は神格化された太安萬侶の神像として中世美術史の展開を考えるうえで重要であり、また地域史の視点からも注目すべきものです。
多神社:『延喜式』神名帳に記載される「多坐弥志理都比古神社(おおにいますみしりつひこじんじゃ)」にあたるとされる式内社。神武天皇・神八井耳命(かむやいみみのみこと)・神淳名川耳命(かむぬなかはみみのみこと 綏靖天皇)・姫御神(玉依姫)の四座を祀っています。このうち神八井耳命は、太安萬侶らをはじめとする古代氏族 多氏の祖とされています。
拝観連絡先(多神社) 電話:0744ー33ー2155
- この記事に関するお問い合わせ先
-
担当課:文化振興課文化財活用係
電話:0744-34-7100