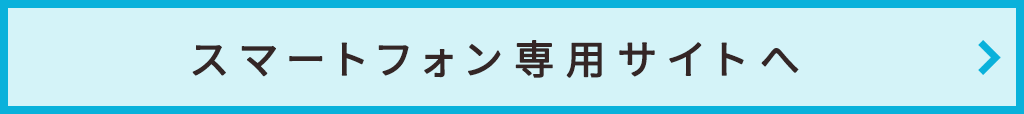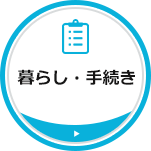補厳禅寺納帳
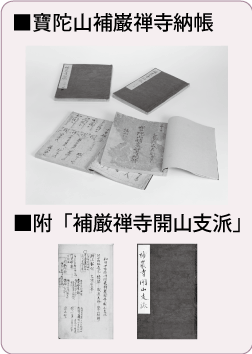
中世の奈良は興福寺の支配下にあり、田原本町では各地域に在地武士が勢力を張っている状態でした。その中の有力な武士として十市氏がおり、現在の橿原市北部から田原本町東南部をおさえていました。この十市氏の菩提寺にあたるのが補巌寺です。
補巌寺は至徳元年(1384)に了堂真覚(りょうどうしんかく)によって開山された寺院で、室町時代には十市氏の庇護(ひご)を受け、菩提寺として寺勢を伸ばしました。江戸時代には味間村の領主藤堂氏の祈願所となりましたが、安政5年(1858)に焼失し、山門・庫裏・鐘楼のみになりました。
さて、補巌寺の納帳は4冊残存しており、その1は明応7年(1498)、その2は大永末年頃、その3は永禄末年頃、その4は元亀3年(1572)に書写されたもので、ほぼ同一の内容のものです。納帳にみえる田畠・屋敷地は約45町歩に及んでおり、その所在地は十市郡を中心に城上・城下郡に拡がっています。田畠などについては、作主の名前のほかに村落や小字の名称を記載しており、現在の小字名と比較することでその所在地を特定できるものが多くみられ、土地の変遷を知るうえで大変貴重です。
この「補巌禅寺納帳」は、故・表章(おもてあきら)法政大学名誉教授によって発見されましたが、そのきっかけは能楽研究者の香西精(こうさいつとむ)氏が、世阿弥から金春大夫(こんぱるだゆう〈別名・禅竹=ぜんちく〉)に宛てた書状にみえる「ふかん寺」が田原本町味間の補巌寺であることを突き止めたことにありました。この二人は、納帳に世阿弥やその妻の法号である「至翁禅門(しおうぜんもん)」、「寿椿尼(じゅちんに)」の記載を納帳に見いだし、世阿弥夫婦が補巌寺で永く菩提を弔われたことを明らかにしました。
世阿弥は、補巌寺第2世・竹叟智厳(ちくそうちげん)に師事し多大の影響を受けました。その芸論には禅林字句の引用が多くあります。また、至翁禅門の忌料(きりょう)として補巌寺に寄進された味間領の「字スチカ井 東ノ八」の田は今も存在しており、補巌寺は世阿弥参学の地として、能楽関係者から慕われています。
「寶陀山補巌禅寺納帳」 4冊
種別
有形文化財(古文書)
所有者
補巌寺
大きさ
その1 縦31.9cm・横12.3cm(40紙)
その2 縦31.5cm・横25.2cm(41紙)
その3 縦31.0cm・横25.1cm(42紙)
その4 縦30.7cm・横24.8cm(45紙)
時代
室町時代
附「補巌禅寺開山支派」 1冊
種別
有形文化財(古文書)
所有者
補巌寺
大きさ
縦30.1cm・横18.9cm(11紙)
時代
江戸時代
- この記事に関するお問い合わせ先
-
担当課:文化振興課文化財活用係
電話:0744-34-7100