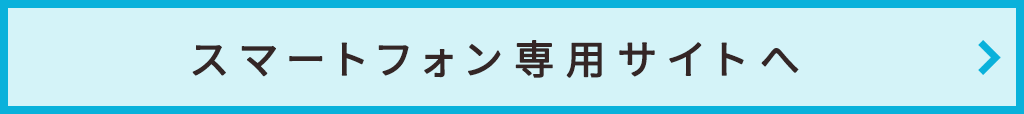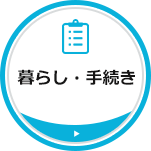田原本町に伝わる昔話 - 第4話
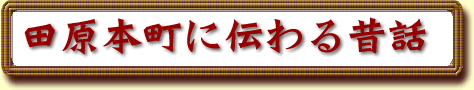
矢継ぎの森のはなし(広報たわらもと1989年6月号掲載)
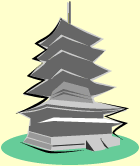
むかし聖徳太子が、どこか自分の住むのに適した所はないものかとおおせられて、南から西北の方向を向き、「あの方面がよいように思われるので、これから矢を射るから、わたしはその落ちたところに行こう」と申されました。そして矢を放たれると今の矢継ぎの森に落ちました。
そこで家来がその事を申し上げますと、太子はまだ距離が近いからとおおせられて、再び矢を放たれると、現在の法隆寺のところに落ちました。いよいよこれでよいとて、永住の地と定められました。
矢継ぎの森にはいま「矢継ぎさん」(屋就ぎ)の祠があります。
むかし、大和の土佐(高取町)の殿様が、郡山の殿様の方へ向いて矢を射ました。すると今の田原本町多にある神社の西、数百メートルのところの小さな森のある所へ落ちました。これではならぬと、そこからまた矢を継いで再び射ました。それからこの森を「矢継ぎの森」というようになりました。
二話とも『こどものための大和の伝説』仲川明(大和タイムス社)
※「矢継ぎさん」の土地には屋就神命(やつぎのかみのみこと)をまつる小祠があり、多神社の摂社です。現在は橿原市大垣町矢就に所在します。
よく似た話がもう一つあります。
むかし、聖徳太子が法貴寺に住もうとしやはったが、水害の多い所(とこ)やからここに住むのは適当でないと言わはって、ここから(千萬院)矢を射やはった。そしてその矢の落ったところに建てやはったんが法隆寺やと、わしの子なじぶんに祖父(じい)さんから聞いてました。
上田一郎氏(法貴寺)の話から
※《聖徳太子》(574~622)用明天皇の第二皇子。名は厩戸豊聰耳皇子(うまやどのとよとみみのおおじ)。聖徳太子は諡名(いみなめい)。特に仏教興隆に尽力し、法隆寺・四天王寺を建立するなど多くの業績を遺しました。
こうした功績から太子は、鎌倉時代になると日本の釈迦として崇められるようになり、釈迦にその誕生仏がつくられたように、太子幼少期(二歳)の南無仏太子像、青年期(十六歳)の孝養像、壮年期の摂政太子像など、種々の姿の彫刻や仏画がつくられました。
田原本町内のお寺では、南無仏太子像と孝養像が多くのこっています。
また、太子が法隆寺と飛鳥を往復されたという道が、「太子道」(筋違道)(すじかいみち)の名でのこっており、宮古から黒田、さらに三宅町・川西町へと、ハイキングコースにもなっています。
屋就神社の東側の道は「矢継街道」と呼ばれ、北進して太子道と合流するのです。
なお聖徳太子のころ、法貴寺には沢山のお寺がありましたが、今では千万院を残すのみとなって、このお寺も聖徳太子が建立され、奏河勝が賜ったとの言い伝えがあります。
雷の話いろいろ(広報たわらもと1989年7月号掲載)
一、雷公(らいこう)の詫言(わびごと)(津島神社)

今からおよそ八百年ほど前の昔、この神社の神様は極度に雷を嫌われていました。
ある日、ゆくりなくも雷公が足をふみはずして落下し、境内の大木を焼いてしまいました。
神様は激しく怒って雷を捕らえて神域の大木に縛り付け、みだりに落ちて大衆を騒がす罪を責められました。雷公はいたく恐縮して「この土地へは我はもとより、わが子々孫々に至るまで決して落ち来たり候まじ」と詫び、以後落ちないことを誓いました。
雷公はようやく許しを得て縛りを解いてもらい、くだんの大石を伝って大空に帰り去りました。その大石には、雷公のかきむしったツメの跡がいまだに歴然とのこっているということです。
(『大和タイムス』昭和三十五年)
※この石は陽石とされ、神殿の前にまつられてます。
二、井戸に落ちた雷(須賀神社)
味間の宮さんに太い大きな杉の木があって、この木によく雷が落ちて、村人を脅かしておりました。
ある日、また雷が杉の木に落ちましたが、勢いあまってそばにあった井戸に落ちました。そこで村人は「それっ」とばかりに井戸に蓋(ふた)をしてしまいました。それ以来雷は落ちなくなったということです。
いまではその井戸もなくなり、大きな杉の木も枯れて、幹だけになってのこっています。
(古老の話から)
三、今里には八王様をまつりたれば、落雷することなしという。
(『川東村他風俗志』奈良県立図書館蔵)
また同じように、「笠形には毘沙門さんを祀るので雷は落ちない」との古老の話があります。
四、ほかに「雷はトラの皮のフンドシをしめ、人間のヘソを好み、ヘソを出していると取りにくる」とか、「蚊帳の中に入っていると雷は近づかない」ともいわれています。 歌にも「線香たてま籠(こも)れ そのまにヘソかくせ」があり、雷が鳴り出すと蚊帳にはいって、祖母や母がよく歌ってくれたものです。
五、ではちょっとここで、田原本町に伝わるお伽話(おとぎばなし)から、落語を一つしてみましょう。
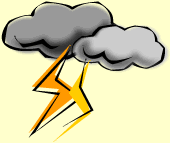
むかしむかし、お日さんとお月さんが伊勢参りをしようという相談がまとまりました。雷がこれを聞いて「どうか私も連れて行って下さい」と頼みました。
お日さんもお月さんも雷に向かって「お前のようにゴロゴロと言うのはやかましいから連れて行くことはできない」と申しました。
雷は参りたくてたまりません。それで「これから戒心いたしまして、けっしてゴロゴロ言いませんから、どうぞ連れて行って下さい」と頼みました。あまり雷が頼みますから仕方なしに連れて行ってやろうと申しました。雷は大喜びでお月さんとお日さんの後について行きました。
途中で宿屋に泊まりましたが、雷の寝ている間にお月さんとお日さんが相談なさいました。
それは、雷があのように言っているがすぐゴロゴロと言うに決まっているから、今のうちに立ってしまおうではないかと言うのでした。それでまだほの暗い中に、雷の寝息を考えて二人は宿屋をお出ましになりました。
後で雷が目を覚ますと、お月さんもお日さんも見えません。どうしたことかと主人に尋ねますと「もうさっきお立ちになりました」と言います。
雷はおどろいて「さてさて月日の経つのははやいものだなあ」と言いましたトサ。これから「月日の経つのは早いもの」ということわざができたということであります。
(磯城郡四ヵ村風俗志より)
さらにそこへ加えると、《宿の主人が雷に向かって「それでは雷さんはいつお立ちで?」。
「では私は夕立(ゆうだち)にしよう」》で落ちとなります。
次回は「魔よけのザクロの木」「弘法大師にまつわる話」です
- この記事に関するお問い合わせ先
-
担当課:文化振興課図書館係
電話:0744-32-0262