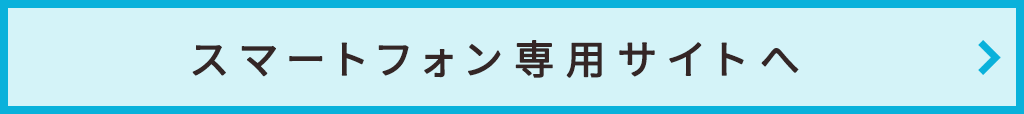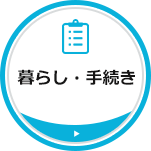国民健康保険 - 保険税の決め方
2025年7月25日更新
国保税の税率
国民健康保険の県単位化に伴い、令和6年度より保険税率が奈良県内統一となりました。「同じ所得・世帯構成であれば県内のどこに住んでも保険税(料)は同じ」になります。
| 区分 | 医療分 (被保険者全員) |
後期高齢者支援金分 (被保険者全員) |
介護納付金分 (40歳以上65歳未満の人のみ) |
|---|---|---|---|
| 所得割 | 7.64% | 3.27% | 3.03% |
| 均等割 | 27,600円 | 11,500円 | 16,900円 |
| 平等割 | 20,000円 | 8,400円 | なし |
| 限度額 | 65万円 | 24万円 | 17万円 |
国保税は、医療分・後期高齢者支援金分・介護納付金分を合わせたものとなります。ただし介護納付金分は、40歳以上65歳未満の人についてのみ算定します。
医療分・後期高齢者支援金分は、所得割、均等割、平等割の合計、介護納付金分は、所得割、均等割の合計となります。
所得割
各被保険者の前年中の総所得金額等から基礎控除額43万円を差し引いた金額の合計額 × 税率
控除後がマイナスになる場合は0として計算します。
均等割
被保険者一人当たりにかかる税額
未就学児(当該年度末時点で0~6歳の被保険者)は均等割の5割を軽減します。
平等割
一世帯当たりにかかる税額
所得申告
世帯主、同じ世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者(後期高齢者医療制度の適用により国保の資格を喪失された方で、その資格喪失後も継続して同一の世帯に属する方)の収入・所得を申告していただく必要があります。前年中の収入・所得が少なく所得税もしくは町・県民税がかからない場合でも、その旨の申告が必要です。
申告されない場合は、所得の確認ができないため本来の保険税計算ができず、保険税の軽減を受けられなかったり、高額療養費の自己負担限度額が高くなる場合もありますので、必ず申告してください。
非自発的失業者の国保税の軽減
非自発的失業者にかかる国民健康保険税が軽減されます。
令和6年3月31日以降に解雇などの非自発的理由で失業し、国保に加入された場合、失業した方の給与所得を100分の30として、所得割が算定されることになります。
軽減が適用されるには届出が必要ですので、下記項目に該当される方は住民保健課に申請してください。
令和6年度に申請している人は、再度申請する必要はありません。
対象者
離職日が令和6年3月31日以降で、雇用保険受給資格者証の『離職理由』に次のコードが記入されている人 11、12、21、22、23、31、32、33、34
軽減される期間
離職日の翌日が属する年度とその翌年度
申請に必要なもの
雇用保険受給資格者証、マイナ保険証や資格確認書等
国保税の納付方法について
- 普通徴収…納付書または口座振替で納付する方法
- 特別徴収…年金から国保税を差し引いて納付する方法
特別徴収(年金からの天引き)の対象者
1〜3の全てに当てはまる人
- 国保の世帯主が国保の被保険者であること
- 世帯内の国保の被保険者全員が65歳以上75歳未満であること
- 特別徴収の対象となる年金額の年額が18万円以上であり、国保税が介護保険料と合わせて、年金受給額の2分の1を超えないこと
※年度途中で65歳になり、上記の条件に当てはまる世帯及び75歳になり上記の条件からはずれる世帯は、当該年度は特別徴収にはなりません。
特別徴収(年金からの天引き)から口座振替へ変更できます
現在、特別徴収(年金からの天引き)で収めていただいている人は、国民健康保険税の納付方法を口座振替に切り替え、申出していただくことにより、特別徴収(年金からの天引き)を中止することができます。
令和7年度以降に特別徴収の条件に当てはまる世帯についても、口座振替にしておくことで口座振替を優先します。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
担当課:住民保健課保険医療年金係
電話:0744-34-2097