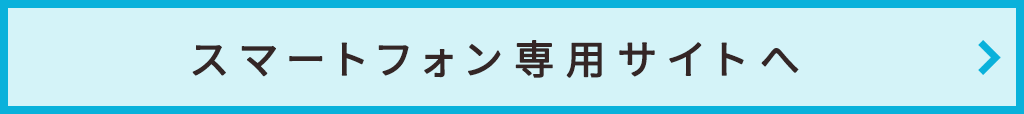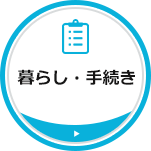お子さまのよりよい就学にむけて〜お子さまのもつ力を最大限に伸ばすことのできる学びの場を考えましょう〜
お子さまにとって必要な教育は何か、その教育が受けられる就学先について考えることはとても大切です。
学習内容がわかり、活動の中で達成感を持ちながら生きる力を身につけていくための学びの場について、本人や保護者を含む関係者で十分に話し合って考えていきましょう。
就学・教育相談について
田原本町教育委員会では、小学校・中学校で特別な支援が必要なお子さまにとっての、ふさわしい学びの場について、教育支援委員会を開き、教育相談を行っています。
対象となるお子さま
1.来年度小学校に就学するお子さまで、下記特別なニーズがあるお子さま
- 視覚障害がある
- 聴覚障害がある
- 肢体不自由がある
- 医療的ケアが必要である
- 発達の遅れがある
などにより、医療や療育を利用しているお子さま、幼稚園や保育所、認定こども園などで個別的な支援を受けているお子さま
今はまだ、相談や療育は利用していないがお子さまの姿から学校生活に不安があると考えられるお子さま
2.小学校、中学校の通常学級に在籍するお子さまで、学習や学校生活において、上記1に挙げる特別なニーズがあるお子さま
特別支援教育における多様な学びの場
特別支援の内容について
お子さま一人一人の困りごとは生活の中で様々です。学校生活の中で、一人一人のお子さまがどんなときに「困り感」を感じ、どのような合理的配慮があれば過ごしやすかったり、学習が積み上がっていったりするのかを考えながら支援を行います。
教師だけでなく、本人や保護者も交え相談しながらどのような支援があればよいかを考えていきます。
合理的配慮の例
○指示の理解に困難があるお子さまの場合、指示をひとつずつ出し、そのたびに認められ、次の指示を期待して聞けるようにする。
○見通しがつきにくく、新しいことをする場面で不安になりやすいお子さまの場合、見通しがつきやすいようにその日の予定をカードや表に示すなどして見てわかるようにする。
○文字を覚えたり、書くのが苦手なお子さまの場合、黒板を写真にとり、手元において、自分のノートに写せるようにする。
○周りの刺激に敏感で集中し続けるのが苦手なお子さまの場合、仕切りのある机を用意したり、別室で課題などに取り組めるようにする。
○読み書きに困難があるお子さまの場合、拡大教科書やタブレット、音声読み上げソフトを利用して勉強できるようにする。
○肢体や視覚が不自由なお子さまの場合、介助者や盲導犬の補助を受けながら学校生活を送れるようにする。
○知的障害があるお子さまの場合、その発達に応じた学習課題に取り組む。
など、学習内容の工夫、学習する体制の工夫などが取り入れられます。
田原本町教育支援委員会とは
教育委員会が委嘱した委員(医師、学識経験者、校園長会代表等)が、特別な教育ニーズをもつお子さまの適正な就学のための調査や相談、審議を行います。
就学・教育相談の流れ
- 就学相談の申し込み(5月)
- 必要書類の記入(5月)
- 現地観察(6月末〜7月初旬)
- 教育相談(7月下旬〜8月上旬)
- 答申(11月下旬〜12月中旬)
- 県教育委員会への就学先の申請(12月下旬〜1月上旬)
詳しくは「就学先決定までの流れ」をご覧ください。
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
担当課:教育総務課学校教育係
電話:0744-34-2074