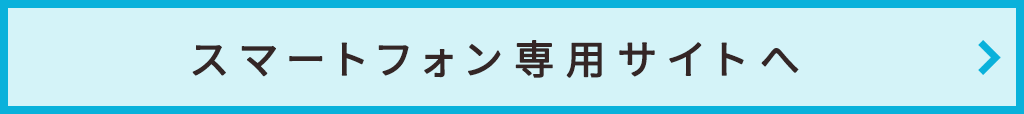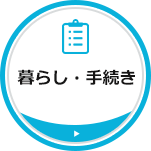成年後見制度について
成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症の人、知的障がいのある人、精神障がいのある人など判断能力が不十分な人の財産管理や身上監護を、代理権や同意権・取消権が付与された成年後見人等が行う仕組みとして、平成12年4月1日からスタートした制度です。
家庭裁判所が成年後見人等を選任する「法定後見」とあらかじめ本人が任意後見人を選ぶ「任意後見」があります。
法定後見制度とは?
「後見」・「保佐」・「補助」の3つに分かれており、本人の判断能力の程度など事情に応じた制度を利用できます。
任意後見制度とは?
本人が十分な判断力があるうちに、将来、判断力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ選んだ任意後見人に生活のことや財産管理に関する事務について契約を結んでおく制度です。
制度の仕組みや内容につきましては下記リンク先をご参照ください。
成年後見制度の市町村長の申し立てについて
成年後見制度を利用したくても、身近に申し立てる親族がいなかったり、申立て経費や後見人の報酬を負担できないなど、さまざまな理由で利用できない人がいます。
このような人々の成年後見制度の利用を公的に支援する制度があります。
市町村長申立権
成年後見制度の利用が必要な状況であるにもかかわらず、本人や家族ともに申立てを行うことが難しい場合など、特に必要があるときは市町村長が申立てすることができます。
後見等開始の審判の申立ての範囲
- 2親等内の親族がいないとき。
- 2親等内の親族の代表者又はそのいずれかの者が文書により、自ら申立てをしないことを町長に申し入れした場合で、該当者の福祉を図るために町長が申立てを行うべきであると判断したとき。(ただし、明らかに文書による申し入れが困難な事由があると認められる場合は、この限りではない。)
- 2親等内の親族があっても虐待や放置等の事実等があり、該当者の福祉を図るために町長が申立てを行うべきであると判断したとき。
- 緊急等の事由により、2親等内の親族の有無の調査を実施することができない場合で、明らかに該当者の福祉を図るために町長が申立てを行うべきであると判断したとき。
- 2親等内の親族がいない場合であっても、3親等又は4親等の親族であって、審査請求する者の存在が明らかな場合は、後見等の審判の申立ては行わないものとする。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
担当:地域包括支援センター
電話:0744-34-2104