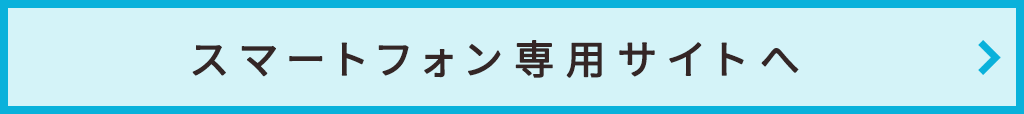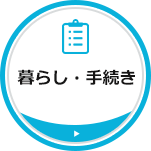避難行動要支援者名簿および個別避難計画におけるQ&A
- ページ内リンク(クリックした先にジャンプします)
1.意向確認
Q:意向確認の対象者はどのようになっていますか?
回答
「田原本町避難行動要支援者避難支援プラン(全体計画)」に基づき、生活基盤が田原本町内の自宅にある者のうち、次の要件のいずれかに該当する方となります。
1.単身世帯又は高齢者のみの世帯に属する高齢者(75歳以上)で、要支援1・2又は要介護1・2の認定を受けている者
2.要介護認定3以上の者
3.障害者手帳1・2級(肢体、視覚、聴覚・言語、内部)を所有する者
4.療育手帳A判定所持者
5.精神障害者保健福祉手帳1級所持者
6. 重症難病患者(特定疾病医療受給者)
7. その他避難支援等関係者が支援の必要を認めた者
※6. 重症難病患者(特定疾病医療受給者)について:県の災害時等在宅難病患者支援事業として、生命維持に関与する医療機器を使用する在宅難病患者 重症難病患者 として、奈良県から町へ情報提供があった者
Q:回答した意向の内容を変更したいがどうすればよいか?
回答
下記リンク先の、『避難行動要支援者名簿情報の外部提供に関する意向確認書 兼 個別避難計画の作成等に関する意向確認書 』を下記問い合わせ先までご提出ください。
https://www.town.tawaramoto.nara.jp/soshki/jumin/tyouju/kenko/kenko/fukushi/kobetsuhinan/18259.html
Q:入退院を繰り返しておりその都度、意向確認書を提出しなければならないのか?
回答
意向確認に同意されていた方で3ヵ月以上の入院・入所が見込まれる場合には町へご連絡ください。なお、退院・退所されご自宅に戻られた場合には町へご連絡いただければ幸いです。
2.避難行動要支援者名簿
Q:名簿にはどのような情報が掲載されますか?
回答
「田原本町避難行動要支援者避難支援プラン(全体計画)」に基づき、以下の項目が記載されております。
1.氏名 2.生年月日 3.性別 4.住所又は居所 5.電話番号 6.避難支援等を必要とする事由 7.個別避難計画の作成の有無
※6.は要介護度およ障がい等級
Q:避難行動要支援者名簿の情報はどこまで共有してよいか?(自治会の方向け)
回答
避難行動要支援者の情報は、平常時から対象者本人から同意を得られている場合は、災害対策基本法第49条の11第2項および田原本町避難行動要支援者避難支援プラン(全体計画)に基づき、民生児童委員、自治会長及びその他地域住民等の日常から避難行動要支援者と関わる者に提供することができるとなっております。
田原本町から、同意者の名簿につきましては、自治会長および民生児童委員の皆様へ提供しております。
自治会長の皆様へ提供された名簿情報は、平常時から災害発生時にスムーズな避難支援等を行えるように、自治会内で判断のうえ、必要最小限の範囲で情報を共有していただくことが可能です。
例えば、自治会内で複数の班がある場合に自治会での判断で、各班長へ担当区域の支援者情報のみを、さらに班長から要支援者の隣人へ名簿情報を提供することは可です。
ただし、同名簿の情報は守秘義務が課されますことから、以下の点にご注意ください。
- 個人情報を適切に管理し、避難支援等に関する目的以外には使用しないでください。
- 名簿の管理は、施錠可能な場所としてください。
- 同意者の名簿は田原本町で1年に1度更新を行うため、毎年春ごろに回収いたします。その都度、複製された名簿および名簿情報を利用して作成された紙媒体を、適切に処分していただく必要がございますので、紙媒体で情報を共有される場合はご注意ください。
Q:避難行動要支援者名簿をどのように活用すればよいか?(自治会の方向け)
回答
町から具体的な活用方法に関する指示はございません。被災時に支援体制を整える際の参考情報にするなど、自治会内で防災に関する取組にご活用ください。
(想定される活用例)
1. 地域の要支援者の状況を把握する。
2. 名簿に掲載されている方について避難支援者を定め、非常時に備える。
3. 自治会内で独自で作成されている要配慮者名簿に、町から提供する避難行動要支援者名簿に記載されている情報を加え独自で別の名簿を作成する。
4. 避難行動要支援者名簿に記載されている方を含め自治会内で避難訓練を行う。
3.個別避難計画 住民向け
Q:町で個別避難計画の作成に関して進めていることは把握しているが、自治会としても早急に計画を作成したいと考えているがどうすればよいか?
回答
町支援による個別避難計画は、優先順位の高い順に関係者の協力を得たうえで順次作成を進めております。町の支援とは別で、自治会等で個別避難計画を作成していただくことは可能ですがその場合、町の個別避難計画の様式を使用していただくことを推奨いたします。なお、自治会独自で作成された個別避難計画書については町へ提出の必要はございません。
https://www.town.tawaramoto.nara.jp/soshki/jumin/tyouju/kenko/kenko/fukushi/kobetsuhinan/18234.html
また、町での個別避難計画の作成方法は、町支援による作成および自己作成に分類されます。町支援による作成の場合、町職員から自治会長へ作成対象者について案内を致します。その際、自治会等で既に独自で個別避難計画書を作成されている場合はその旨をお伝えください。
Q:個別避難計画の情報はどこまで共有してよいか?(自治会の方向け)
回答
個別避難計画の情報は、避難行動要支援者名簿と同様に対象者本人から同意を得られている場合は、災害対策基本法第49条の15第2項および田原本町避難行動要支援者避難支援プラン(全体計画)に基づき、民生児童委員、自治会長及びその他地域住民等の日常から避難行動要支援者と関わる者に提供することができるとなっております。
田原本町から、同意者の個別避難計画につきましては、自治会長および民生児童委員の皆様へ提供しております。
また、個別避難計画の取り扱いに関しても、避難行動要支援者名簿と同様となります。
Q:避難行動要支援者名簿の情報はどこまで共有してよいか?(自治会の方向け)
更新時期は個別避難計画についても、毎年春ごろの更新を予定しております。
4.個別避難計画 委託事業所向け
〇契約に関すること
Q:この事業について、介護支援専門員並びに相談支援専門員に対し委託を行うのは何故か。
回答
個別避難計画について、行政のみ、または自治会等地域の方々のみでの作成は非常に困難であると認識しております。 しかし、要支援者一人一人の状況を把握されている介護支援専門員並びに相談支援専門員の方々にファシリテーターとして計画作成を先導いただき、避難行動要支援者(以下要支援者)の情報、避難支援等関係者(以下自治会等)の助言等を引き出すことで、計画作成を円滑かつ効果的に進行できると認識しております。
Q:一年ごとに契約更新ということは、毎年委託料が発生するのか。また評価等の手間はかかるのに、変更について報酬がないのは何故か。
回答
委託料は、個別避難計画の作成を行い、実施報告書を提出いただくことで、計画作成件数分の請求ができることから、毎年自動的に委託料が発生することはありません。
なお計画の変更に係る委託料は原則ございませんが、「避難支援を行う際に従来の計画内容では支障が生じる事情」が発生し、かつ地域調整会議を開催して計画変更を行う場合は町へご相談ください。
避難支援を行う際に従来の計画内容では支障が生じる事情とは
「家族構成や各連絡先の変更」「避難支援者の変更」「居住地変更あるいは要支援者の著しい状態変化に伴う、避難経路や避難所等での留意事項の変更」といった、情報更新がないと計画の効果的な活用が困難となる内容のことです。
Q:契約を行わない事は可能か。
回答
契約は強制ではありません。契約を行わない場合は個別避難計画の作成に関する事務は発生しません。ただ現状として、地域の方々のみ、もしくは行政のみで計画作成を行うことは非常に困難であり、要支援者一人一人の状況を把握している介護支援専門員並びに相談支援専門員のご協力は非常に重要な事と認識しております。よって契約をされていない場合でも、地域調整会議開催の際は町より参加を依頼させていただきます。
Q:自治会はあくまでも協力で特別責任は負わず、情報共有だけでよいとのことだが、事業所は委託契約となり金銭が発生するため、決まりごとが多くなってくる可能性はあるか。あくまでも地域の避難支援の助けとあるが、認識に齟齬が出るのではないか。
回答
委託契約により介護支援専門員並びに相談支援専門員の方々にかかる責任とは、あくまで個別避難計画の作成に関する事務(仕様書に定める項目)を遂行することであり、計画に関するあらゆることに責任を負うものではありません。
例えば、計画の内容及び実用性は、要支援者を中心に調整会議参加者全員で考えていくものであり、その活用については主に町並びに要支援者や自治会等が災害時等必要に応じて行うものと想定しています。また計画の作成や活用に係る課題等を抽出し改善する役目は町が担うものです。
Q:セルフプランを作成するご本人や、身近である自治会等の方々(調整会議に参加する)に対しては無報酬か。
回答
自治会等の方々への報酬はありません。町からお支払いする金額については、個別避難計画作成の委託料として支払うものであり、地域調整会議の開催調整や既存計画の見直し、実績報告等、仕様に定める項目を実施していただく必要があります。
Q:避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針 平成25 年8 月(令和3 年5 月改定)内閣府(防災担当)(以下、「内閣府の指針」という。) P107 (2)避難支援等関係者等の対応原則 第50条第2項およびその解説より、遺族側から訴訟に至った場合は、委託契約による介護支援専門員並びに相談支援専門員にかかる責任は無いと言い切れるのか。
回答
災害対策基本法第7条第3項に基づき、全ての住民等の防災寄与は努力義務です。また、同法第49条の14~17に規定されている個別避難計画の内容についても、計画に記載された者の避難支援等に係る法的責任及び義務について一切の記述はありません。また、同法第50条第2項に基づき、計画作成を事業所へ委託した場合であっても個別避難計画作成の実施主体は町です。これらのことを踏まえ、災害時における個別避難計画の活用結果について、本契約に基づく業務を誠実かつ適切に履行している場合は、委託先である居宅介護支援事業所等へ法的責任及び義務が発生することはありません(適切な業務の履行の把握については、事業所より提出された各種様式により確認させていただいております)。ただ、これらはあくまでも災害対策基本法上のみのため、民事上までは網羅できていないことがわかりました。そのため、令和7年度の契約書の本文へ、委託先業者への免責事項の項目を追加いたしました。
Q:介護支援専門員および計画相談専門員は、防災に関する専門職でなく避難経路や避難所等での留意事項の変更や、個別避難計画書の作成と言った町民の大切な命を預かる責任のある計画書は防災の専門家に依頼するべきではないか。
回答
介護支援専門員の役割については、「田原本町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例」第3条第2項において、相談支援専門員については、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」第16条において、要介護者等の心身を把握することが義務となっております。また、内閣府の指針P77避難行動要支援者の特性を考慮した計画作成の必要性が明記されており、介護支援専門員および相談支援専門員がその基礎情報を提供する役割を果たすことが妥当であるとされています。避難経路や避難所の選定といった防災に特化した分野については、地域調整会議において参加者全員で協力し合いながら議論と調整を進めることが重要です。その中で、介護支援専門員および相談支援専門員は、避難行動要支援者の心身の状況を最も把握する立場として、地域住民や関係者に必要な情報を提供し、地域の状況に応じた計画作成を円滑に進める役割を担うことが期待されております。計画の変更の基準に関しても、介護支援専門員および相談支援専門員が常に把握されていることから、個別避難計画の変更の判断する立場に適していると考えております。委託先について、地域差はありますが自治会関係者および民生児童委員は定期的に変更となり、心身の把握およびその引き継ぎが難しいことから計画の変更の判断が困難であり、また防災の専門員に関しても介護支援専門員および相談支援専門員と比較して人数が少なく、避難行動要支援者全員の心身の状況を常に把握することが困難なため、当町の方針として介護支援専門員および相談支援専門員へ当委託業務を委託することとなりました。避難経路については、経路上の段差やスロープなど避難するために本人や避難支援者等実施者が必要とする情報が盛り込まれていれば文字でも問題なく、避難所の留意事項についても日常生活から気を付けていることなどを記載することを想定しております。
〇計画対象者に関すること
Q:住民票は田原本町にあるが、居住地が別の市町村にある者は対象となるか。
回答
住民票が田原本町にあっても、恒常的に他市町村にお住まいである場合は、計画作成に同意していても対象外と見なして差し支えありません。
Q:3年という個別避難計画作成期間に対して、もう少し期間を短くしてもよいのではないか。
回答
介護支援専門員並びに相談支援専門員や、自治会等の負担を考慮して、3年間での設定とさせていただいております。期間短縮については、進行状況やそれぞれの立場の負担等を考慮しつつ可能かどうかを町で判断します。
Q:個別避難行動要支援者名簿及び個別避難計画作成の同意についての回収率はどの程度か。また要支援者名簿登録者の中で、個別避難計画作成に同意していない方への対応を今後、協議していく必要があるのではないか。
回答
回収率は約81%(令和6年8月6日)となります。計画に同意されていない方や、意向確認にご回答されていない方については、計画の概要、その有用性等についてご理解を深めていただく必要があると認識しています。自己作成対象の方への案内も併せ、町広報等による周知啓発を行い、計画作成による防災意識の向上を図りたいと存じます。
Q:新規申請者には行政からどのように説明するのか。また、新規申請者で避難計画作成を希望する要介護者は、契約を締結しない事業所に対し通常支援の依頼を受けることはできないか。
回答
個別避難計画の対象者は避難行動要支援者名簿に記載されている方のため、介護保険や各種障害者手帳の新規申請時点で計画等の案内を行う機会は基本的に無いと想定しています。(要介護度、障がい等級等が確定した後、名簿対象者ならば町の名簿に記載されます。その後町より名簿情報提供・計画作成の意向確認を行います)
なお、申請方式による名簿記載については検討中です。
〇計画作成に関すること
Q:地域調整会議より事前に関係者間での話し合いを設定してもらえないか。
回答
基本的には地域調整会議の中で計画内容を協議いただくことを想定しておりますが、必要に応じてご相談いただければと存じます。
Q:田原本町個別避難計画の書式について、計画内容にご本人の承認(同意)欄や、避難支援者の承認(同意)欄、計画作成時の調整会議における自治会等の参画者を記載する欄がないが、問題なしとの認識でよいか。
回答
個別避難計画の作成は、事前に行っている意向確認書において、本人の同意を得た者のみ作成となります。避難支援者の選定について、支援者には、ご家族や隣近所の方、自治会や自主防災組織などが想定されますが、地域調整会議を開催する前に、利用者があらかじめご家族や隣近所の方と調整していただき、そのなかで、支援者がいない場合、自治会や自主防災会、民生委員にお願いすることを想定しています。
支援者の同意については、様式に名前を記載する時点で同意いただいたものとして取り扱う想定をしており、支援者となる方については、自治会や民生委員に情報が提供されることを、事前にご説明いただく必要がありますので、個別避難計画作成に係るチェックリストにてお示しさせていただきます。
調整会議参加者につきまして、様式への記載は不要としておりますが、実績報告時に報告いただくことを想定しています。
Q:計画作成手順について、作成した計画書、報告書を町に提出した後に、対象者や支援者に対し「町も内容に同意したもの」として町から配布するという流れはどうか。
回答
作成された計画の内容は、町も不備等ないか確認を行う想定となります。なお要支援者等への配布は、委託契約の仕様書に定める事務の一つなので、原則介護支援専門員並びに相談支援専門員に行っていただく形となります。
Q:計画作成の説明資料において、【公助】専門的な視点を取り入れ作成とあるが、行政が介入し作成するのか。
回答
個別避難計画については、実施主体が行政であるため「公助」による事業と位置付けております。
また専門的な視点とは、要支援者をとりまく支援者の方々によるもので、例として家族、町、介護支援専門員並びに相談支援専門員、民生委員、自治会、自主防災組織等、さまざまな立場の視点から計画作成を進めるものと認識しております。
Q:施設等入所は自治会へ連絡は可能だが、入院に関してはその度に入退院の連絡を介護支援専門員がしなければならないのか。人によっては短期間で入退院を繰り返す方がいるがどうか。
回答
個別避難計画は要支援者の在宅時の避難支援を主に想定しているため、「要支援者が在宅へ戻る見込みのない入所および入院をされた場合」は、自治会等に情報共有をお願いします。その他の場合(例えば、短期間の入退院等の事情により長期入院等の判断がつかない場合等)は共有困難な状況もあることから、必ずしも共有の必要はございません。
なお、地域調整会議の際に、対象者が入退院を繰り返す状態の場合は、その旨を事前に自治会等に伝えておくことが想定されます。
Q:障がいをお持ちの方が65歳に達し介護保険へ移行される方についてはどう考えているのか。
回答
介護保険に係る避難行動要支援者名簿記載の条件である「一定の介護認定の取得」に従って判断いただくことになります。
例えば、身体障害者手帳1級の方が要介護3以上の認定を受けられた場合、主として要介護3以上の方で避難行動要支援者名簿へ記載されます。その後に計画の変更を行う場合は、介護支援専門員に支援を行っていただくことになると考えられます。
Q:町の地理が分からない。避難経路をあらかじめ自治会訓練や経路等の作成をしてほしい。健常者の移動方法と車椅子等障がいの方が移動できるかどうか。段差や手すり、車椅子通行の道幅、道の舗装の有無等確認の必要性があると思うがどのように考えているか。
回答
ご指摘の通り、個別避難計画の実行性を高めるには、避難ルート作成、居住地域の周辺情報や要支援者の移動方法等の記載が非常に有効です。それらを効果的かつ円滑に計画に落とし込むには、地域調整会議を要支援者本人宅で行い、自治会等と共に実際に居住状況や周辺環境を確認するのが最も有効と考えられます。なお、令和7年度の契約においては周辺の地図情報は町より提供いたします。
Q:地区の中で避難者の援助協力者がどの程度行うことができるかを割り出した上での計画の作成が必要と思われる。平日休日それぞれの日中・夜間によっても違うがどのように考えているか。
回答
ご指摘の通り、要支援者自身やその家族等、また避難支援者や自治会等地域の方々がどこまで対応可能なのか、調整会議の参加者はそれぞれご理解いただく必要があると存じます。この計画は、支援者が如何なる時も支援することを確約するものではないので、あくまで現実的な範囲で作成いただければと存じます。
Q:自治会の方々の避難計画に対する取り組みの特色や考え方などを知りたい。
回答
ご相談に応じ可能な範囲で情報提供させていただきます。ただし、多数ある自治会や自主防災組織等の動向を把握することは困難であり、ご要望にお応えできない場合があることをご了承お願いいたします。
Q:計画作成について前向きに検討したいと考えるが、災害時の支援者になることが他の業務も考え併せたとき、支援者たる責任を果たすことができないと考える。それでも本人から頼まれた場合に、前記理由により断ることは可能か。
回答
災害時の支援において支援者が責任を負うものではありません。また、要支援者の依頼を受けることについても強制ではありません。
なお、家族や地域の方々等を含め、それぞれの立場で現実的にどこまで支援ができるのか、調整会議を通して調整・共有いただければと存じます。
〇計画の変更に関すること
Q:原則1度作成したものは内容の変更がない限り、再提出は不要なのか。例えば介護認定に変更があった時は再提出となるのか。
回答
内容の変更がなければ再提出は必要ありません。計画の変更について「避難支援を行う際に従来の計画内容では支障が生じる事情(Q2参照)」の場合は、変更箇所を修正のうえ再提出をお願いします。それ以外の軽微な内容については、必要に応じて任意で提出いただければと存じます。
Q:要介護1・2の方が、要支援1・2区分に変更した場合、その逆の場合何か対応する必要があるか。また要介護3とそれ以下を行き来するような介護度の方の対応等はどうなるのか。
回答
介護度の変更等により「避難支援を行う際に従来の計画内容では支障が生じる事情(Q2参照)」が発生した場合は、計画の変更が必要になります。なお、要支援1・2はローリスク層の自己作成対象者となり、要介護1以上はハイリスク層で委託の対象となります。要支援者の状況に応じて都度ご相談いただければと存じます。
Q:計画の更新・変更においては状況変化の範囲が大きい、多いと思われる方も比較的いる。その都度介護支援専門員並びに相談支援専門員が何かしら必要に応じてというのは仮に委託料が発生しても難しくできない。不随業務の見直しや詳しい取り決めは必要ではないか。(「依頼があった場合」「必要ならば」などの記述はトラブルのもとになると思われる)
回答
本人の状況変化による計画の変更の必要性は、「避難支援を行う際に従来の計画内容では支障が生じる事情」が発生したかどうかでご判断いただければと存じます。
その他付随業務については、疑義が生じるものはないか契約書・仕様書等可能な限り確認させていただきます。なお本格運用後も疑義・ご指摘等ございましたらご連絡いただければと存じます。
〇計画の自主作成に関すること
Q:要支援者における計画作成を介護支援専門員並びに相談支援専門員に依頼された場合、どう対応すればよいのか。例えば独居の方や判断力が低下している方等が想定されるが、サポートを求められた場合の協力もどこまで、どのように協力するのか不明瞭と思われる。また、計画の自己作成を事業所等が手伝った場合に委託料が発生するのか。
回答
ローリスク層に係る計画作成においては、主として本人もしくは家族等が、町が示す記載例をもとに自主作成いただき、介護支援専門員並びに相談支援専門員は、計画作成を円滑に進めてもらうための助言等を行うものと想定しております。なお自己作成分に対するサポートにより、委託料が発生することはありません。
〇その他
Q:対象者は今後増えていくことと思われ、それは望ましいことだが、7月の説明会からは不安に思うことが沢山ある。事業を継続するには、それぞれの立場で支障が出ない想定でないと疲弊してしまうと思う。例えば、自治会から直接介護支援専門員並びに相談支援専門員に連絡が入ってくるケースが増加しないか。自治会の方々とのつながりは大事ではあるが、その思いを全て受け止めることは精神的負荷になると思う。また、避難訓練は必須業務ではないとのことだが、依頼があった時は協力との記載がある。要支援者や地域の方々の反応を考慮すると断り辛くなる恐れがあると認識している。
回答
ご指摘の通り、介護支援専門員並びに相談支援専門員に一方的に負荷がかかる状況は、不適切かつ事業継続に支障が生じるものと認識しています。
計画作成に係る取り組みや避難訓練等計画の活用面等において、それに関わる方々の役割や考え方等を理解いただき特定の立場のみに負荷が偏らない環境構築を図るため、地域調整会議での発信や情報発信媒体での周知等を通して町より働きかけを継続してまいります。
Q:本来、委託契約により介護支援専門員並びに相談支援専門員等、各法人に正式依頼するのであれば、作成前に個別避難計画作成に関わるマニュアル(作成例や各項目の捉え方等)を提示し作成に取り掛かる方が、より良い田原本町個別避難計画となり、ひいては有事の際、町民の大切な命を助けることができるのではないか。また、個別避難計画作成に関わるマニュアル(作成例や各項目の捉え方等)の発出時期はいつか。
回答
現在居宅介護支援専門員向けのマニュアルを作成いたしました。詳細は下記リンク先をご確認ください。
https://www.town.tawaramoto.nara.jp/soshki/jumin/tyouju/kenko/kenko/fukushi/kobetsuhinan/18236.html
Q:委託契約を行わない場合は、田原本町役場の担当官が田原本町個別避難計画を作成されると思うが、その際は、作成者欄の事業所、連絡先、氏名は田原本町役場の各担当者名で記載されると解釈してよろしいか。
回答
令和6年度の個別避難計画の様式(委託契約の様式第1号)では、委託先の作成者がわかるよう事業所名および担当者の氏名を記載する様式となっておりますが、委託契約を締結していない居宅介護支援事業所の避難行動要支援者の個別避難計画を作成する際は、田原本町と記載するのみで職員氏名は記載いたしません。ただ、災害対策基本法上、計画作成者等へ責任はありませんが、避難行動要支援者等にとって計画の作成者が責任の所在と誤解されてしまう恐れがあること、他の様式で作成者が確認できることを踏まえ、令和7年度より様式第1号の様式から作成者の項目を削除いたしました。
この件に関するお問い合わせ先
長寿介護課 0744-34-2103
健康福祉課 0744-34-2090