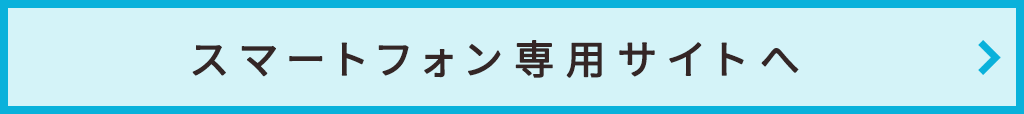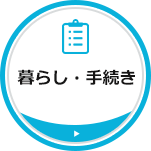4月1日 不登校について
ご提案・ご意見について
いつもお世話になっています。
令和6年度は、小学校の校長先生を始め、やすらぎ教室の先生、県社協の先生、近所のママやお友達、スクールカウンセラーの方々などの温かな支えを受け、子はエネルギーを溜めて学校へ気持ちが向いて、登校するようになってきました。まだまだ支えが必要な部分もありますが、様々な場面で助けて頂き、関わってくださった方々に感謝の気持ちでいっぱいです。
我が子が不登校になると、どうしたら良いかの情報がない状態からスタートし、戸惑いますが、家庭で抱えず、まず親が動いて周囲に発信していくことで絡まっていたものが解けていったように思います。
子どもが不登校になっても一緒に考えてくださる方々の助けを借りながら、前向きに過ごしていくことが大切だと感じました。
先日、木村泰子さんの講演会を聴き、地域で子どもを育てることの大切さを説かれていました。
私自身、子の不登校をきっかけに学び直しをさせてもらっているこの有意義な時間は本当にありがたく、大事なことに気づかせてもらった娘に感謝するとともに、環境や人のせいにしていた自分を恥じて、今後とも私に出来る範囲で、子どもたちを応援していってあげたいです。
「子どもにとっての社会=学校」が、息苦しいものでありませんように、一人ひとりに役割があり、自分の意思が尊重されたり、受け止めてもらえる、そんな空気が学校にありますようにと願っています。
誰かが頑張るのではなく、みんなで学校の空気を作っていけるよう、私自身も大きなことはできませんが、意識していけたらと思います。
話は戻りますが、1年前、家から出ることさえできなくなった子が、きょうだいの学校行事を見届けることができました。子ときょうだいのいる場に私も一緒にいれたことが、本当に嬉しい幸せな貴重な時間となりました。
我が子だけではなく、田原本町内の子どもたちが健やかに育つことを願っています。
子どもまるごとプロジェクトの経過はいかがですか?
メタバースは低年齢の子には不向きかもしれませんね。やすらぎ教室の体制は整えてくださっていますか?学校内の教室以外で安心して学べる居場所を、どの学校でも考えてくださっていますか?
子どもが安心して学べる環境を、知恵を出し合いながら考えていけたらいいですね。
我が子の場合、家から出られなくなったとき、その状況に「なりたくてなっているのではない」と言っていました。学校に行くことが全てではないですが、子の通う校長先生や県社協の学習支援の先生がしてくださったように、一対一の関係の中で、いつでもあなたが好きで、あなたの居場所はあるんだよというメッセージを根気強く送り続けてくださったこと、本当に有り難かったです。
長文になりましたが、お世話になっている方々へのお礼と、不登校の子どものいる家庭からの声、教育総務課の方々へのご意見として投稿させて頂きました。
困っている子は不登校の子だけではないですが、光の当たりにくい場所にいる子どもたちにも心を配り、今後とも子どもたちが安心して通える学校づくりを、一緒に考えて頂けますようお願い致します。
本年度も どうぞ よろしくお願いします。
田原本町の回答
この度は貴重なご意見をいただきありがとうございます。
ご経験を通して多くのことを考え、学び取り、行動してこられた様子が文面から伝わってきます。新年度が始まり期待と不安がたくさんあるこの時期に、ご意見を共有させていただくことで励まされる方もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。
令和6年度にスタートしました「こどもまるごとプロジェクト」につきましては、令和7年度より、「こどもまるごとプロジェクト2.0」として教育環境の確保や子育て支援の充実に努めています。その一環として、学校や家庭以外にもこどもたちが安心して過ごせる場が町内各所に生まれることを目指し、こどもたちの居場所として、食事を提供する場所づくりやつながりの場所づくりなどの取り組みを立ちあげようとする団体のスタートアップ支援を行ってまいります。
当町においても不登校のこどもたちの数が増えていますが、令和6年度は、やすらぎ指導員の配置によるやすらぎ教室の開室日の増や、小学校へのいじめ・不登校対策指導員、田原本中学校の校内サポートルームの人的配置などに取り組んでまいりました。これらの取組みを通して、再び学校に通い始めたお子さんもおられます。令和7年度はやすらぎ指導員を増員し、やすらぎ教室の開催日を週3日に増やす予定をしております。また、こども家庭センターへの臨床心理士の配置により教育と福祉の連携を進め、支援体制の拡充を図ってまいります。
教育委員会といたしましても、こどもたちが安心して通える学校、今日も行きたいと思える学校づくりを推進するとともに、心を許して自分の気持ちを話したり、ありのままの自分を認めたりできる心の居場所づくりやネットワークづくりにも継続して取り組んでまいります。
それには、保護者の皆様や地域の方々とのつながりが不可欠です。こどもたちの成長と幸せを見守る応援団の一員として、今後ともご意見をお聞かせいただけますと幸いです。田原本町の教育にご理解とご協力をどうぞよろしくお願いいたします。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
担当課:教育総務課学校教育係
電話:0744-34-2074