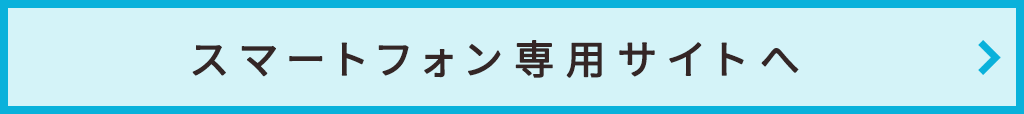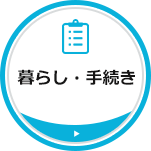第2回田原本町行政改革懇話会会議録(要旨)
2007年10月11日更新
開催日時
平成17年11月22日(火曜日) 午前9時〜午前11時40分
開催場所
田原本町役場301・302会議室
出席者
- 出席委員
浅井宗一委員、今井俊行委員、大倉康至委員、川崎祥記委員、永井満智男委員、楢宏委員、松原綾乃委員、松本久子委員、村尾義文委員、森田昌宏委員、八幡満久委員、育田幸伸委員
欠席委員:森口淳委員 - 田原本町行政改革推進本部員
総務部長、総務部参事、住民福祉部長、生活環境部長、産業建設部長、教育次長、水道部長 - 事務局
総務課長、総務課長補佐、企画財政課長補佐
議事
- 第1回懇話会会議録の承認について
- 田原本町行政改革大綱(案)について
配布資料
- 第4次田原本町行政改革大綱(案)
- 行政改革実施項目
- 平成17年度当初予算歳入歳出・性質別歳出の状況
- 公の施設の管理委託の状況
- 町職員の給与などの状況
- 各種団体等補助金交付調べ
- 施設使用料減免件数の状況
議事概要
1.第1回懇話会会議録の承認について
第1回懇話会会議録について、各委員の同意を得て第1回懇話会会議録が原案どおり承認される。
2.第4次田原本町行政改革大綱(案)について
会長
始めに、第4次田原本町行政改革大綱(案)について、事務局から説明して頂きますが、本日は、皆様のお手元にございます大綱の行政改革の主要事項、地方公共団体おける行政の担うべき役割の重点化、行政ニーズの迅速かつ的確な対応、定員管理及び給与の適正化等、この3項目につきましてまず討議していただきたいと思いますので事務局から説明をよろしくお願いします。
事務局
第4次田原本町行政改革大綱(案)、資料2の行政改革実施項目に基づき説明します。まず、大綱案の第1行政改革の基本的考え方、1行政改革の必要性について説明。次に、第2行政改革の主要事項、1地方公共団体における行政の担うべき役割の重点化(1)民間委託の推進(指定管理者制度の活用)について説明。具体的には資料2の1ページ1.外国青年招致事業、2.ゴミ収集業務の民間委託の推進を挙げております。指定管理者制度の活用といたしまして、2ページの1.宮古保育園と2.福祉作業所の施設は一般の公の施設とは少し性格が違います、指定管理者制度になじむか検討中でございますが、既に、業務につきましては民間に委託しています。3.ふれあいセンター、4.ふれあい農園、5.笠縫駅前自転車駐車場につきましては、指定管理者制度を導入する方向で検討しています。これ以外に町が保有している公の施設について、資料4で一覧表を参考として付けていますので、今後のご意見を伺う材料にして頂ければと思います。
続きまして、先程の、大綱案に戻って頂きまして(2)地方公営企業の経営健全化について説明。これについて3ページに具体的に項目を挙げています。1.量水器の設置これは公民館等公の施設についての量水器の設置でございます。それから2.水道料金については、水道料金の見直しを挙げています。大綱案に戻って頂いて、(3)地域協働の推進について説明。
続きまして、2行政ニーズへの迅速かつ的確な対応(1)組織の機構の見直しについて説明。これについては資料2の4ページに具体的に項目を挙げております1.組織整備の推進、2.グループ制の導入、3.高齢者の保健医療の向上及び福祉の増進等です。大綱案に戻って頂きまして(2)事務事業の見直しについて説明。これにつきましては、資料の5ページから7ページに渡っております。各種いろいろな助成事業とか施策があるわけでございますその辺の改正内容を載せております。数が多いですので見ておいて頂ければと思います。
次に大綱案に戻って頂いて、3定員管理及び給与の適正化等(1)定員管理の適正化、(2)給与の適正化について説明。これにつきましては、資料5今年の2月に町の広報紙で既に一般に公表したもので参考にして頂きたいと思います。以上で会長からご指摘のありました3番まで説明させて頂きました。
会長
ありがとうございました。事務局から説明ございましたが、これから懇談に入りたいと思います。まず、1番の地方公共団体における行政の担うべき役割の重点化これの(1)、(2)、(3)について、皆様からご意見を賜りたいですけれども、指定管理者制度と申しましても皆様方なじみがないと思いますので事務局から説明をお願いします。
事務局
平成15年の地方自治法の改正によりまして、制度が取り入れられたわけでございます。今までも、業務の一部でありますとか、大半を一般事業者の方に業務委任している事実がございます。この指定管理者制度になりますと公の施設の管理運営すべてを、指定した民間でありますとか、NPO、公共的団体等、指定した管理者の方にほぼ全ての運営をお任せするというような制度でございます。法の施行日が来年18年の9月からとなっております。そういうことで、町の公の施設個々この制度を取り入れるか現在、検討中でございます。わからない点ありましたら補足します以上です。
会長
説明ありがとうございました。指定管理者制度により、できるだけ民間にお願いするとなりましたら、今まで5時15分で終わっていたのが、民間であれば9時まで延長して自分ところの利便性を図る、そして経費の節減ということにも繋がることで、民間に担うべき事は民間にお願いするということを政府の骨子の方針のなかでそれが示され改正されたという趣旨でございます。県においても先日、新聞に載っておりましたように、この制度を取り入れ、また各自治体においても、そういう方向に進んでいるということでございます。それでは、今申し上げました1番の地方公共団体における行政の担うべき役割の重点化ということにつきまして委員の方々、何かご協議ご審議ございましたらご発言よろしくお願いします。
会長
ゴミ収集業務の民間委託の推進で一部されているということですが、どの部分がされていますか。
部長
今後、一部委託を考えていきたいと思っています、これにつきましては、廃棄物処理法によりまして、市町村の地域内におきます一般廃棄物の収集、運搬及び処分につきましては市町村の固有事務となっています。本町につきましては、家庭や事業系ゴミ、粗大ゴミなどは直営で行っています。しかし、し尿のくみ取りと浄化槽の処理につきましては、本町では昭和49年から、おおやまと環境整美事業協同組合に許可しています。そういったことから、民間業者に依頼しているものです。民間業者は、設備費や人件費などに投資を図っておられるわけでございます。一方、快適な生活及び公衆衛生の向上を目指し、昭和55年度から公共下水道整備事業に着手していることから、平成16年度では、約60.5%の供用開始の普及率になっているところです。したがって町の固有事務とされる「し尿処理」を担ってきた業者は、業務量の減少により経営基盤の根底が揺らいでいるところでございます。国におきましても廃棄物の適正な処理の見地から、昭和50年に「下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法」により、処理業者の受ける影響の緩和と合わせて、経営の近代化及び規模の適正化に関する事項又、事務の縮小、廃止を余儀なくされることから救済措置等を定めた法律が施行されました。また、昭和60年には、従来の生し尿だけが対象であったものが浄化槽汚泥処理、海洋投棄も含むことになり、さらに資金上の措置も可能な改正がなされました。
現在2台の車両により業務を致しておりますが、平成21年頃には、本町の下水道の普及によりまして1台が減少になると予想されます。従いまして、代替事業等を検討していく必要がございまして、そのために、ゴミ収集の一部の委託を考えているものでございます。
会長
特法のことですね。
部長
はい。
会長
し尿処理の業務が、縮小になることからゴミの収集について一部を委託するということですね。
部長
はい。
会長
全部委託というのは考えておられないですか。
部長
現在、職員により直営で行っています。定年退職者があっても補充しておりません。徐々にそういう形をとっていく必要があると思いますが、当面は一部委託を行ったらと検討しているところです。
委員
委託というのは、委託したら委託料支払いますね、委託したら安くなるから委託するということですか。
部長
この場合は、そういう問題もございます。直営でするとなれば職員も採用しなければなりません。民間委託すれば人員も3名から2名体制にするなどして経費の節減も考えられる。一方、合特法の関係でありますが、代替え業務を与えないで、他の方法で解決していくことも可能であります。
委員
どれくらい安くなりますか。
部長
ちょっとそこまではわかりません。
会長
他にございませんか。
委員
資料4を見ますと、公の施設が直営でズラッと並んでますけど、今後更に指定管理者制度を広げていく予定はありますか。
事務局
当面は、先程説明しました、ふれあいセンター、ふれあい農園、笠縫駅前自転車駐車場をできるだけ早い時期に指定管理者制度にしていきたい。その他の施設についても、今後それぞれ検討を加えまして必要性が認められれば指定管理者制度を取り入れたいと思います。
委員
これから広げていこうとすることが適切かどうかの問題とか、委託する先の業績、経費節減の度合いがどの程度進むのか、指定管理者制度の適用対象施設なのかというあたりを定期的に検証していく必要があると思いますので、だらだらと役場内部で事業を進めるのでなく、たまたま事務事業の見直しのところで、行政評価システムの導入と書いておられますので、できれば第3者の委員により、そういう行政評価システムについての見直しをするような、ある程度専門性をもった方を委員にしてその中で評価システムの委員会を作った中で、委託と直営にしたときとの損得を毎年、定期的に見直して進めていく形のシステムを作って頂いたほうが実際に経費が削減されているかどうかわかるような形、節目節目ができていくのではないかと思います。
事務局
いろんな会議の中で議題にしようと思えばできるでしょうが、指定管理者を取り入れる場合の指定管理者選定委員会を近々設置したいと思っています。その選定委員会のなかでもその指定管理者を置く施設ももちろんでございますが、それ以外の直営になっております施設についても議論をしていきたいと思います。
委員
この指定管理者制度については、いろんな地方自治体のほうで努力されており、新聞紙上で見てみますと芦屋市なんかは、箱物については全件指定管理者制度に移行すると載っていました。指定管理者制度を行う場合に、対象となる全てに対して指定管理者制度に移行できるかどうかということを検討すべきだろうと思います。先程もお話がありましたように、実際に一つ一つについて、どれだけの人件費だとか物件費とかどれだけの経費がかかっていてそれに対して指定管理者制度に移行することによってどういうふうにそれが改善できるかそういうあたりを一つ一つ検証する必要があると思います。
委員
指定管理者制度になった場合の財源は全て民間に委ねられるのですか。財源は、町の方から支出されるのですか。
事務局
施設ごとに対応が分かれます。公の施設が、使用料や料金を徴収している場合と全く使用料等を徴収していない施設あります。たとえば、図書館なら使用料を取っていませんし、笠縫駅前の自転車駐車場は料金を取っています。料金を取っている施設を指定管理者に委託した場合は、ひとつはその料金を指定管理者の収入にし、その収入だけでやっていけるかどうか客観的にみてどうしてもやっていけないとなれば委託料を上乗せする場合もあります。使用料だけで賄えるだろうと判断できれば、その使用料の範囲内で指定管理者に任せます。また、指定管理者が企業努力で使用料収入が増えるような施策、アイデアを出して頂ければそれはそれで結構かと思います。それから先は、使用料あるいは財政運営上の金額的な問題プラス住民に対するサービスが、今まで以上に向上するかどうかも判断材料になるかと思います。たとえば、同じ委託料を払っていてもサービスが向上すればいいことであります。サービスが同じであれば経費が安くなればいいだろうし、いろんなことが考えられます。使用料を取ってない施設であれば委託料で指定管理者にお願いする訳です。委託料が行政側から見て直営で行っている経費よりも安くすませればいいことであり、ケースバイケースでいろんな対応ができるかと思います。
委員
役場の関係される方に教えて頂きたいですけど、ここ数日テレビ、新聞等で大にぎわいのマンションの設計業者が手抜きをした建築確認申請を検査する側もいい加減にチェックしたから大変な問題になっている。この提出された建築確認申請をチェックする民間の業者は国から委託されているらしいですね。これも先程説明のあった指定管理者制度になるのですか。
事務局
行政の管轄で町の場合、職員に建築士を置いておりませんので、県の桜井土木事務所に建築確認をする確認業務がございます。県が対応する中で建築確認の事務の一部を民間業者にというのは事務処理のスピードアップを図るためにされているということです、県の事務なので詳しい内容についてはわかりません。
委員
私、どうしてお尋ねするのかと申しますと、今言ったことが指定管理者制度にあたるのであれば、マンションの住民との補償になれば一般の民間業者で補償できるわけがないから、この指定管理者制度を取り入れないで国が、直営でやっていたら補償にも応えられる。そこで申し上げたいのは、民間でできるものは民間でという趣旨はわかりますが、何でもかんでも民間に委託していいものか慎重に考えて頂きたい。
委員
今の話に関連してですが、公の施設は町民の方々が日常生活の中で使用される施設ですから、経費の削減とか管理の育成について議論している訳ですから、町民の方へのサービス機能が低下になるようなことは当然避けるべき事だし、むしろ民間の方の熱意でよりよいサービスをしてもらうような指定管理者を選定して活用していくようにしなくてはなりません。経費の削減とか費用対効果を審議する選定委員会あるいは、新しく指定管理者を設けるかどうかを選定する委員会を設けられるそうですがシステムとしては、指定管理者に委託した事業所について住民の方から苦情とか出てくるときは漏らさず内容を委員会に挙げさせ更に、指定管理者で委託を続けるべきか、どう事業内容を改善させるか、そういうことをみなさん方の意見また住民の評価をくみ上げられるようなシステムを作ったらよいと感じました。
会長
それから他の市町村では学校給食なども民間委託されているようですが田原本町のほうでは今のところ考えておられないのですか。
部長
直営でやっておりますので、民間委託という考えは持っておりません。
会長
それは費用対効果も考えてそちらの方がいいと言うことですか。
部長
現在、直営と言う形がベストとは申しませんが、より安心、安全を考えて今のところ直営でやっておりますので、今後ご指摘のように考え方としては持っていくべきと思いますが、現状としては直営でと思っております。
会長
確かに安全性もありますし利便性、費用対効果いろいろそういう面で町のほうも選定委員会なども設置されて一つ一つの施設について指定管理者制度についてご検討して頂ければと思います。資料に書いてないですけれども、田原本町生涯学習センターですが昨年完成されましたけど指定管理の導入がどうかとご検討頂ければと思います。年間で施設管理に約1億近くかかり、人件費は職員10数名おられますので合わせて1億6,7千万円いると思います。これを民間委託され指定管理者を導入されれば3分の1ぐらいの急テンポがでてくる又、利便性についても休みの日の有効利用をもっと色々な事考えられます。民間の知恵を借りれば有効な手段ではないかと私は考えますので、これらの点も選定委員会のなかでご検討願えればと思います。後ほど出てきます定員の削減にも繋がってくる訳でございます。私としては非常に大事なことではないかとその点もご検討願えればと思います。
会長
他に何かご意見ございませんか。
委員
だいたい意見でつくしたかと思うのですが、委託か直営かという究極の選択かなと思います。また、この中間もあり得る話なのかな。たとえば、直営でやらざるを得ないと致しましても、たとえば、職員でやるかどうか嘱託の職員でやるか民間ではパートさんでやるとかこういうことをやることによって、委託か直営かと言うことの中間的なそういう考え方の発想もやって頂けるのかなと思います。民間委託の推進のところで行政にしかできない事務事業がございますけど、行政でしかできないのか行政の職員でしかできないか何故そうなのかということを考えますとコストの安さといいますか、それをどう活用していくのかと両極端にわけにくい業務非常に多いかと思いますそういうところでお考え頂くのも一案かなと思います。
事務局
今のご質問ですが、地方自治法の法律の硬いところの表現でございます。指定管理者に委託するか直営でするか二者選択の言葉のようになっております。今言って頂いた意見につきましては直営に入ってしまうわけです。直営でやりながらその中の業務の一部たとえば、公園管理の中の草刈りをシルバー人材センターにお願いするとかアルバイトにお願いするとか、あるいは役場の清掃業務を委託するとか現時点でもいろいろ実施しておりますが、それは委託か直営かとなれば直営ということになります。
委員
わかりました。
会長
1のところ他にございますか。
委員
1の行政改革の必要性というところから第2行政改革の主要項目に入っていくわけでございますが第2以降については、経費節減とか人員の削減とかについて、今このようになっていると言うことでございまして、行政改革の必要性のところにですね非常に財政状況が厳しいとかの言葉をそういうふうなことを考えて頂ければと、文中の「少子高齢化の進行………行財政基盤の強化を求められています。」この文章を見ておりますと、これから要請されますニーズというのは多様化されてくるまた、非常に高度化になってくると、もっと人や物が必要であるかのような印象与えかねないと思うわけです。第2以降を見ますと人を削減するとか経費を削減する項目になってますから、おそらく大綱というのはオープンになるわけですから、町として行政改革の必要性をどのように考えているのかと言うことを住民に訴える非常に重要な部分でありますから、現状が三位一体の改革により交付税が非常に少なくなってくるということで、従来のような行政運営ができなくなったような当たりの現状を住民に認識してもらうような文言にしたほうが納得性があるのではないかと思います。
会長
確かに委員の言われたとおりと思いますので、その点について検討よろしくお願いします。この項目これでよろしいですか。この中にも書いておりますように「公共施設の管理運営について積極的に民間活力を導入することで、住民のサービスの向上と経費の削減を図る」とされておりますので委員会を導入して一つ一つしっかりと必要かどうか検討するということでよろしくお願いします。
会長
次の2の地方公営企業の経営の健全化についてはどうでございますか。ここでは、水道料金を値上げすると言うようなことが載っておりますけれども、赤字はどれぐらいですか。
部長
平成16年度末で累積欠損金1,445万7千円を生じています。
会長
この件につきましては、議会にまわされて改定についての検討されているわけですね。
部長
現在、議会に審議してもらっていない状況でございます。実情は決算のとき、報告しておりますので認識はしていただいていると思います。まだ、話はしていません。
会長
他にございませんか。
委員
町の水道料金は他の市町村と比べてどうですか。
部長
本町の水道料金は、1世帯1ヶ月平均使用水量27立方になります。金額にしますと3,890円で、それは県下29市町村の中では安い方から4番目になります。
委員
水道の累積赤字が1,400万とかいうお話ですが、民間でいう企業努力、どうしたら赤字というか経営又は独立採算性がとれるか水道の部門で考えておられて、要するに業者に委託して老朽化している水道管のふせ替えとかそのときの入札とか経費を削減していく方法とか考え、それを検討されて水道料金を上げずに今の時代ですから県内では4番目に安いかどうかわかりませんけど経営努力というか企業努力を考えておられるのかどうか、水道は水道で独立採算性ですから鋭意努力して頂けたらと私は思うのですけども、ただ赤字がでるから何で赤字がでるかという根元を解消しなくてはいけないと思います、赤字だから上げるという単純な問題ではないと思います。
部長
ただ単に料金改正それで収支あわそうという考えではございません。田原本町西竹田の上水道は昭和55年より稼働しております。施設も年数が過ぎ老朽化が進んでおります。そういう関係もありまして、東の方で新配水場の建設、そして西竹田の浄水場では維持補修又は施設の改修等をおこなってきたために、平成16年度末で赤字が生じた訳でございます。歳出の削減につきましては、水質そして施設の維持管理、動力費等の必要経費で平成16年度決算の中では約97%を占めているような状況でございます。その中で総配水量が減少しており、今後、水需要が増えるかどうか。また、内容を精査し削減するところはないか、よく検討したいと考えています。
会長
よそで聞きますと、企業によっては、企業努力され井戸を掘られているところもあり、そのために水道の需要が伸びないし水道料金の収入も減る、特に大きな企業が、そういうことです。料金を上げれば結局、民間でも努力され井戸を掘られるところありますので充分に考えて頂きまして経営の健全化と、どうすれば経費が節減できるかと考え合わせながらやって頂けたらと思います。
委員
料金改正を実施され上げることによって経営も充分やっていけること分かります。しかし、介護保険により年金受給者は保険料を引かれていきます、はじめの約束よりどんどん高くなるに従いまた、国民健康保険料も今年から上がりいろんな意見を聞いております。その中でいろいろと水道料金上がり何上がりということを考えたら、果たして住民の生活が困る人が増えてくるのじゃないかとそういうことを一応考慮にいれて、今後検討して頂きたいと思います。
会長
他にございませんか。それでは3の地域協働の推進という項目に入りたいと思います。このことについては、そう問題がないと思うわけでございますが何かご意見ございますか。
委員
「住民の声を施策に反映するように活動主体との積極的な連携・協力を図る」と非常にありがたいこと書いて頂いておりますが、自治連合会で自主防災組織の結成しているところかなり増えてきております、町の財政の大変なときにとは思いますが、補助金の制度化をお願いしております。まだ回答頂いておりませんので、今、こういう文章も書いておりますので書くだけではいけませんので実際に、98自治会のほとんどの方の要望ですから善処して頂けたらと思いますよろしくお願いします。
会長
それでは1についてはよろしいでしょうか。それでは5分ほど休憩させて頂いて10分から再開しますのでよろしくお願いします。
会長
それでは、再開致します。
部長
先程の説明の中で平成16年度末の累積欠損金1,445万7千円とご報告致しました。平成17年度末の累積欠損金は8,144万4千円ぐらいになる見込みです。それを付け加えさせて頂きたいと思います。
会長
累計で8,144万4千円ですか。
部長
はい、累計で8,144万4千円です。
会長
毎年、赤字が続いていく訳ですか。
部長
はい、減価償却費等が平成22年頃まで相当伸びてくる状況ですので、現行の料金でいきますと毎年度、赤字が続く見込みです。
会長
わかりました。引き続いて、2番の行政ニーズへの迅速かつ的確な対応の中の(1)組織の機構の見直しそれから(2)事務事業の見直しということで行政改革実施項目の中では、4ページの組織整備の推進、グループ制の導入、高齢者の保健医療の向上及び福祉の増進、それから次の事務事業の見直しとして、町県民税の6月賦課、母子家庭支援関連事業の見直し、人間、脳ドッグ助成制度、学童保育の保育時間延長及び有料化、敬老事業の見なおし、土地利用の円滑化、行政評価システムの導入等々書いてございますけれども、これらについて何かございますか。
委員
行政評価システムというのは、あちこちの公共団体、県も含め推進されてますが町としては、どういうふうなことを考えておられるのですか。
部長
お手元の資料に若干内容を書いております。行政の活動を一定の評価指標に基づき、有効性・妥当性・効率性等について評価するシステムというような内容を書いております。具体的には、行政評価につきましては施策に対して行う評価、これは行政の基本的な方針を施策と申します、それと政策を実現する方法としまして施策を実現するため具体化するのが事務事業でございます。今回この事務事業について、行政評価を取り入れたいと考えております。限られた財源でございまして効率的、効果的な配分が必要でございます。こう言ったことから事務の効率化と投資的効果またコスト削減、行政ニーズの対応等の点に着目を致しまして事務事業評価システムを行いたい。評価システムについて、具体的には煮詰まっていませんが、数値化できるものは数値化したいと思っております。いわゆるマニュアル化を図り定期的に見直しを図っていきたい。すでに役割を終わっているもの、効果のあがってないもの等々について、廃止、見直しを行っていきたい。このような形でシステム化を図りたいと考えています。
会長
他ございませんか。
委員
各課各部署に置いて細かく一律に見直しをされている様子は、この表とかでよくわかりますが、しかし、福祉と教育については最後のほうに回して頂けたらと思います。一般会計歳出について、グラフにして頂いたのですけどバランスが、真のバランスになっているのかどうか私にはわかりません。本当に抜本的に改革されるべきものは何かということを一体どこがチェックするのか、今、行政評価システムの話がでましたのでチェックする立場とか、そういう人の意見が尊重されるように願っています。
部長
資料3でございます、17年度の予算をグラフにしたものです。1ページ目は17年度の歳入の構成割合を数値とグラフで表しています。町税が37%、地方交付税が26%これで半分以上、これが町の収入で、後はそれぞれ事業を行いましたら補助金などの収入で94億1千万円の当初予算でございます。2枚目は、民生費から予備費までの構成割合と金額をグラフにあらわしたものです。先程の教育に係るものは、94億1千万円の内17.4%民生費が22%でございます。公債費15.5%と年々増加しております。これは、地方債の返済に係るものでございます。どの程度の構成割合が、適切なのか市町村の事業の実施によりまして異なってきます。昨年の教育費は、北小の校舎改築や生涯学習センター工事がございましたので、かなりのウエイトを占めておりました。このように94億1千万円が、どのような配分になったかを結果的にみたものでございますので、先に枠を取りまして数値をつけたものではございません。たまたま17年度は、このようなふうになったとご理解していただきたいと思います。3ページ目は、94億1千万円の性質別歳出の状況でございます。上から3段目の項目につきましては、前回の財政状況の時に説明を致しましたが人件費、扶助費、公債費の義務的経費の割合でございます。合計で49.1%約半分がこれらの経費で消えています。次に建設事業費は、道路、学校等の公共施設の新増設の投資的経費でございまして8億8千万円でございます。次に物件費は、人件費、維持補修費、扶助費、補助費以外の経費でございます賃金、旅費、交際費、需用費そのような経費でございます。物件費は、14億345万1千円でございます。前年に比べて7千万円程度の減少でございます。これは、耐震診断とか北小の仮校舎用プレハブの借料等が減少したためです。次に、維持補修費ですが、これは公共施設の修理とか維持補修に係るものであります。次に、補助費等で10億5,731万2千円で11.2%になっております。これは、前年より3,700万円ほど増えています。国保病院組合の負担金や山辺広域行政事務組合の負担金などの関係で増加しております。あと、積立金や繰出金この繰出金は、国民健康保険特別会計また老人保健特別会計、公共下水道事業特別会計、介護保険の特別会計へ一般会計から繰り出している額13億6,246万6千円で14.5%でございます。以上のような94億1千万円の構成割合ということでございます。
会長
あと何かご意見ございますか。
委員
歳入に見合った歳出を考えたらいいと、そして、今後、収入がどんどん減っていくとそして出るのが増えたら出と入りとが合わないということで、先程から聞いてたんですけど田原本町の借金が290億もあるのですね。そして、年々14億5,700万も払っていかなくてはならないと、これを今、細かいこと審議されてますけど、町として、今後ある程度の方向性を決めなければならないと思うのですけど、どのように考えておられるか、一番大きな問題と思うのです、だいたいのこと聞かせて頂いてそして、この補助金とか繰出金ですかそれらを踏まえてどのように町として思っておられるのか教えて頂きたい。
部長
具体的な数値は、現段階では未確定である。交付税、町税が歳入の大半を占めている。今後、増加することはなく、減っていくことは考えられる。こういった中、公債費(返済)が増えてくる。歳入が減って、歳出が増えていくことから、経常的な経費の削減を図っていかなければならない。入るを量りて、出ずるを為す。こういったこともお示しをしている行政改革の一つであります。
委員
見通しが立たないとのことであるが、経費をできる限り抑えてもらって、そして、値上げするものは一時的でもいたしかたないということを踏まえ、今後、皆さんと方針を立てていく必要があると思っています。
委員
田原本町ができて、数十年、色々なしがらみの中で、行政の範疇が増してきている気もする。はたして、今の行政が住民から見て公平なのかという尺度に照らして、公平性に欠けているものは、見直していく必要がある。ゼロベースの予算の発想で、一旦白紙に戻して、根気よく縮小方向に持っていかなければ、出るものを抑えることは難しくなる。行政側では、言いにくい部分もあるだろうから、この懇話会である程度思い切った、課題を出していくことが必要である。
会長
補助金であれば以前からの経緯もあり、また、使用料は、低く抑えられている状況である。行政側では、言いにくい部分もあるだろうから、この懇話会で、白紙に戻して、住民の目から見て負担を求めるところには、求めていくなどの議論をすすめていき、また、住民の方にも財政的に厳しいことを認識していただき、田原本町がどうあるべきか考えていく必要があると思う。
委員
行政評価システムは、事務事業についての評価ということであるが、県では、公共事業の評価システムにおいて、委員会の設置も含めて、検討されている。県とは、行政規模等が違うが、行政システムでは、数値化をされると思う。将来的には、専門的かつ行政改革の知識をもった外部の委員も入れた常設の委員会を設けられることを希望します。
会長
今のところそういう考えはありますか。
部長
18年度からシステムづくりをしていきたい。委員のご意見を参考にシステムづくりを検討して参りたい。
委員
前回には、民間の企業では、破綻の状況であるとのご意見もあった。どうしたら良いのか素人ではわかりづらい。いまの関連で、専門的な人を入れて検討してはと思います。
会長
行政ニーズへの迅速かつ的確な対応につきまして、他にご意見ございませんか。それでは、この項目の、事務事業の見直し、組織の機構の改革を通じて、ご努力をお願いしたい。
続きまして、定員管理及び給与の適正化等定員管理の適正化及び給与の適正化の項目について移ります。資料は8から11ページになります。
会長
職員定数の削減15%の目標が示されているが、きっちりと実施していくのですか。
事務局
この目標で進めていきたいと考えています。現に近年におきましては、退職者の補充をおこなっておらず、削減の方向で進んでいます。
会長
資料の中にある、人口一人あたりの義務的経費の状況では、田原本町は、非常に少ない訳ですね。
事務局
一概には言えませんが、施設を多く持っているところは多くなる要因です。
会長
定数の削減15%、何年かけて、何年度迄にという目標はあるのですか。
事務局
概ね5年間で280人程度にしたいということです。条例上の職員定数は、331人に対しまして、現在の職員数は301人であります。
会長
5年間で、約20人減ということですね。
委員
定員管理で、15%削減、280人程度を目標とすることであるが、これからの新たな行政課題、多様化する住民ニーズへの迅速な対応の部分では、新しい人数も必要となる。事務事業の見直しで、どのような形で職員を削減できるか、各部門毎で削減目標があるのか、あるいは今の部室の在り方、縦割り的なところを、グループ制という話もあるが、それにより削減可能という考えがあると思われる。
数値目標も確かに良いが、企業の場合、最近、就業規則上において降格制度もある。行政の場合も降格的な施策等で、全体に職員のレベルアップが図られるのではないか。人数だけ目標に達してもよろしくないのでは。良い職員が多く残って、活力ある仕事をする組織がよいのではないかという気がします。
会長
降格制度は、ありますね。
事務局
制度として、分限処分等はありますが、現実には、事例はありません。
今のお話は人事の評価と関連がありますが、現時点では未確定な部分もありますが、来年度以降、国の方からも昇給にまた勤勉手当の支給に関しても、人事評価を取り入れるという動きになっています。資料10ページの9に示しておりますが、職務評価を行って、反映させるという動きになっております。
委員
弥生の里ホールには、町の職員で音楽用の反響板の技術者がいないので、民間の業者に依頼し、一人2万円で2名分4万円の実費分を負担した。町の職員で行えばその実費分は町の収入になり、収入増につながることから町の職員が技術等を習得されればどうかと思います。
部長
ご指摘の技術的な専門職員はおりません。外部から専門の業者を入れております。職員の中でも技術的な研修を受け、職員でできる範囲のものは行うなど考えて行きたいが、ただ、研修には長期間を要しますので、将来的に検討して参りたい。具体的なものは現時点ではありません。
委員
定員管理の適正化の件で、民間企業の例をご参考に紹介する。こういう風にして下さいということではない。
各部署毎の適正人員をどのような基準で配置されているのか。私どもは、事務量調査を実施して各店の人員の傾斜配置をしている。繁忙時、ピーク時の人員なのか、平均的な日々の配置なのか、あるいは、余力をもったものになっているのか、そういうところを整理いただけたらなと思う。それで、足りない所は嘱託職員、パートなどを有効活用されればよいのでは。私どもでは、今までは、パート職員は業務の制約があったが、今では、社会的にも有効活用されている。
もう一点は、給与の削減、各種手当ての見直しについて考えておられるが、非常に良いことである。全体としては、総額の人件費の削減は良いことであるが、各職員間の傾斜配分を考えるのも方法である。先程の職務評価、国家公務員に準じるということであるが、民間と違うのでどこまでそこに手を加えられるのか、計りかねるが、企業であれば、優秀な社員により近づけたい、通常であれば優秀な社員の方が少ないといわれているので、それをどうレベルアップするかということで、各企業では、給料に差をつけている。昔は、平等ということが給与体系では一番重視されたが、今は、公正、公平な処遇が一番重視されている。
よく働く職員には、それに見合う賃金を払う、そうでない職員にはそれなりの賃金という考え方をより一層明確にされて、全体としての給与の削減は良いことであるが、一部では優秀な職員には、賃上げになってもよいのではないか、それが、組織の活性化につながると思う。業務についての、貢献度あるいは、年間の取り組みの評価などでメリハリをつければよいのではと思う。
私どもの例であるが、一年に一度は必ず所属長は各職員に対し面談を行い、その中で、期待度を明示し、併せて、前年度の職務評価の中身を必ず示し、良いところ、こういう課題ができなかったので引下げたなど、どう評価したかを本人に示す。そういうことで、翌年度の業務に取り組む姿勢、貢献度をみるとして、業務の密度をあげている。
時間外勤務の削減はどこにもあることで、私どもでも喫緊の課題である。私の職場では、事前の申請を徹底している。何の目的で量はどれくらいか、その当日の朝、少なくとも昼までに申請を取っている。同じ係の仕事の中で、時間外をする人としない人があれば、業務の公平性に欠けることから、又仕事の段取りが難しくなることから、帰る迄の仕事の内容を把握した上で、全員が早く終れるような対策を講じていることを、参考として申し上げました。
委員
職員の評価という面で一つ危惧を持つ。住民から見て、本当に親切に対応されている職員もいる。厳しい情勢であるので、そういう職員の評価をどうされるのか、書類上のみで評価をされないかという危惧を持ちます。
会長
町の場合今のところ勤務評価はないのですね。
事務局
給与条例の中では、勤勉手当等は評価に基づいて支給するとなっておりますが、現実には適用しておりません。係長及び課長補佐の昇格時に、昇格試験を実施致しておりまして、勤務評価の一部と考えております。
委員
職員数はだんだん減ってきて、現在300名ということだが、生涯学習センターで十数名おられるが、こちらから行かれたのか、生涯学習センターがなければ十数名減らせたということになるのですか。
事務局
生涯学習センターには、旧の図書館また公民館の職員もそのまま移行していますことから、センターができたことによって正職員の増には、そうつながっていません。
ただ、嘱託員やパート職員は増になっています。
委員
平均給料であるが、平均年齢が44.3歳となっていることからこれくらいかなと思う。民間の場合は、一定の年齢に達したら昇給ストップさらに給与ダウンするが、そういうシステムがあるのか、また、一人あたりの残業が、月10時間程度と思うが、一人あたりの残業時間を増やしてでも人数を減らした方が総人件費は節約できると思われる。民間と比べれば、残業の時間数は少ないと思われるので、日頃かなり余裕をもってやられているのかという感じもしています。
事務局
課によって、時間外勤務の非常に多い所とほとんど無い所とばらつきがあります。このばらつきをどう考えるのかまた、残業の少ないところは余裕があるということに結び付けられるのか微妙なところです。
部長
補足ですが、先程各部署毎の適正人員はどのように出しているのかとのお尋ねがありましたが、定期的には行っておりません。残業の偏っている所があるのが現状です。季節的な要因のものもありますが、忙しくやっている所もありそうでない所もあります。職員がだんだん減っていきますが、補充もできないということで今の行政をどのように行っていくか今後の課題です。そういったことから、資料4ページにありますように組織の整備として、統廃合により、スリム化をした組織づくりをしていかねばならないと考えています。
また、グループ制の項目がありますが、まだまだ研究していかなればなりませんが、係毎の壁があります。同じ課の中でも、一つの係が残業しても、他の係が帰宅するという現状があり、こういったことも解消しながら、仕事の効率化を図る必要であります。また、公正、公平な仕事量の配分を検討するということでなく、取り組んでいかなければという危機感を持っております。
事務局
もう一点申し忘れましたが、昇給の関係ですが、現在の給与条例では56歳以上で延伸になりまして、58歳で昇給停止となります。民間と比べまして、年齢が高いところまでいっているかもしれません。
それと、給料表が来年度4月から、また下がります。下がるうえに一回の昇給間差がごく小さなものに、今の一回の昇給を4分割になる改正です。細分化して、勤務評定により昇給の幅に差を持たせる制度に変わります。先程の人事評価にもつながってくるものと考えます。
会長
ということは、勤務評定を実施されるということですか。
事務局
勤務評定の詳細がまだ示されておりませんが、何らかの勤務評定しなければならないと考えています。
会長
時間外勤務手当は、どこでも問題で時間外勤務、休日勤務手当を減らすことが課題である。休日勤務について他の日に休む振替ということを実施されていますか。
事務局
基本的に全て振替を行っています。
会長
資料では、時間外勤務手当が5,144万円であり、一人あたりでは18万円ですが、先程の話にもあったが、時間外勤務をする人が偏っている。極端にいえば、年間50万円以上もらっている人、また年間2・3万円の人もいるかもしれない。
委員の発言にもあったが、昼までに時間外勤務の内容を提出し、課長がきっちり管理することを検討されればと思います。
副会長
庁舎外の現場へ出て行く場合などの把握はどのようにされていますか。
事務局
基本的に課長が課員の管理をしています。時間外勤務につきましては、事前に課長に内容を報告し実施するようになっておりますが、より厳格に運用していきたい。
また、町内の現場等に行くときには課長に報告するようになっています。
会長
実施されていると思うが、時期的に忙しい部署では臨時職員等を一定の期間採用されていますか。
事務局
必要に応じて、日々雇用職員を活用しています。
会長
定員管理、給与の適正化等であるが、田原本町の場合、ラスパイレス指数、地方公務員と国家公務員の給与水準格差についても、県下の中では低く抑えられており、努力されていることが、伺える。厳しい財政状況であるので、定員の削減、時間外勤務の削減などにより、適正な健全な財政状況に近づけるよう努力願います。この項目については、以上で終ります。
これで、本日の予定は終りましたが、次に進みますか。
事務局
次回会議の項目について、説明させていただけますか。
会長
それでは、説明願います。
事務局
引き続き説明をさせていただきます。
4.人材育成の推進です。
分権型社会の担い手にふさわしい人材を育成するため、職員一人ひとりの意識改革を含め、資質の向上、能力の開発などに努め、政策形成能力や課題設定能力を持った人材の育成を計画的に推進し、また、他の地方自治体等との人事交流を行い、多様な人材の確保を図る。
5.公正の確保と透明性の向上
住民に信頼され開かれた行政を確立するため、行政運営における公正の確保と透明性のより一層の向上を図る。
6.電子自治体の推進
情報セキュリティの確保に留意しながら、IT(情報通信技術)の活用とこれにあわせた業務や制度の見直しにより、住民の利便性の向上と行政運営の簡素化、効率化、信頼性及び透明性の向上を図る。
7.自主性・自立性の高い財政運用の確保
(1)経費節減合理化等財政の健全化
国が検討している地方分権のための三位一体改革については大筋ほぼ集約化されつつあるが、具体的財源移譲については、まだ不透明で予断を許さない状況にあり、自主財源の確保と住民負担の公平性の見地からも町税等の収納率のさらなる向上を図り、歳入の確保に努めるとともに、補助金、使用料、手数料公共事業の入札制度の見直しなどにより安定した財政基盤の確立に努め、経費の節減や施策の重点化により財政の健全化を図る。
(2)補助金等の整理合理化
様々な団体等に対する補助金については、その事業効果や目的、団体の状況などを精査し、終期の設定や廃止・縮減を行う。
また、協議会等の負担金についても、その目的、成果が十分達成されているか精査し、当初の意義が薄れているものについては、脱会を検討するとともに、団体の決算報告などを見定め負担金の削減に努める。
(3)公共事業
公共工事については、関係各課と連携を図り、できる限り合冊工事の施工に努め経費の削減を図るとともに、公共工事の入札・契約について、情報の公開等の適正化に資する取り組みを行う。
8.地方議会
地方分権の進展に伴い、議会の果たすべき役割がますます増大しており、これを踏まえた議会運営が一層強く求められている。その一方で議員の定数や報酬に対する批判があり、本町の議会では、議員の定数・報酬について見直しを行い平成17年度から費用弁償の廃止と議員の定数18人から16人に削減を実施する。でありますが、これは実施致しました。
第3、実施期間
大綱に基づく、具体的な事項については、実施計画を作成し、平成17年度から5年間を目途に推進するものとする。
資料の説明ですが、
6.電子自治体の推進につきましては、12ページに、3項目をあげております。
7.自主性・自立性の高い財政運用の確保の(1)経費節減合理化等財政の健全化の項目については、13から18ページまでで削減目標をあげています。
(2)補助金等の整理合理化については、19から21ページに項目があります。
それから、各種団体の補助金の現況について、資料6にあります。
(3)公共工事については、22ページです。
それから、地方議会については、23ページで、これは実施済みの項目であります。
次に、資料7につきましては、14ページ8の施設使用料減免の見直しに関連する現状の資料です。
以上でございます。
会長
どうも有り難うございました。
本日は、色々な貴重なご意見を賜り誠に有り難うございました。
これをもちまして、第2回田原本町行政改革懇話会の協議を終了致します。
次回の会議は、12月22日(木曜日)本会場で1時30分から開催しますので、よろしくお願い致します。本日は、どうも有り難うございました。
懇話会会議録
- この記事に関するお問い合わせ先
-
担当課:企画財政課政策企画係
電話:0744-34-2083